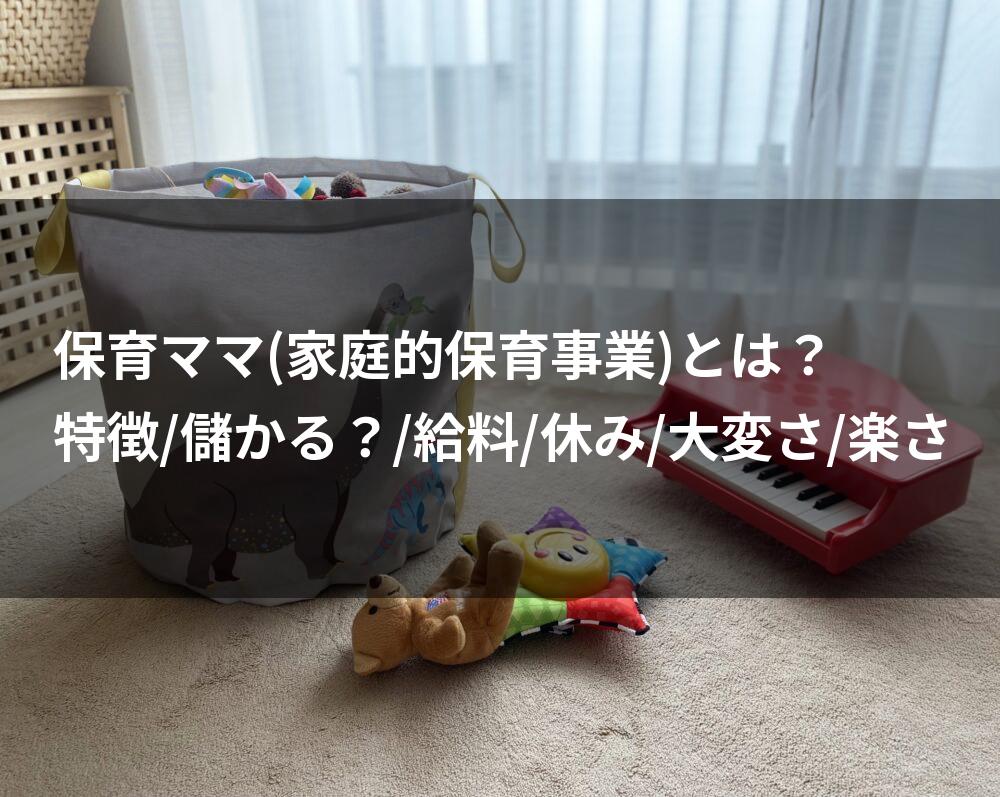| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育ママ(家庭的保育事業)とは? | ・市区町村認可の小規模保育事業で、保育者の自宅等で3歳未満児を5名以下保育 ・待機児童が多い地域で保育施設の代替として活用、家庭的な保育が特徴 ・保育士資格が必要だが、自治体研修で代替可能な場合も ・子ども・子育て支援新制度「地域型保育給付」の対象 |
| こんなひとは保育ママ(家庭的保育事業)はできない | ・就学前の子がいる、または看護・介護が必要な人がいる場合 ・通風採光の良い6畳以上の保育環境が用意できない場合 ・ペットを飼っている、または他に仕事をしている場合 ・自宅での保育となるため、様々な制約がある |
| 保育ママ(家庭的保育事業)になる方法 | ・市区町村が事業を実施しているか、募集があるか確認 ・募集に応募し、必要な書類を揃えて申し込む(面接の場合も) ・市区町村の研修受講後、保育室の視察確認を経て認定を受ける ・市区町村から保育希望者が紹介され、利用者と面談後に利用が決定 |
| 保育ママ(家庭的保育事業)の一日の例 | ・受け入れ、自由遊び、おやつ、外遊び、昼食、午睡、おやつ、自由遊び、お迎え ・保育園と同様のスケジュールだが、子供の年齢や体調に合わせて調整 |
| 保育ママ(家庭的保育事業)は休めない? | ・休暇はきちんと定められており、年次・夏季休暇も計画的に取得可能 ・市区町村が定めた代替保育施設があり、休みや急病時はそこで預かる ・代替保育施設側は補助金を受け取っている |
| 保育ママ(家庭的保育事業)の保育行事は? | ・行事は独自に行うこともある ・運動会など、一部の行事は代替保育施設と合同で行う場合も |
| 保育ママ(家庭的保育事業)の給料は? | ・保育料と市区町村からの補助金が収入源 ・東京都江戸川区の場合、環境整備費や保育補助費が支給 ・人数に応じて月収は変動するが、収入は安定しない可能性も ・個人事業主として国民保険料や税金を自己負担する必要がある |
| 【まとめ】保育ママ(家庭的保育事業)は儲かる? | ・市区町村認可の小規模保育事業で、応募と研修が必要 ・給料は変動制で人数や時間によるため、決して儲かる事業ではない ・自分の経験を活かし、個々に寄り添った保育ができる点は魅力的 ・責任や能力に見合った収入が得られるかは疑問が残る |
| よくある質問(FAQ) | ・子どもが好きで家庭的な保育をしたい人、保育士経験を活かしたい人に向いている ・開業資金は保育室の整備費用や備品購入費などがかかる(補助金制度も) ・安全管理や保護者との連携が大変だが、成長を間近で見守れるやりがいがある ・基本は保育士資格が必要だが、自治体研修で代替可能 ・年齢制限は自治体によるが、25歳〜55歳くらいが多い |
- 保育ママって何?
- 保育ママは儲かるの?
- 大変じゃない?
保育士の皆さん、家庭的保育事業(保育ママ)という働き方をご存知ですか?この記事では、現役保育士の著者が、保育ママの仕事内容や給料、休暇について徹底調査しました。
今回は、保育ママ(家庭的保育事業)について調査してみました。
もちろん、お金だけが目的ではないと思いますが、継続して収入を得られる状況でないと、事業として継続は難しいでしょう。
決して楽とは言えない仕事ですが、子ども一人ひとりに寄り添った保育ができる魅力もあります。

保育ママって本当に儲かるの?

必ずしも高収入とは言えないけれど、やりがいを感じられる仕事だよ
この記事を読めば、家庭的保育事業(保育ママ)について、以下の点がわかります。
- 家庭的保育事業(保育ママ)の概要
- 給料や収入の実態
- 休暇の取得状況
結論としては、保育ママ(家庭的保育事業)は決して儲かる仕事ではありません。
しかし、少ない定員なので、ひとりひとりに寄り添った家庭的な保育を実施できるメリットがある一方、重大な責任も伴います。
保育ママに関しては、市区町村等の自治体の情報を参考にしています
その経験が参考になればと思います
保育ママ(家庭的保育事業)とは?
家庭的保育事業は市町村の認可を受けた家庭的保育事業者が保育者の自宅などで行う小規模な保育の事業です。
地域によっては保育ママと呼ばれている場合があります。
基本的には3歳未満児が対象で、定員は5名以下となっています。
1人の家庭的保育者(保育士)が子ども3人までの保育が可能で、家庭的保育補助者がいる場合にこども5人までを見ることができます。
主に待機児童が多い地域で、新規の保育園を作るのが難しい場合の保育施設の代替として活用されています。
子ども一人ひとりに寄り添った家庭的な保育を提供している点が特徴です。
保育者自身に就学前の子どもがいないことや、看護・介護を必要とする人がいないことが条件となります。
利用基準は、保護者の方が就業していて「3号認定」の子どもが対象になります。
利用料金は市町村によって異なりますが、保育所と同様で保護者の所得に応じた保育料となっています。
家庭的保育事業者は、基本的には保育士資格が必要です。
保育士資格がない場合は、市区町村が実施する研修を受講する必要があります。
また、保育ママ(家庭的保育事業)は、2015年にスタートした子ども・子育て支援新制度「地域型保育給付」の対象になっています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 許認可 | 市区町村が認可 |
| 保育料 | 市区町村が定める(保育所と同等) |
| 定員 | 3人(家庭的保育補助者がいる場合は5人) |
| 年齢 | 3歳未満 |
以下は例として東京都江戸川区の保育ママの就業条件になります。
調査時点の情報になるので最新の情報は必ず市区町村に確認してください。
- (1)乳児を育てた経験のある方(または、保育士・教員・助産師・保健師・看護師の資格がある方)
- (2)健康な25歳~概ね55歳までの女性(55歳を超える場合にはご相談ください)
- (3)日曜・祝日を除く、毎日午前7時30分~午後6時までの保育が可能な方
- (4)保育室として6畳相当の部屋を確保できる方
- (5)就学前のお子さんがいない方
また、すべての市区町村で保育ママ(家庭的保育事業)を募集しているわけではないので注意が必要です。
※参考https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e048/kosodate/kosodate/hoiku/nitijou/mama/naritai.html
こんなひとは保育ママ(家庭的保育事業)はできない
市区町村によって多少基準は異なりますが、多くの市区町村では以下のような方は保育ママになるのが難しいかもしれません。
- 保育者自身に就学前の子供がいる場合
- 看護介護を必要とする人がいる場合
- 通風採光の良い保育環境の6畳以上の部屋が準備できない場合
- ペットを飼っている場合
- 他に仕事をしている場合
多くの市区町村ではこのような基準が定められていることがほとんどです。
保育ママは自宅で保育をすることになるので、様々な制約があります。
保育ママ(家庭的保育事業)になる方法
市区町村によって多少異なりますが、おおまかに以下の手順で保育ママ(家庭的保育事業)を開始します。
- 住んでいる市区町村が保育ママ(家庭的保育事業)を実施しているかを確認する
- 市区町村によっては需要がないため実施していない場合があります。
- 保育ママ(家庭的保育事業)を現在募集しているかを確認する
- 保育ママ(家庭的保育事業)制度を実施していてもすでに定員が足りているため現在募集していない場合があります。
- 保育ママ(家庭的保育事業)の募集に応募する
- 必要な書類や条件を揃えて自治体に申し込みます。面接などを行う場合もあります。
- 市区町村の実施する研修を受ける
- 保育を行う部屋の視察確認
- 市区町村より認定を受ける
- 市区町村より保育を希望する方が紹介される
- 利用者と面談を行う
- 利用が決定する
保育ママは定員は少ないですが、保育園と同等の機能を有することになるのでかなりしっかりとした手順があります。
当然、待機児童が出ていないエリアの場合は需要がないため、保育ママになるのは難しいかもしれません。
待機児童が多い市区町村でも、地域やエリアによっては需要がない場合、保育ママになるのは難しくなります。
あくまでも市区町村が認可ををする必要が利用が想定される児童がいないことには許可されないかもしれません。
保育ママ(家庭的保育事業)の一日の例
基本的には保育園でのスケジュールと変わりませんが、子供の年齢や体調などにあわせて保育ママ(家庭的保育事業)自身でさまざまな保育を提供します。
- 受け入れ
- 自由遊び
- おやつ
- 外遊び
- 昼食
- 午睡
- おやつ
- 自由遊び
- お迎え
保育ママ(家庭的保育事業)は休めない?
保育ママ(家庭的保育事業)は気軽に休めないというイメージもあるかもしれませんが、必ずしもそういうわけではないです。
以下は東京都北区の家庭福祉員(保育ママ(家庭的保育事業))の保育時間になります。
- (1)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日
- (2)年末年始(12月29日から1月3日まで)
- (3)年次休暇(年20日)
- (4)慶弔休暇
- (5)夏季休暇(5日)
休暇がきちんと定められており、その期間は休むことができます。
年次休暇・夏季休暇なども計画的に取得が可能です。
保育ママ(家庭的保育事業)には必ず、市区町村が定めた代替保育施設というものが用意されています。
保育ママ(家庭的保育事業)が休みの場合は、こどもは市区町村が定めた代替保育施設で預かることになっています。
急な傷病の場合なども同様の方法で対処することが可能です。
ちなみに代替保育施設側は、代替保育施設になることで補助金を貰っているので、損をしているわけではありません。
保育ママ(家庭的保育事業)の保育行事は?
保育ママ(家庭的保育事業)の行事などは、独自に行うこともあります。
ですが、一部の行事(運動会)などは人数の兼ね合いで、代替保育施設と合同に行う場合もあります。
保育ママ(家庭的保育事業)の給料は?
保育ママ(家庭的保育事業)が得られる収入は市区町村によって異なります。
基本的には、保育料と市区町村からの補助金が収入になります。
例えば、東京都江戸川区の場合は以下のような金額になっています。
- 環境整備費 月額3万円(2人以上受託の場合には加算あり)
- 保育補助費 月額乳児1人につき7万円
| 人数 | 月収 |
|---|---|
| 1人の場合 | 10万円 |
| 2人の場合 | 20万円 |
| 3人の場合 | 30万円(+加算) |
| 4人の場合 | 40万円(+加算) |
| 5人の場合 | 50万円(+加算) |
年収は保育ママ一人の場合は、最大360万円になります。
家庭的保育事業補助者をつければ最大600万円ですが、補助者への給料も必要となります。
収入は安定しない
定員の人数が必ず毎年割り当てられると決まっているわけではないので、場合によっては一人のみの保育になってしまう可能性もあります。
新規の保育施設ができれば、来年度からはもう必要ありませんということになってしまうリスクもあります。
保育室の整備費用なども一部補助してもらえることも多いですが、せっかく自宅の環境を保育ママ(家庭的保育事業)ができるように整備したのに、事業が継続できず急に収入がゼロになってしまうというリスクもあります。
労働時間も不安定で長い場合もある
保育ママ(家庭的保育事業)は基本的に延長保育にも対応する必要があります。
家庭によって預ける時間が異なりますが、すべての時間に保育を提供しなければなりません。
もちろん基本的には一人なので自分が常に保育を行う必要があります。
つまり、一人で見ている場合は保育ママの就業時間が長くなってしまうこともがあります。
もちろん、延長の保育料は払われますが雀の涙ほどです。
個人事業主になる
一見、定員が満たされれば給料は高いように見えますが、保育ママ(家庭的保育事業)は個人事業主のため、国民保険料・国民年金などは自己負担になります。
確定申告も自分で行い、税金も自分で支払う必要があります。
当然、ボーナスもないので、年収はそこまで保育園に勤務する保育士とは変わらない結果となるかもしれません。
設備にかかる経費も自腹
家庭的保育事業に自宅を利用する場合、子どもを安全に保育できるようにするための設備を揃える必要があります。
市区町村によっては整備費用を補助してくれる場合もありますが、基本的には自己負担となります。
【まとめ】保育ママ(家庭的保育事業)は儲かる?
- 家庭的保育事業は、市区町村の認可を受けた小規模な保育事業
- 保育ママになるには、市区町村への応募と研修が必要
- 給料は保育料と補助金で構成されるが、人数や時間によって変動
保育ママ(家庭的保育事業)は決して儲かる事業とは言えません。
3人の子どもを一人で保育することになるため、責任も重大です。
その一方で、自分の培ってきた経験を活かし、自分のやり方でひとりひとりに寄り添った保育ができるのは魅力的でしょう。
基本的に一人で保育園の機能を運営することになるため、責任は重大です。
そう考えると、その責任や能力に見合った収入が得られるか疑問が残ります。
収入は自治体によって異なり、稼げる自治体もあるかもしれないため、きちんとした下調べが必要です。
保育ママ(家庭的保育事業)の特徴を理解して、ご自身の働き方やキャリアプランに合うか検討してみましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育ママ(家庭的保育事業)はどんな人が向いていますか?
- A
子どもが好きで、家庭的な雰囲気の中で子ども一人ひとりに寄り添った保育をしたい方に向いています。保育士としての経験を活かし、自分の裁量で保育をしたい方にもおすすめです。
- Q保育ママ(家庭的保育事業)の開業資金はどれくらい必要ですか?
- A
保育室の整備費用や備品購入費などがかかります。市区町村によっては補助金制度があるので、事前に確認するようにしましょう。
- Q保育ママ(家庭的保育事業)の仕事で大変なことは何ですか?
- A
少人数とはいえ、子どもたちの安全管理や健康管理に責任を持つ必要があります。保護者との連携やコミュニケーションも重要になるため、様々な場面で気を使うことが多いかもしれません。
- Q保育ママ(家庭的保育事業)のやりがいは何ですか?
- A
子どもたちの成長を間近で見守り、一人ひとりの個性を尊重した丁寧な保育ができることです。「先生のおかげで成長できました」と保護者から感謝されることもあり、大きなやりがいを感じられます。
- Q保育ママ(家庭的保育事業)の資格は必要ですか?
- A
基本的には保育士資格が必要です。保育士資格がない場合は、市区町村が実施する研修を受講することで、保育ママとして働くことができます。
- Q保育ママ(家庭的保育事業)の年齢制限はありますか?
- A
市区町村によって異なりますが、25歳〜55歳くらいまでとしているところが多いようです。ただし、55歳を超える場合でも相談可能な場合もあります。