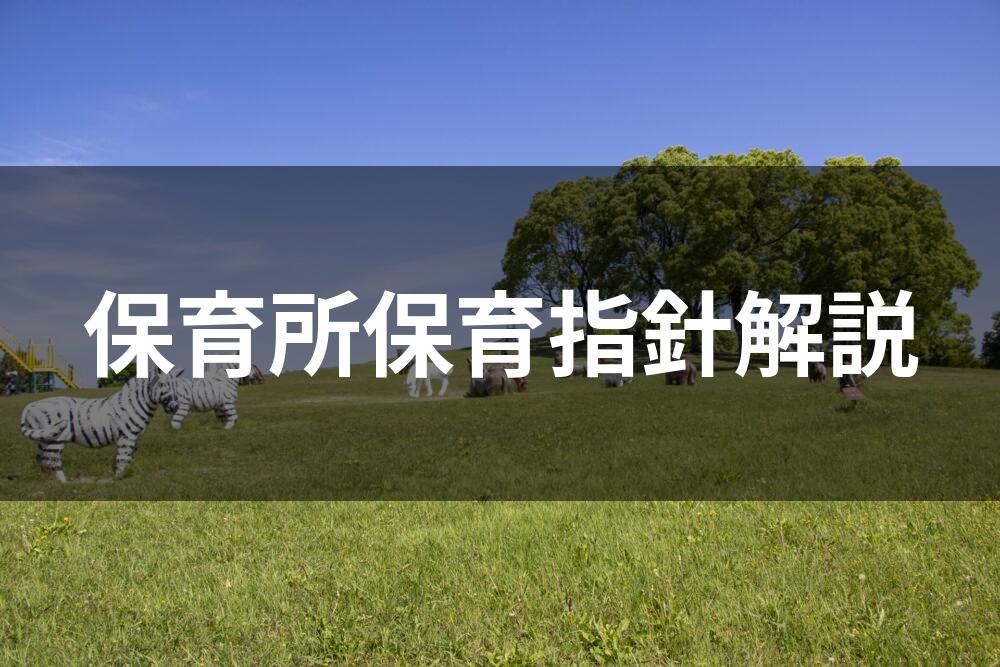| 目次 | 内容 |
|---|---|
| そもそも保育所保育指針ってなに? | ・日本の保育所における基本的な運営指針 ・厚生労働省が定める、保育園の運営や保育士が保育をする上での基本的な考え方を記述 ・幼稚園や認定こども園には別の指針があるが、2018年改訂で幼児教育内容は共通化 |
| 保育所保育指針の概要 | ・全5章で構成され、保育の基本原則、具体的な保育目標、子どもの健康と安全、保護者への支援、職員の専門性向上を定義 ・各章は保育園および保育士が質の高い保育を行うための指針 ・詳細は子ども家庭庁のウェブサイトで確認可能 |
| 保育所保育指針は改訂される<最新の改訂は2018年> | ・社会情勢の変化に伴い定期的に改訂 ・直近の改訂は2018年3月で、およそ10年ごとの見直し傾向 ・2015年施行の「子ども・子育て支援新制度」や1、2歳児の保育所利用増加など、保育環境の変化を反映 |
| 最新の改訂<2018年>の内容や要旨は? | ・乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載を充実 ・保育所保育における幼児教育を積極的に位置付け ・健康や安全の記載見直し、保護者・家庭・地域連携の子育て支援を明記 ・職員の資質・専門性の向上を重視 |
| 保育所保育指針の最新版はどこで手に入る? | ・子ども家庭庁がインターネット上で公開しており、ダウンロード可能 ・「保育所保育指針」と「保育所保育指針解説」をウェブで入手できる ・勤務先の保育園にも冊子版が置かれている場合が多い |
| 保育士として迷った際は保育所保育指針に立ち返ると良いかも | ・保育方針、理念、保育観などで迷った際のよりどころ ・園の方針や同僚との意見の違いが生じた際、基本指針として確認 ・自身の保育や園の運営を客観的に見直し、間違いに気づくきっかけ |
| 保育所保育指針を軽視している保育園は要注意 | ・質の面で不安がある保育園には注意が必要 ・園長や施設長が指針の理解や改訂の趣旨に無関心な場合、事故や災害への備えが不十分なリスクがある ・一般と異なる保育が身につき、転職時にトラブルにつながる可能性 |
| 保育士資格があるからOKというスタンスではいけない | ・保育士資格に更新制度はないが、自己研鑽は不可欠 ・今後の保育士不足緩和により、経験年数だけでなく質の向上がより重要に ・国の示す指針を理解し、専門性向上への姿勢が求められる |
| 【まとめ】保育所保育指針は保育士のバイブル! | ・保育士にとって日々の保育を実践する上で最も重要な共通指針 ・概要、2018年改訂ポイント、最新版入手方法を理解する内容 ・保育士自身の成長と安全な保育実践に不可欠な道しるべ |
| よくある質問(FAQ) | ・最新版は2018年改訂が全体改訂で、運用に関するQ&Aや通知は随時公開中 ・公式解説書は実践ポイントを解説し、主要書店やオンラインで購入可能 ・幼児教育の方向性や養護と教育の一体性を理解し、遊びや生活を通じた子どもの能力育成を実践 ・指針を深く理解するには、全体像と改訂点の把握、自身の保育との照らし合わせが重要 ・幼稚園や認定こども園の指針は管轄が異なるが、幼児教育の骨格は共通で、今後も社会情勢に応じ見直される可能性あり |
- 保育所保育指針ってなに?
- 最新版はどこで手に入る?
保育士のみなさんにとって、保育所保育指針は日々の保育を実践する上で最も重要な共通指針です。
この記事では、保育士のみなさんが改めて保育所保育指針の概要、2018年の改訂内容のポイント、そして最新版の入手方法を分かりやすく解説します。

忙しくてなかなか時間を取れないけれど、最新の保育所保育指針の改訂点や入手方法を効率よく知りたいです。

このガイドを読めば、すぐに疑問を解決し、保育実践に役立てることができます。
保育所保育指針は厚生労働省が出している保育園向けの指針です。保育士本人も保育所の基本である保育指針は必ず理解しておくべき内容だと思います。
そもそも保育所保育指針ってなに?
保育所保育指針は1965年に最初に制定された日本の保育所における基本的な運営指針になります。保育所保育指針は厚生労働省によって定められています。
保育所保育指針とは何かは、厚生労働省の保育所保育指針解説に以下のように述べられています。
保育所保育指針は、保育所保育の基本となる考え方や保育のねらい及び内容など保育の実施に関わる事項と、これに関連する運営に関する事項について定めたものである。
つまり、保育所保育指針には、保育園の運営者はもちろん、保育士が保育をする上で基本とすべき考え方などが記載されています。
多くの保育園はこの保育所保育指針も基本的なベースとして、それぞれ保育理念や保育観を掲げていることになります。逆にいうと、
保育士本人も保育所の基本である保育指針は必ず理解しておくべき内容になります。
幼稚園は「幼稚園教育要領」認定こども園は「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」は別に定めらている
ちなみに余談にはなりますが、幼稚園は「幼稚園教育要領」が、認定こども園は「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」はそれぞれ別に定められています。保育所とは管轄や役割が異なるので、それぞれに指針がある形になります。
直近でこれらの施設形態を跨いで、転職をしたという方はそれぞれを見比べてみると良いと思います。
ただし、2018年の保育所保育指針と合わせて、幼稚園の「幼稚園教育要領」、認定こども園の「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」も改定されていて、幼児教育の内容については共通化されています。
そのため、幼稚園から保育園に転職した、保育所から認定こども園に転職したというような場合でも、幼児教育の内容は同一なので、今までの指針とまるっきり内容が変わってしまうということは無いので、その点は安心してください。
保育所保育指針の概要
保育所保育指針は以下の目次構成となっています。
第1章 総則
第2章 保育の内容
第3章 健康及び安全
第4章 子育て支援
第5章 職員の資質向上
第1章の総則には、保育所保育に関する基本原則、養護に関する基本的事項、保育の計画及び評価、幼児教育を行う施設として共有すべき事項などについて書かれています。
第2章はの保育の内容では、第一章の保育所保育に関する基本原則の「保育の目標」に関してより具体的な内容を定義しています。
第3章では、子どもが健康で安全に過ごすための指針を定義しています。
第4章では、保育所における保護者に対する子育て支援について定義しています。保育所は、子育て支援の場でもあります。
そして、第5章では、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上について記載されています。まさに保育園及び保育士がどのように保育の質を担保していくべきかという点になります。
より詳細については、[保育所保育指針の解説(子ども家庭庁)](https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/36b55701/20231016_policies_hoiku_66.pdf)を確認してください。
保育所保育指針は改訂される<最新の改訂は2018年>
厚生労働省によって出されている保育所保育指針は定期的に改訂されています。これは、時代などの変化における子育て環境の変化などに伴い、保育所のあり方も変化しているためです。
直近の改訂は2018年3月になっています。その前の改訂が1990年、2000年、2008年という風になっているので、およそ十年ごとに改訂がなされています。
とりわけ2018年の改訂では、2015年から施行されている「子ども・子育て支援新制度」の影響も大きく受けているとされています。この制度は、「量」と「質」の両面から子育てを社会全体で支えるということが主たる趣旨の制度になります。
そのため、1、2歳児を中心に保育所利用児童数が増加している背景などもあり、保育をめぐる状況の変化が反映されている形になります。
最新の改訂<2018年>の内容や要旨は?
最新の改訂<2018年>では以下の内容の改訂が行われています。
(1)乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実
(2)保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ
(3)子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直し
(4)保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性
(5)職員の資質・専門性の向上
乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実については、先程も書いたように、1、2歳児を中心に保育所利用児童数が増加していることから記載の充実が図られています。
また、東日本大震災などの災害の影響もあり、子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直しも行われています。
また、特質すべき点としては、保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性についてです。「保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努める」ことを明記して記載内容が整理されています。
より詳細については、https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/36b55701/20231016_policies_hoiku_66.pdfを確認して下さい。
保育所保育指針の最新版はどこで手に入る?
保育所保育指針の最新版は子ども家庭庁がインターネット上で公開しています。以下からダウンロード、参照することが可能です。
- [保育所保育指針(子ども家庭庁)]([保育所保育指針解説書について(子ども家庭庁)](https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/))
また、子ども家庭庁は合わせて、保育所保育指針の解説も公開しています。解説ではよりわかりやすく保育所保育指針について説明しています。
手っ取り早く確認したい場合は、これらを利用すると良いと思います。また、現在、保育園に勤めている場合は、その勤めている保育園にも、必ず冊子化されている保育所保育指針が置かれていると思います。
保育士として迷った際は保育所保育指針に立ち返ると良いかも
働く保育士としては、なにか保育方針、理念、保育観などで迷った場合は、まずは保育所保育指針に立ち返ると良いかもしれません。
保育士として現場で働いていると同僚や先輩などと考え方が合わなかったり、園の方針や考え方にどうしても納得できないということはよくあることだと思います。
園の保育理念や個人の保育観には正解・不正解がない場合が多いですが、保育所保育指針はすべての保育園がベースにしている指針になります。
改めて保育所保育指針に立ち返ることで、自分や保育園の間違いに気づくことができるかもしれません。
保育所保育指針を軽視している保育園は要注意
働く保育士の目線では、保育所保育指針を軽視する保育園のリスクです。特に最近では、保育の定員を確保するために保育所がかなりの勢いで乱立していて、質の面で不安がある保育園もあるようです。
特に、園長や施設長などの園の代表者が改訂の趣旨を理解していなかったり、無関心である場合には注意が必要です。
例えば、保育所保育指針には子どもが安全に過ごすための、事故や災害への備えに関しても記載がされています。なにか事故が起きてしまった際に、現場の保育士として責任を取らされてしまうこともあるかもしれません。
また、すべての保育園は保育所保育指針を基準として、保育園の運営につとめていると思うので、普通の保育園ではありえない保育士としての行いなどが身についてしまっているかもしれません。転職した際などに、そのような行いをしてしまってなにかトラブルなどの原因になるかもしれません。
- マイナビ保育士
 |全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです! - ジョブメドレー保育士
 | 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)

※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。
転職の際などは、保育園の保育所保育指針の考え方や理解度などについても、保育理念などと合わせて聞いてみると良いかもしれません。
保育士資格があるからOKというスタンスではいけない
保育士の資格には、現在のところ更新制度などは存在しませんが、保育士資格があるからOKというスタンスではいけないです。
現状の保育士の待遇などに不満がある場合でも「保育所保育指針の改訂とかは知らないです。保育士資格を持っています。経験年数も長いです。国は給料上げてください」では通らないと思います。
おそらく、これからは保育士不足もやや落ち着く時代になってくると思います。その際には、今のようにとりあえず経験年数があれば処遇改善費として給料を上乗せして貰えるという時代ではなくなってくるかもしれません。
そうなったら、国の掲げる保育所保育指針をしっかり理解して質の向上に務める姿勢も保育士としてより重要になってくるかもしれません。
まとめ
保育所保育指針は、日々の保育を実践する上で最も重要な保育士の共通指針です。
この記事では、指針の概要、2018年改訂のポイント、そして最新版の入手方法について解説しました。
保育所保育指針は日本の保育所における基本的な運営指針になります。すべての保育園では、この指針をもとに運営がなされているはずです。
そのため、保育士本人も保育所の基本である保育指針は必ず理解しておくべき内容になります。
保育所保育指針の最新版は厚生労働省がインターネット上で公開しているので、すぐに参照できますし、保育園にも必ずあると思います。
保育所保育指針を軽視している保育園は要注意ですし、保育士本人も保育士資格があるからOKというスタンスではいけません。
経験を積んで改めて見返してみると新たな理解を得られることもあるかもしれません。保育所保育指針は保育士のバイブルとも言える大切な共通指針になるので、改めて理解しなおしてみると良いと思います。
保育所保育指針は、あなたの保育をより良くするための大切な道しるべです。
この機会に改めて指針を読み解き、日々の保育実践に活かしていきましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育所保育指針の最新版は2018年改訂とのことですが、それ以降に細かな変更や通知は出ていないのでしょうか?
- A
はい、保育所保育指針の最新の全体改訂は2018年(平成30年)4月1日施行されたものになります。
指針本文そのものが頻繁に全面改訂されるわけではありません。
しかし、厚生労働省からは、指針の運用に関するQ&Aや追加の通知が発出されることがあります。
これらは指針本文を「改訂」するものではなく、現在の指針をより適切に実践するための補足情報です。
常に厚生労働省のウェブサイトを確認すると良いでしょう。
- Q保育所保育指針の公式「解説書」は、どのような内容で、どこで購入できますか?
- A
公式の解説書は、厚生労働省編『保育所保育指針解説』として発行されています。
この解説書は、指針のねらいや内容、背景をより深く読み解き、日々の保育実践に役立てるためのポイントが具体的に解説されています。
購入は、全国の主要な書店やオンライン書店で可能です。
主な発行元としては、全国社会福祉協議会やフレーベル館などが挙げられます。
- Q2018年改訂で特に重視された「幼児教育の方向性」や「養護と教育の一体性」について、保育士はどのように日々の保育に活かせば良いですか?
- A
2018年改訂では、「幼児教育の方向性」として「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示され、子どもたちの資質能力の育成が重視されています。
また、「養護と教育の一体性」は、生命の保持と情緒の安定を図る「養護」と、健やかな発達を促す「教育」が、車の両輪のように連携して行われることの重要性を示しています。
保育士向けの実践としては、遊びを通して非認知能力を育むこと、そして、食事や睡眠といった生活習慣の援助がそのまま学びにつながるよう意識することがポイントになります。
- Q保育所保育指針の内容を深く「読み解き」、理解するための「ポイント」は何ですか?
- A
保育所保育指針を深く読み解き、理解するためのポイントは、まず全体像を把握することです。
総則、保育の内容、健康及び安全、子育て支援、職員の資質向上という章立てを理解し、それぞれが保育にどう関わるかを知ることが大切です。
次に、2018年改訂で追加・強化された乳児・1歳以上3歳未満児の保育、保護者連携、地域連携、発達の連続性などの視点を持つことが重要です。
また、自身の保育実践を振り返りながら、指針の記述に照らし合わせて考えることで、より深い理解につながるでしょう。
- Q幼稚園の「幼稚園教育要領」や認定こども園の「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」も2018年に改訂されたとのことですが、これらは保育所保育指針とどう違うのですか?
- A
幼稚園教育要領と幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、それぞれ幼稚園と幼保連携型認定こども園の教育・保育の基準を定めたものです。
これらも2018年改訂が最新版で、保育所保育指針と合わせて解説がされています。
主な違いは、管轄が異なること、そしてそれぞれの施設種別に合わせた運営に関する内容が含まれる点です。
しかし、幼児教育の方向性や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」といった幼児教育の骨格となる内容は、保育所保育指針と共通しています。
そのため、施設形態が変わっても、保育士としての基本的な考え方は大きく変わりません。
- Q保育所保育指針は、今後も定期的に「改訂」される予定はありますか?
- A
保育所保育指針は、社会情勢の変化や子どもの育ちを取り巻く環境の変化に応じて、定期的に改訂されてきました。
これまでの傾向を見ると、およそ10年程度のスパンで全体的な見直しが行われています。
現時点では、次回の改訂がいつになるという具体的な発表はありません。
しかし、子どもや子育てを取り巻く状況は常に変化しているため、今後も必要に応じて見直しが行われる可能性はあるでしょう。
保育士としては、常に最新の情報を得るように心がけ、指針の内容を解説した情報を参照することが大切です。