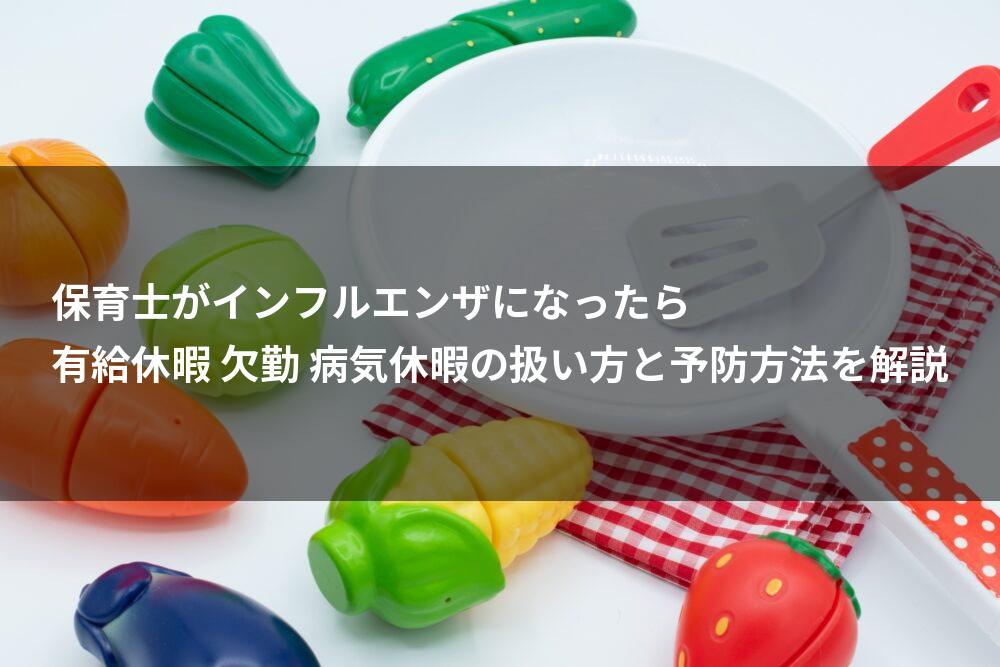| 目次 | 内容 |
|---|---|
| インフルエンザって? | ・ウイルスによる呼吸器感染症 ・風邪より重症化しやすく症状が急に出現 ・高熱や全身の倦怠感などを伴う ・乳幼児や高齢者は合併症の可能性 |
| インフルエンザの流行時期 | ・主に毎年12月から3月頃 ・流行する時期は年によって変動 ・自治体からの流行情報に注意 |
| インフルエンザと風邪の違い | ・原因となるウイルスの種類が違う ・インフルエンザは感染力が高い ・インフルエンザは風邪より症状が重いことが多い |
| 保育士のインフルエンザの予防方法 | ・国の感染症対策ガイドラインを確認 ・予防接種、手洗い、うがい、換気を徹底 ・人混みを避ける対策 ・食事、睡眠、ストレス管理で免疫力アップ |
| 保育士がインフルエンザにかかったら出勤停止? | ・法律で定められた規則はない、園の判断による ・感染症のため出勤停止とする園が多い ・園児基準(解熱後2〜3日)に準じ休むことが一般的 ・回復してからの出勤で感染拡大防止 |
| 保育士のインフルエンザでの休みは有給休暇、欠勤、病気休暇のどれにあたる? | ・勤務先の保育園の規則による ・有給休暇消化、病気休暇、欠勤のいずれか ・病気休暇では医師の診断書が必要な場合あり ・有給がない場合は欠勤となり給料が減る |
| 家族がインフルエンザになった場合は? | ・保育士本人に症状がなければすぐ休む必要はない ・普段以上に感染予防対策を徹底する ・自身に症状が出たら病院を受診し検査 |
| 無理やり出勤させる・するという行為は救いようがない | ・感染を隠して出勤することは危険な行為 ・子どもや他の職員へ感染を広げるリスクがある ・問題が起きた場合責任を問われる可能性 ・インフルエンザ罹患時は正直に報告し休暇取得 |
| まとめ:保育士のインフルエンザ。有給休暇、欠勤、病気休暇扱いは?予防方法も解説! | ・休暇の扱いは園の規則による ・予防接種や日常の対策が重要 ・罹患時は無理せず回復優先 ・診断書の要否など園の規定確認が必要 |
| よくある質問(FAQ) | ・病気休暇なしの場合の休み方、診断書の要否など様々な疑問への回答 ・休む期間や家族罹患時の対応 ・出勤強要された際の対処法や園での予防策も解説 |
- 保育士がインフルエンザになった場合どのような扱いになる?
- 有給休暇、欠勤、病気休暇などはどうすれば良い?
- インフルエンザの予防方法が知りたい!
- インフルエンザなのに出勤を要求された。
インフルエンザは保育士が毎年悩まされる感染症であり、予防が非常に重要です。
この記事では、インフルエンザにかかった場合の休暇(有給休暇、欠勤、病気休暇)の扱いや予防方法について解説しており、その扱いは園によって異なります。

インフルエンザになったらどんな休暇の扱いになるの?どう予防したらいい?

この記事で、その疑問にお答えします
- インフルエンザと風邪の違いや流行時期
- 保育士が行うべき具体的なインフルエンザの予防方法
- 保育士がインフルエンザにかかった場合の休暇の扱い(有給・欠勤・病気休暇)
- 罹患時の無理な出勤のリスク
その経験が参考になればと思います
インフルエンザって?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症。風邪に比べて症状が重く、乳幼児や高齢者では重症化することもあります。
風邪と間違われやすいインフルエンザですが、風邪に比べて高熱が出て、のどの痛みだけでなく、関節痛や筋肉痛を伴います。
さらに風邪の場合ゆっくり症状が出てくるのに対して、インフルエンザは急激に症状が出てきます。症状が出る部位も局所的ではなく、全身に倦怠感が現れるのも特徴です。
潜伏期間は1~4日(平均2日)で多くの場合1週間程度で治りますが、乳幼児や高齢者、基礎疾患を持つ方の中には、肺炎を併発したり、基礎疾患の悪化を招く場合があります。
※ 参照元 https://family.saraya.com/kansen/influenza/index.html
インフルエンザの流行時期
インフルエンザの流行時期は毎年12月から3月頃となっています。時期は毎年微妙に異なることがあります。この時期を迎える前に予防接種の受付も開始されます。昨今でいうとその他の感染症が流行しインフルエンザがほとんど流行しないということもありました。
インフルエンザの流行の具体的なタイミングは自治体などからもインフルエンザ流行情報も発出されるので注意して確認しておくことをおすすめします。
インフルエンザと風邪の違い
インフルエンザと風邪の違いは、ウイルスの違いになります。
インフルエンザウイルスによって引き起こされるのがインフルエンザになります。ちなみにインフルエンザウイルスにもA型・B型・C型等様々な種類があり、年によって流行も異なります。
一般的に風邪よりも感染力が高く、症状も重い場合が多いのがインフルエンザになります。
保育士のインフルエンザの予防方法
子ども家庭庁が「保育所における感染症対策ガイドライン」を発出しているので基本的にはそちらを確認しましょう。
※参考「保育所における感染症対策ガイドライン」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/c60bb9fc/20230720_policies_hoiku_25.pdf
予防接種を受ける
インフルエンザの予防接種で一番効果が期待できるのが、ワクチンによる予防接種になります。最近では保育園でも、予防接種の費用を負担してくれる園が多いです。価格としては5千円前後が多いでしょう。
基本的には一回のワクチンの接種になりますが、さらに効果を増やすために2回接種を行なうことも可能です。
予防接種は完璧にインフルエンザの感染を防げるというわけではないですが、感染した場合の症状を緩和する効果も期待できます。
インフルエンザの予防接種は早ければ、9月頃から受付を開始しています。昨今は、インフルエンザの予防接種がとても人気が高く、各医療機関でも早期に予防接種のワクチン不足が見られるので注意しましょう。
手洗い・うがいをする
インフルエンザに関わらず、手洗い・うがいは感染症の予防にとても重要です。帰宅後、食事前などに必ずうがい手洗いを徹底しましょう。また、うがいでのどを潤すことで、喉の抵抗力を高めるという効果もあります。
保育室の換気をする
インフルエンザのウイルスは咳やくしゃみで吐き出された場合、その場に数時間滞留しているというデータもあるようです。そのため保育室を定期的に換気するということは重要です。冬などは特に寒さを気にして換気がおざなりになりがちなので、より注意が必要です。
人混みを避ける
満員電車などの人混みはインフルエンザなどの感染の可能性が高いポイントになります。インフルエンザは飛沫感染と言って、感染者のくしゃみや咳などで感染するため、人が多い人混みは要注意になります。
保育士は特にインフルエンザの流行時期は満員電車などの人混みは避けたほうが良いです。どうしても人混みに行く必要がある場合は、マスクなどを着用して、うがい手洗いを徹底しましょう。
免疫力を高める
インフルエンザなどの感染症を予防するには、菌を取り込まないことも大切ですが、体の免疫力を高めることも重要です。以下にあげる対策などを講じることで体の免疫力を高めることができます。
栄養をしっかり取る
バランスの良い食事で栄養をしっかり取ることも重要です。インフルエンザの予防に限らず、良い体調を維持する上でも大切なことになります。
睡眠をしっかり取る
睡眠時間に関しても体の免疫力に影響を与える要素になります。人にもよると思いますが、少なくとも7時間程度の睡眠を毎日取ることで免疫力の向上に効果が期待できます。
ストレスを軽減する
精神的なストレスというのも、体の免疫力に大きな影響があります。定期的にストレスを発散して溜め込まないことも重要です。
保育士がインフルエンザにかかったら出勤停止?
インフルエンザにかかった子どもは登園禁止という形になりますが、保育士に関しては特に法律などで規定がありません。そのため、各保育園の判断に委ねられていることになります。感染症なので基本的には出勤停止という扱いをしている園が多いでしょう。
ちなみに保育園に登園する園児たちの基準は以下になります。
インフルエンザの出席停止期間の基準 「“発症した後5日を経過”し、かつ“解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過”するまで」
※ 厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」より
このように園児に対しての基準は設定されていますが、保育士の場合も同様で多くの保育園では保育士がインフルエンザにかかった場合は、熱が下がり一定期間が経過した場合に出勤可能とすることが多いです。
解熱後に体力的に問題がなくても、インフルエンザの菌を保持していてさらなる感染拡大を防ぐ狙いがあります。
保育士のインフルエンザでの休みは有給休暇、欠勤、病気休暇のどれにあたる?
保育士がインフルエンザで休む場合に、有給休暇、欠勤、病気休暇のどれにあたるのかについては保育園の規定によって異なります。
そのため、有給休暇を消化させる場合や病気休暇という形で、有給休暇とは別に病気休暇という形で 有給での休暇を設けている 場合もあります。
これらは保育園によって様々なので規定を確認してみましょう。
当然、病気休暇のような規定がない場合で、有給休暇が残っていない場合は「欠勤」という扱いになってしまいます。欠勤の場合は、その月に支払われる基本給が休んだ日数分少なくなります。
ただ、感染症の病気による欠勤になるので、給与やボーナスの査定に関わるということはあまり考えにくいです。しっかりと予防をしていてインフルエンザにかかってしまうのは致し方ないことではあります。
病気休暇の場合に診断書は必要?
インフルエンザに感染した場合に病気休暇など、有給休暇とは別に有給での休暇になる場合は診断書の提出を求められる場合があります。
これについては、インフルエンザと嘘をついて休むことを防止するという狙いがあると思います。休んだ分の給料が支払われることになるので、当然と言えば当然です。
医師の診断書というのは意外と高額(2〜4千円程度が必要)なので注意しましょう。また、園によってはインフルエンザということがわかる「薬の明細」や「レシート」などでも代用できる場合もあるので、確認してみましょう。
有給休暇を消化する場合は特に診断書などは必要がない場合はほとんどですが、次回の出勤の際に医師の診断書(出勤可能である証明)が必要な場合もあるので、そちらが必要かどうかについても勤務している保育園に確認してみましょう。
家族がインフルエンザになった場合は?
家族がインフルエンザになった場合などは、すぐに出勤を取りやめる必要はないです。今まで以上に感染への予防に気を使い、保育士本人に感染が広がらないように注意しましょう。熱や体への倦怠感などが生じた場合はすぐに病院に行きインフルエンザではないかどうかの確認も必要です。
無理やり出勤させる・するという行為は救いようがない
もし勤務している保育園がインフルエンザでも無理やり保育士を出勤させるような環境になっている場合は、改善が必要です。
園長から出勤しろという具体的な指示がなくても園の雰囲気として出勤せざるを得ないような雰囲気が形成されている場合も同様です。
もし重要な行事などがある場合でも、インフルエンザであることを黙って園長などに報告せずに出勤することは不適切な行動です。
保育士がインフルエンザであることを隠して出勤して、子どもに移るなど何か問題が発生した場合は責任をとることになります。場合によっては懲戒免職処分などもあり得ます。
自分の身を守るためにも、園長などにインフルエンザになったことをしっかりと告げて休暇の取得を申し出ましょう。
免疫力の低い子どもはもちろん、大人であっても死に至る可能性があるのがインフルエンザというものです。
職員が足りないからといって無理やり出勤させて子どもや他の保育士に感染が拡大してしまっては意味がありません。
どんな状況であっても、インフルエンザにかかってしまったら菌がなくなるまでは出勤しないのが正しい行動です。
まとめ:保育士のインフルエンザ。有給休暇、欠勤、病気休暇扱いは?予防方法も解説!
保育士にとってインフルエンザは重要な課題です。
この感染症にかかった場合の休暇の扱い方と予防方法について詳しく解説しました。
- インフルエンザ罹患時の休暇は有給休暇、病気休暇、欠勤など園の規定により対応が異なる
- 予防接種や手洗い・うがい、換気など日常の予防が非常に効果的です
- インフルエンザにかかったら無理に出勤せず回復を優先することが大切です
- 診断書の提出を求められる場合があるため園の規定を確認する必要があります
保育士も毎年悩まされるインフルエンザは 予防が重要 です。以下の予防方法が効果的です。
- 予防接種を受ける
- 手洗い・うがいをする
- 保育室の換気をする
- 人混みを避ける
- 栄養をしっかり取る
- 睡眠をしっかり取る
- ストレスを軽減する
保育士がインフルエンザで休む場合の扱いは保育園によって様々です。有給休暇の消化になる場合や別途病気休暇での休みになる場合もあります。医療機関の診断書などが必要になる場合もあるので注意しましょう。
また、保育園の方針などでインフルエンザでも休めない、出勤を強要されるような環境は救いようがないので転職を検討したほうが良いです。
- マイナビ保育士
 |全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです! - ジョブメドレー保育士
 | 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)

※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。
ご自身の園の規則を確認し、ご紹介した予防策をぜひ参考にしてみてください。
よくある質問(FAQ)
- Qインフルエンザで休む場合、病気休暇がない園ではどうなる?
- A
園に病気休暇の制度がない場合、インフルエンザで休む際は有給休暇を消化することになります。
有給休暇が残っていない場合は欠勤扱いになり、その期間の給与は支払われません。
ただし、感染症による欠勤が給与やボーナスの査定に直接影響することは少ないです。
ご自身の園の就業規則を確認してください。
- Qインフルエンザで休む場合に診断書はいつも必要?
- A
病気休暇などの特別休暇を利用する場合、多くの園では医師の診断書の提出が必要です。
これはインフルエンザの感染を確認し、休暇を適切に管理するためです。
診断書の作成には費用がかかります。
園によっては薬の明細書などで代用できる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
有給休暇で休む場合は診断書が不要なことが多いですが、復帰時に出勤可能であることを証明する診断書が必要な場合もあります。
- Qインフルエンザにかかったら何日間くらい休む必要がある?
- A
園児の場合、インフルエンザは発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児の場合は3日)を経過するまでが出席停止期間の基準です。
保育士についても、法律で明確な日数が定められているわけではありませんが、園児の基準に準じて、解熱後一定期間は出勤停止とする園が多いです。
熱が下がってもウイルスが体内に残っている可能性があるため、感染拡大を防ぐためにもしっかりと回復してから出勤します。
具体的な休む期間は園の規定に従います。
- Q保育士が家族のインフルエンザで休むことはできる?
- A
家族がインフルエンザにかかっても、保育士本人に症状がなければすぐに出勤を取りやめる必要はありません。
今まで以上に手洗いやうがいなどの感染予防に努めます。
もしご自身に発熱や倦怠感などインフルエンザのような症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診し検査を受けてください。
インフルエンザ感染が確認された場合は、ご自身の罹患として休暇を取得します。
- Qもしインフルエンザでも出勤するよう言われたらどう対応すべき?
- A
インフルエンザにかかっているにも関わらず出勤を強要されることは、絶対に受け入れてはなりません。
大切な行事があっても、感染を隠して出勤することは子どもたちや他の職員への感染リスクを高める大変危険な行為です。
万が一、感染が広がるなどの問題が発生した場合、責任を問われることになります。
まずは園長や管理者にインフルエンザに罹患したことを正直に伝え、休暇の取得を申請してください。
回復するまで無理せず休むことが、ご自身の身と子どもたちの健康を守るために最も重要です。
- Qインフルエンザ予防のために保育園で特に気を付けるべき点は?
- A
インフルエンザ予防には、保育園での日常的な対策が非常に大切です。
子どもたちと一緒に手洗いやうがいを徹底し、正しく行う習慣をつけましょう。
保育室の定期的な換気も重要です。
集団生活の場では感染が広がりやすいため、子どもたちの体調変化に注意を払い、少しでも異変を感じたら早めに対応することも感染拡大を防ぐために必要です。
予防接種なども効果的です。