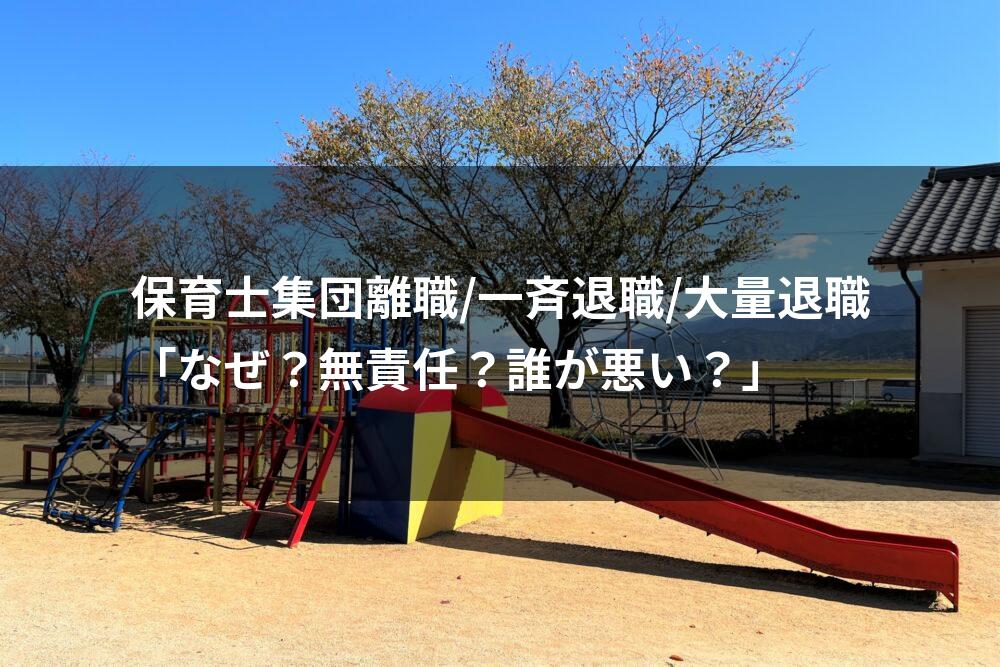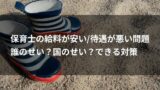| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育士の一斉退職・離職の事例 | ・中央区、目黒区、横浜市、浜松市などで発生 ・長時間労働、給与低下、運営会社との認識ずれ、パワハラなどが原因 ・一斉退職はニュースになる事例だが、大小含めると毎年のように各地で発生 |
| 集団離職をする保育士は無責任ではない | ・職業選択の自由が憲法で保障されている ・給与や人間関係に不満があれば転職は当然の権利 ・経営者には労働環境改善の責任がある ・認可保育園を監督する自治体にも責任がある |
| 集団離職はブラック保育園に対してかなり有効 | ・慢性的な人手不足により運営が困難になる ・ニュースで報道されることでイメージが低下する ・保育士不足で運営縮小や閉鎖に追い込まれる可能性も ・保育士の待遇改善につながる可能性 |
| 預ける保護者もリスクを留意しておくべき | ・保育士の労働環境が悪い保育園もある ・保護者の評判が良い保育園でも注意が必要 ・転園を余儀なくされる可能性も考慮すべき ・保育業界の改善には保護者の働きかけも重要 |
| 根本的には国が悪い | ・保育士の待遇は国によって定められている ・待遇改善が進まないことが問題 ・国が待遇を保障して初めて責任を問える |
| まとめ | ・集団離職は最終手段だがブラック保育園には有効 ・背景には低賃金や過酷な労働環境がある ・保育園だけでなく国にも責任がある ・法に則った手続きが重要 |
| よくある質問(FAQ) | ・集団離職は無責任とは言えない ・低賃金や過酷な労働環境が背景にある ・保育士の権利を守るための行動 ・経営者は働きやすい環境を整える責任がある ・国や自治体は待遇改善に取り組む必要あり |
- 集団離職は無責任?
- なんで集団離職が起きる?
保育士が一斉に退職を行う集団離職というのが相次いでいます。保育士の集団離職は決して無責任ではありません。
背景には、低賃金や過酷な労働環境といった構造的な問題が存在します。
この記事では、現役保育士の視点から、集団離職の事例や責任の所在を考察し、ブラック保育園への有効な対抗手段としての側面を解説します。
最後まで読むことで、保育士不足の根本原因や、保育園選びの重要性についても理解が深まるでしょう。

保育士の集団離職って、本当に無責任なの?

いいえ、保育士にも職業選択の自由があります。きちんとした手続きの上で退職するということは問題ないです
- 集団離職の事例と背景
- 保育士に責任はない理由
- ブラック保育園が生まれる原因
- 保護者が知っておくべきリスク
複数回の転職経験があります
その経験が参考になればと思います
保育士の一斉退職・離職の事例
ここで紹介しているのは比較的最近話題になったニュースだが、実際にはもっと多くの保育士の一斉退職が起きていると思われます。話題にならない程度の大小の一斉離職を含めたら、毎年のように似たようなことが各地で起きていると言えるかもしれません。
中央区の認可保育園の保育士の大量退職
中央区の認可保育園で18人のうち13人が順次退職するというニュースになっています。
退職の理由は、長時間労働などへの不満や給与の低下などです。
目黒区の認可保育園での大量退職
目黒区の認可保育園では5人中4人が退職するというニュースがありました。
同保育園では過去にも大量退職が起きていたようですが、退職理由はボーナス支給や夏休み取得などに運営会社との認識の違いがあったようです。
横浜市の認可保育所での大量退職
横浜市の認可保育園で保育士11人が一気に退職したというニュースです。
退職した11人のうち7人は別の新設した保育園で働いているということです。引き抜きではないか?などと問題になりました。
新設の保育園側は引き抜きということを否定して単に募集に対して応募して転職したと主張しています。
結果的に、大量退職があった保育園は保育士の必要人数を満たせなくなり、定員を縮小しての運営を余儀なくされています。
浜松市の認可保育園での集団離職
静岡県浜松市の認可保育園で、18人の職員がパワハラやセクハラなどを理由に一斉に退職届を出したというニュースです。
ニュースやSNSでもかなり話題になり、その後、経営者が入れ替わり運営を存続するという方向で調整されています。
経営者が入れ替わることで、退職の意思を示していた保育士の一部が退職を撤回しています。ただし、一部の保育士は体調を崩しており退職することが決定しています。
集団離職をする保育士は無責任ではない
私の考えとしては、集団離職をする保育士は無責任ではないと思います。
保育士はどこで働くのも自由
保育士に限らずですが、日本には「職業選択の自由」が憲法で定められています。自分の職業は自分の意思で決定することができるようになっています。
当然ですが、保育士は自分が働く場所は自分で決める自由があります。他人や第三者が退職する保育士に対して、「無責任だ」と言って職業選択の自由を侵害することはあってはならないことだと思います。
給与や人間関係に不満があればより良い保育園に転職するのは保育士でなくても当たり前のことです。それがどうしても受け入れられないのであれば、すべて公立保育園にするなどして、働く保育士もすべて公務員にして制約をつけるべきだと思います。
「引き抜き」を批判するのも間違い
転職エージェントなどの紹介会社によりよい待遇で引き抜きをされてしまうということを嘆く保育園の経営者がいます。
そもそも、保育士の転職は「潜在保育士の復帰」「新卒保育士の就職」を除いたらほぼすべてが「引き抜き」に該当します。
もともと別の保育園で働いていたのを辞めて新しい保育園で働くわけですから「引き抜き」が駄目となったら、保育士は転職できなくなってしまいます。
前述したとおり保育士はどこで働くのも自由です。「引き抜かれて」転職するのもその保育士の自由です。
引き抜きを防ぎたいのであれば、他の保育園より給料を上げたり、労働環境を改善したり、人間関係を良くすればよいです。それができないのであれば、引き抜かれて当然です。
保育園の経営者に責任がある
結論としては、集団離職は、集団離職を防げなかった保育園の経営者に問題があります。
給与に不満を持つ保育士が退職を申し出ているなら、給与を上げるのが有効です。転職先の保育園と同水準か、わずかに上回る程度で十分でしょう。決して法外な金額を提示する必要はありません。
人間関係に不満を持って辞めていくのであれば、改善すれば良いでしょう。経営者としての腕の見せどころだと思います。保育士に限らずですが、人間関係が良ければ転職を踏みとどまる人も多いです。
それができないのであれば新たな犠牲者を出さないためにも閉園したほうがましかもしれません。
認可している市区町村にも責任がある
もちろんそのような保育園を認可している自治体にも責任があります。
浜松市の認可保育園の集団離職では、パワハラなどが起きていたことについて、保育士から弁護士や労働基準監督署などに相談があったようです。当然、自治体も把握していたと思われます。
それでも改善が見られなかったため、一斉退職に至りました。「認可」保育園であるため、自治体の認可がなければ運営はできません。
自治体が、保育定員を確保するため(待機児童を増やさないため)のしわ寄せが最終的に保育士に集まっています。待機児童を減らすために急ピッチで認可を勧めていったというのも原因の一端になっていると思います。
パワハラが起きる保育園を自治体が「認可」してしまっていて改善もできていなかったということにも責任はあると思います。
わざわざ一斉に辞める必要は無いのでは?
これに関してもそこまで不満が噴出する状態を放置していた保育園の経営者に責任があります。それまでにも幾度となく何人も保育士が辞めていったと思います。今まで起きていることは無視して最後の部分だけを切り取れば確かに一斉退職になります。
過去に様々な保育士がいて、最後の最後になって一斉に辞めるということになったはずです。それまでになんの対処も出来ずに一斉に辞めたとたん「引き抜きだ」「無責任だ」と騒ぎ出す経営者はとても滑稽だと思います。
一例ですが、福岡市の認可保育園で、保育士や園児に対して副園長が暴力などをふるい逮捕されたというニュースがありました。
この園では、約9年間に被害女性を含む60人以上の保育士が退職しているということが報道されています。9年間でそれだけの人が辞めていてもなにも変わらず逮捕されるに至ったわけです。
むしろ、早い段階で保育士が一斉退職をしていてその保育園のことが話題になっていれば、園児や保育士への暴力ももっと前に防げていたかもしれません。これはあくまでも一例ですが、このようなこともあるのが事実です。
保育士としても、保育園側が今まで最低限の対応をとってきたのであれば、一斉退職には至らないはずです。
子どもを預ける保護者は、保育士を責めるのではなく、保育園、そして認可している自治体や国に対して働きかけることが問題解決につながります。
集団離職はブラック保育園に対してかなり有効
集団離職はブラック保育園に対してはかなり有効であると言えます。
急に一人や二人辞めるくらいでは、少々追加でコストは掛かりますが派遣会社を利用するなどして穴埋めをすることができますが、大半の保育士が辞めるとなると流石にそうは行かないです。その上、ニュースなどで報道されてしまえばダメージは相当なものになります。
園児の人数に対して、必要な保育士の人数は決まっているため、保育士が足りないと運営を継続することができなくなります。
横浜市の認可保育園の例でも縮小という形で運営をしています。
3-5歳児のクラスを廃止して、運営を縮小して営業を続けています。37人の園児たちは市内の別の保育園への転園を余儀なくされたようです。
しかしながら、実際には認可保育園は潰れるというところまでは行かないです。このように、認可保育園は行政から一度認可されれば、入園の可否を行政が選別している以上、ブラックであろうと保育士が足りなかろうとも簡単には閉園とは行かないです。
ですが、相当なダメージがあることは間違いないです。実際に園の名称も報道されるので、いざ保育士を探そうと思ってもそう簡単には見つからないと思います。
逆にこれから、就職や転職を考える保育士の方も、現状の給料待遇の情報だけではなく、その園の過去の情報などもしっかり調査したほうが良いかもしれません。
預ける保護者もリスクを留意しておくべき
ブラック保育園に子どもを預ける場合、保護者もリスクを認識しておく必要があります。保護者の間で評判が良い保育園でも、保育士が過酷な労働環境で働いている場合、同様の問題が起こる可能性があります。
むしろ、そのような保育園ほど保護者の評判が良い場合があります。
自分の子どもを預けた保育園で一斉退職があって転園を余儀なくされるということは今後も発生していくと思います。
もちろん、保育園に入れれば御の字という状況なのでそうはいかないかもしれませんが、預ける保育園をしっかりと選ぶことが大事です。
一番の被害者は大人の事情に振り回されてしまうこども達なので、しっかりと行政や国にはたらきかけていくことで保育業界を改善していく必要があると思います。
根本的には国が悪い
保育士の大量離職などの問題は、根本的には国の責任であると言えます。保育士の待遇は国によって定められているためです。
保育士の待遇が低い状況が続いているにもかかわらず、対策が進んでいない点が問題です。待遇が改善されない限り、同様の問題が繰り返されるでしょう。
一定水準の待遇を保障して初めて、一斉に離職する保育士に対して関係者や第三者が責任を問うことができるようになるでしょう。
まとめ
保育士の集団離職は、無責任ではありません。
背景には低賃金や過酷な労働環境があり、ブラック保育園への有効な対抗手段となり得ます。
- 集団離職の背景と事例
- 保育士に責任がない理由
- ブラック保育園が生まれる原因

保育士の集団離職は、保育園だけでなく国にも責任がある
保育士の集団離職は最終手段ではありますが、ブラック保育園には有効な手段となり得ます。
退職の際は、法に則った手続きを行うようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士が集団離職するのは無責任ですか?
- A
いいえ、保育士が集団離職するのは必ずしも無責任とは言えません。
背景には、低賃金や過酷な労働環境といった問題があり、自身の権利を守るための行動として理解できます。
- Q集団離職はどのような事例がありますか?
- A
近年、中央区、目黒区、横浜市、浜松市などの認可保育園で保育士の大量退職が発生しています。
これらの事例では、長時間労働、給与の低下、運営会社との認識のずれ、パワハラなどが原因として挙げられています。
- Qなぜ保育園で集団離職が起こるのですか?
- A
集団離職の背景には、保育士の慢性的な人手不足、低賃金、過酷な労働環境、人間関係の悪化など、複数の要因が複合的に絡み合っています。
これらの問題が改善されない場合、保育士は職場に見切りをつけ、集団離職という形で表面化することがあります。
- Q保育園の経営者は集団離職に対してどのような責任がありますか?
- A
保育園の経営者は、保育士が働きやすい環境を整える責任があります。
具体的には、適正な給与水準の維持、労働時間の管理、人間関係の改善、ハラスメント対策などが求められます。
これらの対策を怠り集団離職を招いた場合、経営者としての責任を問われる可能性があります。
- Qブラック保育園に預ける保護者はどのようなリスクがありますか?
- A
ブラック保育園では、保育士の負担が大きいため、質の高い保育が提供されない可能性があります。
また、保育士の入れ替わりが激しく、子どもの成長に悪影響を及ぼすことも考えられます。
最悪の場合、保育園が閉鎖され、転園を余儀なくされることもあります。
- Q集団離職を防ぐために、国や自治体は何をすべきですか?
- A
国や自治体は、保育士の待遇改善と労働環境の整備に積極的に取り組む必要があります。
具体的には、給与水準の引き上げ、保育士の配置基準の見直し、保育士向けの相談窓口の設置などが考えられます。
また、保育園への監査を強化し、問題のある保育園に対して改善指導を行うことが重要です。