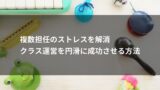| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育観とは?そもそも何なのか? | ・保育士が子どもと接する上で大切にする価値観や考え方 ・叱り方など具体的な場面での判断に現れる個人の信念 ・厚生労働省の保育所保育指針でも、個々の保育観を共有し保育に取り組むことを推奨 ・明確な正解がなく、保育士ごとに異なる曖昧な概念 |
| 保育観が違う、あわないは保育士あるある | ・保育観に正解がないため、保育士それぞれの経験から違いが生じるのは自然なこと ・他の保育士の対応を見て「自分ならこうする」と感じることや、先輩からの指導で違いに気づく場面が多い ・複数の保育士で担任をする場合、ペアの保育観のずれが明確になる |
| 保育観は周りの保育士と合わせるべきかどうか | ・単に周囲に合わせるだけでは、誤った保育や自身の成長につながらない可能性 ・行動の背景にある理由を理解し、率直な話し合いを通じて自身の考えや相手の考えを深める姿勢が重要 ・保育所保育指針を改めて読み、子どもの最善の利益につながる行動かを確認 ・保育園全体で個々の保育観を共有し、協力して保育に取り組むことが求められる |
| 働く上では保育園の理念との合致も重要 | ・自身の保育観が保育園の理念や方針と一致していると、長く快適に働ける要因となる ・理念とのずれが大きい場合、仕事が精神的な負担になり継続が難しくなる可能性がある ・就職や転職の際には、保育園の見学などを通じて、その理念や方針を事前に確認することが大切 |
| どうしても合わない場合は転職も視野に | ・保育園の理念、方針、または周囲の保育士の保育観がどうしても受け入れられない場合、転職も一つの解決策 ・転職先選びでは、再度のミスマッチを防ぐため、園の理念や雰囲気を事前に詳しく調査することが不可欠 ・保育士専門の転職サイトを利用すると、見学手配や詳細な情報収集がしやすく、納得のいく転職につながる |
| まとめ | ・保育観は保育士それぞれに違いがあり、これは自然なこと ・同僚との違いを感じた際は、保育指針に基づき子どもの最善の利益を追求する重要性 ・保育園全体で保育観を共有し、チームとして協力する姿勢が求められる ・自分の保育観と園の理念が一致しない場合は、転職も選択肢の一つ ・保育観は常に変化し成長するもの、学び続ける姿勢が大切 |
| よくある質問(FAQ) | ・同僚とのコミュニケーション: 相手の考えの背景を質問で理解し、オープンな話し合いで相互理解を深めること ・園の理念との相違: 理念再確認、主任や園長に相談、改善なければ転職も検討 ・子どもへの対応一貫性: 具体事例でケース会議実施、子どもの利益を目標に方針決定 ・ベテランとの意見交換: 経験を尊重しつつ意図を質問、提案として自身の考えを伝える。必要なら第三者に相談 ・保育観の変化: 経験や学びを通じて常に変化し成長。子どもの利益を大切にしつつ、柔軟に更新する姿勢 |
- 先輩から注意された
- ペアの保育士と考え方があわない
- 保育観の違いからギクシャクした
保育士として働く中で、同僚と保育観が違うと感じることはありませんか? これは多くの保育士が経験する、非常に重要な悩みです。
この記事では、「保育観」という言葉の意味を深く掘り下げ、保育士同士で意見が合わない時の具体的な対処法について、私の経験も踏まえて詳しく解説します。

同僚と保育観が違う時、どのように向き合えば良いか悩んでいます。

あなたの保育観を大切にしながら、より良い協力関係を築くヒントが見つかります。
細かいことも含めれば、こんなことは日常茶飯事かもしれません。これらは保育観だけの問題でないことも多いです。保育観があうあわないと言われますが、そもそも「保育観」とはなんなのでしょうか。そういう観点も踏まえて、保育士同士で保育観が違う場合の対処法について解説します。
私自身もまだまだ未熟ではありますが、実際に保育士として働いているなかで、感じていることや実践していることを紹介します。
その経験が参考になればと思います
保育観とは?そもそも何なのか?
保育観とは、保育における価値観のことで、保育士として仕事をしていくなかで、子どもと接していく中での大切にしているポイントのことです。
例えば、ある場面で、園児に対して叱るべきなのか、叱らないべきなのか、叱るのであるならどう叱るのかなど、もちろん場面や状況によっても異なると思います。
厚生労働省が定めている保育所保育指針にも「保育観」という言葉は書かれています。指針では、全ての保育所に共通する保育の目標を定めています。
「保育の目標」を、
一人一人の保育士等が自分自身の保育観、子ども観と照らし合わせながら深く理解するとともに、保育所全体で共有しながら、保育に取り組んでいくことが求められています。
というように書かれています。ちなみに保育の目標に関しては以下のように書かれています。
ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わければならない。
(ア) 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。
(イ) 健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。
(ウ) 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。
(エ) 生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。
(オ) 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと。
(カ) 様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと。
保育士としてこういうような保育観を持つべきかというものが、決められていたり、定められているわけではもちろんありません。なので、保育観というのはものすごく曖昧なもので、保育士個人個人によって異なるものになります。
このように、保育士は自分自身の「保育観」と照らし合わせながら、保育の目標を理解し、保育に取り組んでいくことが求められています。
※参照「子ども家庭庁 保育所保育指針解説」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/eb316dce-fa78-48b4-90cc-da85228387c2/f4758db1/20231013-policies-hoiku-shishin-h30-bunkatsu-1_24.pdf
保育観が違う、あわないは保育士あるある
保育観は正解が誰かによって定義されているものではないため、保育士ひとりひとりによって違いがあるものです。
保育士はそれぞれが人生で様々な経験をしてきていますし、保育においてもそれぞれ異なった経験をしてきているので、違いが生じるのは当たり前と言えるのかもしれません。
他の同僚の保育士の保育を見ていて、自分だったらこうするのに、なぜそうしたんだろうと思うことは保育士ならよくあると思います。
また、先輩の保育士などから「こんな時はこうすべきだ」と言われることもあると思います。それが個人の保育観の違いによるものであることも多いです。
特に保育園は同じクラスに複数の保育士が入って担任となることが多いので、ペア同士での保育観の違いなどがわかりやすく見えてしまいます。
保育観は周りの保育士と合わせるべきかどうか
保育観に違いがあることがわかった際に、周りの保育士と合わせるべきかどうかは、保育士の悩みのタネでもあると思います。
一概に先輩の保育士や担任の保育士に合わせればそれで良いということではない場合もあります。保育士としての経験が長いからと言ってその保育士の保育観が優れているとは限らないためです。
ただ先輩や周囲に合わせるというだけだと間違った保育観、及び、保育スキルが身についてしまうかもしれません。
例えば、先輩が子どもに対して暴力を振るうというような指導をしていた場合はどうでしょうか。
もちろん暴力は犯罪なので、保育観云々の問題ではそもそもないです。これはかなり、極端な例ですが、ただ先輩や周囲の保育士に合わせるだけだと、間違ったことをしてしまうかもしれません。
このように、周りの保育士と行動を合わせるだけでは、真の意味での子どものための行動の理解につながらないこともあります。
なんの理由があってそのような行動をとったのかということを理解することが、保育士としての成長にも大切だと思います。
もし、一緒に組んでいるペアの保育士と保育観が合わないということがあれば、そのことを素直に本人に聞いてみると良いかもしれません。
「なぜそうしたのか」「自分だったらこうしてた」などを正直に話したり、聞いてみることで相手や自分の考え方も変わるかもしれません。
自分の根底にある信念のような保育観は変える必要はないかもしれませんが、保育士ひとりひとりの保育観は常に変化していくものだと思うので、常に新たに学んでいく姿勢が大切だと思います。
保育所保育指針を読もう
保育観の違いから生まれる、それぞれの保育士の行動などに関して、それでも困ったり、納得がいかなかったら保育所保育指針などを改めて読んでみるのが良いと思います。
冒頭にも書いたように、保育所保育指針は全ての保育所に共通する保育の目標を定めています。保育観に正解不正解はないと説明しましたが、保育の目標は全ての保育所に共通しています。
その行動が「保育の目標」の達成に近づいているかどうか、今一度、確認してみると良いかもしれません。自分の行動や他の保育士の行動が、子どものためになっているかどうかということを改めて理解し直してみると良いかもしれません。
保育観は保育園内で共有されるべき
先程も書きましたが、保育所保育指針には以下のように書かれています。
一人一人の保育士等が自分自身の保育観、子ども観と照らし合わせながら深く理解するとともに、保育所全体で共有しながら、保育に取り組んでいくことが求められています。
一人ひとりの保育観を保育所全体で共有しながら、保育に取り組むことが求められていると記載されています。保育観は個人個人で異なっていたとしても、それを保育園内で共有して保育に取り組んでいくことが保育園には求められています。
このことは、保育士には間違いなく求められていることなので、何か保育士間で意見の相違が出てきたときも、保育観が合わないということで片付けずに、保育園内でどうしていくべきなのかを共有して保育を行っていく必要があります。
働く上では保育園の理念との合致も重要
保育園で働く上では、自分の保育観が保育園の理念や方針と一致しているということも重要です。 保育園の保育理念や方針については以下の記事でも解説しています。
自分の保育観が保育園の理念や方針とずれていると、場合によってはその保育園での仕事そのものが耐え難いものになってしまう可能性もあります。
ブラック保育園、ホワイト保育園云々の前に、そのことが苦痛になってしまうと、保育士として長く続かないということになってしまいます。
ただ、転職や就職をする上では、そこで働いているそれぞれの保育士の保育観などを事前に計り知ることは難しいです。このような細かい保育観については、保育園の見学などを通して、少しでも事前に理解できると良いと思います。
もちろん実際に働き始めないとわからない部分が大半を占めているため、まずは大枠である保育園の理念や方針と自分の考えが一致しているかどうかを知ることが大切です。
どうしても合わない場合は転職も視野に
どうしても、保育園の理念や方針、周囲の保育士の保育観が自分と違い「納得できない」「容認できない」「理解できない」という場合は、転職を検討するのも良いかもしれません。
ただ、転職したからと言って改善できるとは限らないため、前述したように、保育園の理念や方針と自分の考えが合致しているかどうか、しっかり調査して転職をすべきです。
このような場合は、保育士向けの転職サイトを利用しての転職がおすすめです。
転職サイトを利用すれば、しっかりと事前に保育園の見学を申し込むことができます。保育園の普段の様子や保育方針なども担当者から聞くことができるので、より理解が深まった状態で面接に臨むことができます。
- マイナビ保育士
 |全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです! - ジョブメドレー保育士
 | 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)

※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。
まとめ
この記事では、保育士の保育観が一人ひとり異なるのは自然なことであるとお伝えしてきました。
そして、同僚との違いを感じた際の具体的な対処法についても詳しく解説しています。
保育士の保育観について、大切な点をまとめます。
あなたの根底にある保育への信念は大切にしながらも、保育観は常に変化していくものです。
この機会に改めて自身の保育観を見つめ直し、学び続ける姿勢を持ってより良い保育の実現を目指しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育観が違う同僚とのコミュニケーションで最も大切なことは何ですか?
- A
同僚と保育観が違うと感じる時、まず大切なのは相手の考えの「背景」を理解しようとすることです。
単に意見が違うと片付けるのではなく、「なぜそう考えたのか」「どのような子どもへの想いがあるのか」を質問を通じて聞き出すことから始めましょう。
オープンな話し合いの場を設け、建設的な意見交換を心がけることで、相互理解が深まります。
報連相も徹底し、決定事項やその後の対応をチーム内で共有する意識を持つと、よりスムーズな連携ができます。
- Q自分の保育観と園の理念が異なる場合、どのように対応すべきでしょうか?
- A
ご自身の保育観と園の理念にずれを感じることは、プロの保育士として深く考えるきっかけになります。
まず、園の保育理念を改めて確認し、ご自身の保育観と共通する点や異なる点を具体的に整理しましょう。
もし解決が難しいと感じる場合は、主任や園長に相談する機会を設けることをおすすめします。
状況が改善されない、またはご自身の保育士としての価値観が大きく阻害されると感じるようでしたら、ご自身の保育観と合致する園を探すことも選択肢の一つです。
- Q保育観の違いが原因で、子どもたちへの対応に一貫性がなくなるのを防ぐには?
- A
子どもたちへの一貫性のある対応は、彼らの情緒の安定や成長にとって非常に重要です。
保育観の相違から対応にブレが生じる場合は、具体的な事例を挙げて「ケース会議」を定期的に行うことが有効です。
この場で、「子どもの最善の利益」という共通の目標に立ち返り、全員で話し合い、具体的な対応方針を決定します。
役割分担を明確にし、共通の目標に向かってチームとして協力する体制を築くことが、保育の質の向上につながります。
- Qベテランの保育士と保育観が合わない時、どのように自分の意見を伝えたら良いでしょうか?
- A
ベテランの先生と保育観が違うと感じることはよくあります。
大切なのは、相手の経験や知識を尊重しつつ、ご自身の意見も建設的に伝えることです。
まずは「なぜそうされたのですか」と質問し、相手の意図や考えの背景を理解することから始めましょう。
その上で、「私はこのように考えてみたのですが、どうでしょうか」というように、提案としてご自身の考えを伝えてみてください。
どうしても解決が難しい場合は、主任や園長などの第三者に相談し、間に入ってもらうことも一つの方法です。
- Q保育観は一度決まったら変えるべきではないのでしょうか?
- A
保育観は、保育士としての経験や学びを通じて、常に変化し、成長していくものだと私は考えています。
根底にある「子どもの最善の利益を願う気持ち」は大切にしつつも、新しい知識や多様な価値観に触れることで、ご自身の保育観をより豊かにしていくことができます。
他の保育士の意見を聞いたり、研修に参加したりする中で、新たな気づきを得て、ご自身の保育観を柔軟に更新していく姿勢が、プロの保育士として大切になります。
- Q保育観の相違が職場の人間関係のストレスに繋がる場合、どのように乗り越えれば良いですか?
- A
保育観の相違が原因で人間関係にストレスを感じる場合、まずは感情的にならず、プロ意識を持って客観的に状況を見るように心がけましょう。
自分の意見に固執するのではなく、相手の意見にも耳を傾け、共通の目標である「子どもの健全な成長」のためにどうすればよいかを考えます。
必要であれば、主任や園長などの上位者に相談し、第三者からのアドバイスや調整を求めることも有効です。
ご自身の心身の健康も大切にしながら、ストレスと向き合う方法を見つけていくことが重要です。