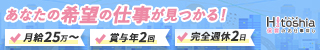| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育士が実家暮らしが良いか悪いかは個人の状況次第 | ・保育士の実家暮らしは金銭面で非常に有利 ・良いか悪いかは個人の状況や価値観次第 ・他人目線の「自立」「恥ずかしい」で判断せず、自身の幸せを重視すべき |
| 親から自立しろ、一人暮らししろと言われてしまっている | ・親が一人暮らしを勧める理由を理解し、要望を満たす努力が重要 ・親の干渉を受け入れるか、一人暮らしを検討するかの判断が必要 ・家事や金銭面で親の負担を軽減する行動が有効 |
| 実家ぐらしのメリットとデメリットを整理 | メリット ・家事や金銭の負担が少ない ・孤独を感じにくく、家族の協力が得やすい デメリット ・同居人から干渉を受けやすい ・友人や恋人を招きにくい ・家族との喧嘩が増える可能性 |
| 保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしをするかを選ぶポイント。 | ・勤務先との距離や通勤時間 ・家事や食事の準備、栄養面への影響 ・実家の住み心地や家族関係 ・目標貯金額と金銭的な余裕 ・保育士宿舎借り上げ制度の利用可否 |
| 保育士の実家暮らしによくある疑問など | 結婚との関係 ・貯金や自己投資でお金を有効活用できるため、実家暮らしが結婚を遠ざけるとは限らない 一人暮らしと経済面 ・首都圏での宿舎借り上げ制度活用が経済的な負担を減らす方法 自立の問題 ・家事や生活は実家でも経験でき、自立は個人の行動次第である |
| まとめ:保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしするかは状況次第! | ・実家暮らしの可否は個人の状況や価値観で異なる ・特に経済的メリットが大きい選択肢 ・判断ポイント:通勤、家事・食事、実家の居心地、貯金、宿舎借り上げ制度 ・自己の状況を考慮し、より良い環境を選ぶことが重要 |
| よくある質問(FAQ) | プライベート時間 ・家族とルールを決め、家以外でリラックスする工夫が必要 貯金目標 ・手取りの1〜2割が目安、一人暮らしなら費用を具体的に計算し設定 一人暮らし準備 ・費用シミュレーション、家事練習、家具家電の準備が重要 ストレス軽減 ・オンオフの切り替え、友人との交流、趣味を持つことが有効 経済負担軽減(宿舎以外) ・家計簿、自炊、格安スマホ、節電節水で負担を減らす 最も重視すべき点 ・ライフスタイルと将来計画に合わせた総合的な判断 |
- 保育士の実家暮らしは良いの?悪いの?
- 早く自立した方が良い?
- 親から出ていけと言われている。。。
保育士として毎日頑張る中で、住まいの選択は仕事のモチベーションやプライベートに大きく影響します。
実家暮らしを続けるべきか、それとも一人暮らしに踏み出すべきか悩む方は多いですが、この記事では保育士にとってより良い環境を見つけるためのヒントを具体的に解説します。

疲れて実家に帰っても、親に気を使ってしまう。このまま実家暮らしで貯金はできるのかな、一人暮らしは可能なの?

保育士としての生活をより豊かにするためには、ご自身の状況と将来を見据えた住まいの選択がとても大切です。
保育士に限ったことではないですが、
- 自立したほうが良い
- ○歳で実家は恥ずかしい
というような考えをもっている人も少なくないです。でも保育士の給料事情を考えると、なかなか難しいという人もいると思います。今回は、保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしをするかを選ぶポイントについて解説します。
実家ぐらし、一人暮らしの経験があります
その経験が参考になればと思います
保育士が実家暮らしが良いか悪いかは個人の状況次第
初めに結論になりますが、個人的には保育士が実家暮らしをするということは金銭面を考えるととてもおすすめです。ただし、実家暮らしが良いか悪いかは、完全に個人の状況と価値観によって異なるものになります。
- 自立したほうが良い
- ○歳で実家は恥ずかしい
という人もいますが、そもそも何をもって自立というのでしょうか。実家から出れば自動的に自立になるのでしょうか。このような、他人目線の意見で、保育士が実家暮らしをすべきか、実家を出るべきかということを決めることは自分の幸せには直結しません。
もちろん「恥ずかしい」と思われたくないと思うことも間違っていないですし、自分の正しい気持ちだと思います。ですが、保育士が実家暮らしをやめて一人暮らしをするということは、追加のコストがかなりかかる行動となります。それを他人目線の考えで決めてしまうのは、安易な選択だと個人的に思います。
親から自立しろ、一人暮らししろと言われてしまっている
なかには自分自身は実家暮らしを続けたいけれど、親から自立しろ、一人暮らししろと言われてしまっているという保育士の方もいらっしゃると思います。
親がなぜそのように言ってきているのかということを理解する必要があります。
それぞれの親がそう思う理由は様々だと思いますが、
例えば、自立しろ、一人暮らししろという言葉の背景には以下のような心理がある場合があります。
- 家事や料理ができるようになって欲しい
- 結婚して欲しい
- 居座られるとお金がかかる
- 家事が大変になる
もし、まだ実家暮らしをしたいという保育士の方は、これらの親の要望をある程度満たす必要があると思います。
例えば、家事や料理ができるようになって欲しいという場合は、できる限り、実家にいる間も家事や料理をするということです。金銭的な面で出ていってほしいという場合は、実家にいれるお金を増やすことなどが考えられます。結婚してほしいという親に対しては、そのような話も素振りだけでも少しはしなければいけません。
そして、実家にいる以上ある程度、親から生活に関して干渉されるということは受け入れる必要があります。一緒に住む以上、このようなデメリットもある程度は受け入れる姿勢が必要です。
逆に、そのデメリットがあまりにも大きいのであれば、実家を出るということの検討が必要になるということになります。
実家ぐらしのメリットとデメリットを整理
保育士が実家暮らしを続けるべきかそうでないかを検討するために、まずは実家暮らしのメリットとデメリットを整理します。もちろん、各家庭によって状況は異なると思うので、自分がもし一人暮らしを始めたらどのようなメリットを失い、デメリットを減らすことができるのかということを把握することが大切です。
家事の負担が減る
実家暮らしで親に家事をしてもらえるという場合は、家事の負担は大幅に減ります。毎日の洗濯、料理、掃除、日用品の買い出しや買い物など、一人暮らしを始めたらやらなければならないことは多くありますが、その一部でもやってもらえれば、負担は大きく減ることになります。減った分は自分の時間に当てることができます。
金銭的な負担が減る
実家暮らしをする上で、毎月お金を入れているという人も多いとは思いますが、ほとんどの場合、一人暮らしをしたときよりも少ない金額になると思います。特に、都市部になると家賃も高額になるため、実家暮らしの金銭的なメリットは非常に大きいです。
また、日常生活という観点においても、基本的に、大人数で暮らしたほうが、金銭的な費用対効果は良くなります。食材も日用品も1人分を買うよりも大人数分を買ったほうが割安になるためです。
孤独を感じにくい
実家暮らしは常に家に誰かがいるので、孤独を感じにくいというメリットがあります。特に、寂しがり屋な性格の人は一人暮らしに耐えられないという場合もあるでしょう。もちろん、一人暮らしをしたら、友人や恋人などを家に招くこともできるので、必ずしも孤独ばかりというわけではありません。
協力を得やすい
実家暮らしは、困った時に何かと家族からの協力を得やすいです。あれをやっておいてほしい、これをやっておいてほしい、といった形で何かをお願いすることができます。もちろん、家族の誰かが困ったときは自分がすぐに助ける側にまわることができます。遠方で一人暮らしをしている場合は、万一の場合は、新幹線や飛行機などで駆けつけなくてはいけなくなり、それはそれで負担が大きいです。
同居人から干渉を受けやすい
実家暮らしの大きなデメリットになるのが、同居人から干渉だと思います。親というものは、うるさい生き物で、自分の生活についてなにかと口出しをしてくる場合が多いでしょう。それが精神的なストレスになってしまうという場合もあります。最初の頃は良くても、だんだんと実家ぐらしが長くなるにつれて、干渉の度合いが変わってくるという点にも注意が必要です。
友人や恋人を招きにくい
実家には、友人や恋人は招きにくいという方が多いと思います。常に家族の目があるので、人を呼ぶということに関して、できることは限られてくるでしょう。
喧嘩もしやすい
実家暮らしで同居人との距離が近ければそれだけ喧嘩をしてしまうことも多くなるでしょう。離れていれば、我慢できることでも一緒に暮らしていると我慢できないことも多いです。
保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしをするかを選ぶポイント。
個人的には保育士は実家暮らしはとてもおすすめと書きましたが、これも 個人の状況次第です 。それぞれの状況は異なるので、保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしをするかを選択する上でのポイントを解説します。
勤務する保育園から近いか遠いか
実家暮らしをするかどうかで一つの大切なポイントは、勤務する保育園から近いか遠いかということだと思います。保育士は、通勤は平日ほぼ毎日することになるので、通勤にかかる時間が、日々の生活の質に大きく関わってきます。
例えば、通勤時間が片道1時間と仮定すると、往復で2時間になります。これが一月だと勤務日数を考えると約40時間も通勤に費やすことになります。この時間を減らすことができれば、普段の自由に使える時間を増やすことができます。
逆に言うと、実家から近い保育園の求人を探すこともできるので、実家から勤務先が遠い = すぐ引っ越す と考えなくても良いかもしれません。特に保育士の場合は日本全国どこでも保育園があるので、比較的仕事は探しやすいですしね。
家事や食事、食事の栄養面を考慮する
実家の場合は、家事などを両親がやってくれるということもあると思うので、その時間についても考慮すべきです。
仮に通勤時間が少なくなったとしても、その時間と同じくらいの時間を費やして家事をやらなくてはいけないという状況になってしまうと、どちらが良いかわからなくなってしまいます。
もちろん、家事が好きという人であれば問題はないです。逆に、通勤の時間が本などを読む時間に当てられて好きという人もいると思います。
また、食事の栄養面についても考えるべきです。一人暮らしをしたとして、保育園での仕事が忙しく、自炊をする時間がなくなってしまったとします。コンビニ弁当ばかりを買ってしまうということになると、
これは短期的な金額や時間というものさしでは、はかることができないことです。栄養が偏ってしまって、将来病気になってしまった場合にはさらに余計なコストがかかり、時間も失われることになります。
実家の居心地が良いか悪いか
実家の居心地が良いか悪いかということも重要な要素です。これは自分の部屋があるか、家具や家電などの設備的な要素はもちろん、両親などの同居者との関係性についても大切な部分です。
例えば、両親が「早く実家から出ろ」というスタンスの場合は、実家に住んでいること自体が居心地が悪くなってしまいます。生活の半分くらいの時間を過ごす居住地での居心地が悪い状況下が続くということは、精神衛生上良くないです。
逆に、なんでも両親に相談できて、いつも味方になってくれるという場合は、一緒に住んでいたほうが心強いですよね。
どれくらい貯金をしたいかどうか
そして、最後に大切な要素は、どれくらい貯金をしたいかどうかという点です。つまり、金銭的な問題です。
家賃にかかっている費用だけではなく、光熱費や食事代、細かい日用品や消耗品の費用も考えると、実家暮らしのほうが費用対効果は良いのは明らかです。仮に、実家にいくらかお金を入れているとしても、なかなか埋まることがない差であると思います。
一人暮らしをする場合は、家賃に加えて少なくとも8万円から10万円程度の費用がかかります。家賃5万円とすると、月13万円から15万円程度の費用が必要です。仮に、一人暮らしの費用を家賃含め月10万円に抑えられた場合、実家暮らしをすれば年120万円の貯金ができる計算になります。
貯金はしないという人でも、この金額を自分の趣味などに費やすことができるようになります。やはり金銭面が実家暮らしの最大のメリットなので、実家暮らしをするか実家を出るかを迷っている方はよく考慮すべき点になります。
保育士宿舎借り上げ制度が利用できるかどうか
保育士が賃貸を借りて一人暮らしをする場合に利用できる可能性があるのが、国の事業である保育士宿舎借り上げ制度です。保育士宿舎借り上げ制度は、保育園で働く保育士向けに月額8万円程度の賃貸に、自己負担がほとんどなく住むことができる制度になります。保育士宿舎借り上げ制度は、市区町村などの自治体によって実施有無が異なります。 保育士宿舎借り上げ制度を実施している市区町村内、かつ、利用できる保育園に就業する必要があります。
保育士宿舎借り上げ制度の概要については以下の記事でも解説していますので参考にしてみてください.
これが利用できれば一人暮らしの金銭面での負担をかなり抑えることができます。保育士宿舎借り上げ制度を利用した場合の保育士の負担額で多いのは月額1万円程度です。
既に就業中の方の場合は、保育園に利用ができないか聞いてみると良いです。これから転職などを機に利用を検討したいという方は、保育士向けの転職エージェントに対応している保育園の求人を確認するのがおすすめです。
保育士の実家暮らしによくある疑問など
ここからは保育士の実家暮らしによくある疑問などに回答します。
結婚が遠ざかってしまう?
実家暮らしをしていると結婚が遠ざかるのでは?と考える人も多いようです。ただ、個人的にはそうは思いません。
料理や家事は実家でもすることが可能ですし、貯金がある人のほうが結婚もしやすいと思います。貯金をしないとしてもお金をその分自分磨きなどに利用することもできます。
誰かと出会ったり、デートをしたりするのにもお金はかかるので、実家暮らしでお金を貯めておくほうがかえって良いかもしれません。
ひとり暮らしをしたいけどお金がない
保育士の方に多いのが、やはりひとり暮らしをしたいけどお金がないという人だと思います。たしかに、保育士の月給では賃貸を借りて生活するとかなり苦しい生活を求められるでしょう。
おすすめは、東京などの首都圏に引っ越して、保育士宿舎借り上げ制度を利用して一人暮らしをすることです。
東京都などは保育士の給与も全国平均と比較して高いですし、保育士宿舎借り上げ制度が利用できれば、賃貸への自己負担がほとんどない状態で一人暮らしの生活することが可能です。
実家暮らしだと自立できないのではないか?
実家暮らしだと自立できないのではないか?という考えを持っている方や、周囲にそのように言われているという方もいると思います。
個人的には、一人暮らしでしか経験できないことの多くは実家暮らしでも経験ができると私は思っています。
掃除、洗濯、料理などの家事は、実家でも自分がやろうと思えばできると思います。逆に一人暮らしでも掃除や洗濯、料理などをほとんどせずに生活することもできなくはないです。
何をもって自立とするかにもよりますが、結局は本人の気持ちと行動次第なので、自立のためだけに一人暮らしをするというのは個人的にはおすすめできません。
まとめ:保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしするかは状況次第!
保育士の実家暮らしが良いか悪いかは、個人の状況や価値観によって大きく変わるものと理解できます。
特に、経済的なメリットは実家暮らしの大きな魅力です。
保育士が実家暮らしをするか、実家を出て一人暮らしをするかは状況次第です。他人からこう思われたくないから一人暮らしをするというのは安易な選択です。
保育士が実家暮らしをするか実家を出て一人暮らしをするかを選ぶポイントを挙げました。
- 勤務する保育園から近いか遠いか
- 家事や食事、食事の栄養面を考慮する
- 実家の居心地が良いか悪いか
- どれくらい貯金をしたいかどうか
- 保育士宿舎借り上げ制度が利用できるかどうか
通勤時間、食事面、栄養・健康面、家事の負担への考え方はもちろん、実家に住むということの精神面のプラスやマイナスもあります。
金銭面に関しては、やはり実家が有利ですが、保育士宿舎借り上げ制度を利用するという手段もあります。
自分自身の状況を踏まえて、保育士としてより良い環境で仕事ができると良いですね。
ご自身のライフスタイルや将来設計を見つめ直し、保育士としてより充実した働き方ができるよう、最適な住まいを選択してくださいね。
よくある質問(FAQ)
- Q実家暮らしをしながら、自分らしいプライベートな時間を確保するにはどうすれば良いですか?
- A
実家暮らしでも、自分だけの空間や時間を作る工夫ができます。
まず、家族と自分の部屋での過ごし方や外出のルールを話し合い、決めておくことが大切です。
また、家以外でリラックスできる場所を見つけたり、趣味に没頭する時間を意識的に設けるのも良いでしょう。
- Q保育士の給料で生活する上で、将来のためにどれくらいの貯金を目標にすべきですか?
- A
保育士の給料は高くない傾向にありますが、計画的に貯金することは可能です。
一般的には手取りの1割から2割を目標にすると良いでしょう。
一人暮らしを考えているなら、家賃や初期費用、毎月の生活費を計算し、具体的な貯蓄目標を設定すると安心です。
- Q実家暮らしから一人暮らしへ移行する際に、事前に準備しておくべきことは何ですか?
- A
一人暮らしにスムーズに移行するためには、事前の準備が非常に重要です。
家賃や光熱費、食費など、一人暮らしでかかる費用を具体的にシミュレーションしましょう。
家事の練習をしたり、必要な家具や家電の情報を集めたりするのも良い準備となります。
- Q実家暮らしを続ける中で、仕事のストレスを効果的に軽減する方法はありますか?
- A
仕事のストレス軽減には、オンオフの切り替えが大切です。
仕事で疲れたときは、自宅でゆっくり過ごすだけでなく、信頼できる友人や職場の同僚と話す時間を作るのも良いでしょう。
自分の好きなことに没頭できる趣味を持つことは、精神的な安定につながります。
- Q保育士が一人暮らしをする際、保育士宿舎借り上げ制度以外に経済的負担を減らす方法はありますか?
- A
保育士宿舎借り上げ制度が利用できない場合でも、経済的な負担を減らす方法はあります。
家計簿をつけて支出を見える化したり、自炊を増やして食費を抑えたり、格安スマートフォンへの切り替えも効果的です。
日々の生活で節電や節水を意識することも、積み重ねると大きな節約につながります。
- Q保育士が実家と一人暮らしを選ぶ際、最終的に「最も重視すべきポイント」は何ですか?
- A
最終的に最も重視すべきポイントは、ご自身のライフスタイルと将来の計画に合った選択ができるかどうかです。
経済的な余裕、プライベートの自由度、家族との関係性、そして仕事への影響など、複数の要素を総合的に考えて、後悔のない住まい方を選ぶことが大切です。