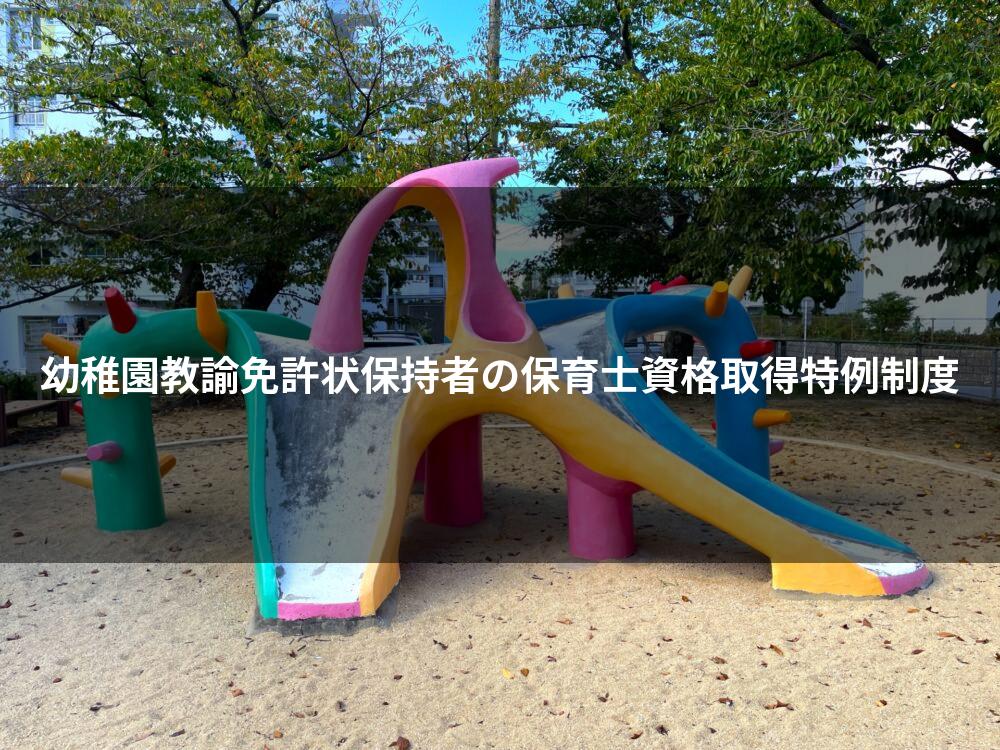- 保育士資格取得特例制度って何?
- 手順や必要な期間、お金について知りたい
認定こども園の普及により、幼稚園教諭と保育士の両方の資格が必要とされる場面が増えています。
この状況に対応するため、国では幼稚園教諭免許状をお持ちの方を対象とした特例制度を設けており、この記事では私が実際に制度を利用して保育士資格を取得した経験に基づき、その詳細な手順を解説します。

幼稚園教諭の私が、特例制度で保育士資格を取得するための具体的な手順や注意点を知りたい

私の実体験を踏まえて、特例制度の手順や知っておくべきポイントを詳しくお伝えします
この記事でわかること
- 幼稚園教諭免許状保持者向けの保育士資格取得特例制度の概要と対象
- 特例制度を利用した資格取得の具体的な流れと手順
- 資格取得にかかるおおよその期間と費用
- 実際に制度を利用した経験に基づく注意点やおすすめの養成施設
幼稚園教諭免許状保持者の保育士資格取得特例制度について知っていますか?こども家庭庁が令和11年度末まで特例として延長している措置になります。
認定こども園などでは幼稚園教諭と保育士資格が求められるので、特例制度の期間中に保育士資格の取得がおすすめです。
※参考「厚生労働省 幼稚園教諭免許・保育士資格の
更なる併有促進について」https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000989489.pdf
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoikushi-shikaku-tokurei
https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/tokurei.html
https://www.hoyokyo.or.jp/exam/Howto-payment.html
保育士資格取得特例制度を利用して保育士資格を取得した経験があります
制度については、厚生労働省の幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例の情報を参考にしています
その経験が参考になればと思います
実体験有!幼稚園教諭免許状保持者の保育士資格取得特例制度の手順解説!
時間が無い方のために先に簡単に特例制度の概要を紹介します。
幼稚園での勤務経験が3年以上かつ4,320時間以上ある、もしくはこれからそれを満たす予定がある 方が、
保育士養成施設等で特例教科目(4科目)8単位を履修修了 することで、
手順を略化して保育士資格を取得することができる制度です。こども家庭庁が令和11年度末まで特例として延長している措置になります。
詳細は以下からの内容を参考にしてみてください。
幼稚園教諭免許状保持者の保育士資格取得特例制度の概要
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例は厚生労働省が実施する保育士資格の取得に対する制度になります。
幼稚園教諭の免許状を持っていて幼稚園での実務経験がある方を対象に保育士試験の科目を免除にする制度になります。
特例制度は、平成27年度に始まり一旦は平成31年度末まで期間限定でしたが、さらに令和11年度末まで延長されています。
制度の背景としては、幼稚園が学校教育と保育を一体的に提供する認定こども園に円滑に移行を進めるための制度になっています。幼稚園・保育所で働く幼稚園教諭・保育士のうち25%程度は、いずれかの免許・資格で勤務しているようです。
幼稚園での勤務は幼稚園教諭免許のみ必要でしたが、認定こども園の職員は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」である必要があるためです。
保育教諭とは?
保育教諭は、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていて、認定こども園で働く職員のことを指します。
認定こども園の中でも「幼保連携型認定こども園」で働く職員は、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を保持している必要があります。
ただし、幼保連携型認定こども園の保育教諭等については、令和11年度末まで、いずれか一方の免許状・資格のみで保育教諭等となることができる経過措置が設けられています。
つまり、現在は片方の資格・免許しか持っていない場合でも幼保連携型認定こども園で就業することが可能ですが、いずれは両方の資格の保有が求められるということになります。
ちなみに、認定こども園には以下のような種類があり、そのそれぞれで、施設の内容が異なっています。
- 幼保連携型認定こども園
- 幼稚園型認定こども園
- 保育所型認定こども園
- 地域裁量型認定こども園
詳細は以下の記事でも紹介しています。
ちなみに、認定こども園は幼保連携型認定こども園が最も多く全体の約7割程度を占めています。
幼稚園教諭免許状保持者の保育士資格取得特例制度の対象者
- 幼稚園免許状を持っている
- 幼稚園の関連施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者
が対象になっています。3年以上かつ4,320時間以上というのはフルタイムで3年間働いていれば条件を満たしていることになると思います。
施設というのは以下のものが該当します。
(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
(2)認定こども園
(3)保育所
(4)小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設
(5)事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設
(6)公立の認可外保育施設
(7)へき地保育所
(8)幼稚園併設型認可外保育施設
(9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
過去に上記の施設での実務経験があればよいので、現時点で就業しているかどうかは関係がありません。また、異なる複数の施設で働いていた経験は合算することが可能です。
注意が必要な点としては、実務経験の証明は過去に働いていた施設の担当者にして貰う必要があります。
具体的には、就業していた証明書類を書いて貰う必要があります。園が廃園しているなどで証明が困難な場合は実務経験に含めることができません。
幼稚園などをあまり良い辞め方をしていない場合は、依頼するのが億劫になるかとも思いますが、ただ簡単な書類を書いてもらうだけなので遠慮は必要ないです。
私の場合は、書類を手紙で送付して記載を依頼しました。
保育士資格取得特例制度での資格取得方法
保育士資格取得特例制度での資格取得方法は大きく以下の流れになります。
- 養成施設で特例教科目(4科目)8単位を履修修了する
- (通常の)保育士試験への受験申請を行なう
- 合格証が届く
- 保育士登録を行なう
養成施設は大学や専門学校にあたり、それぞれ幼稚園教諭免許状保持者の保育士資格取得特例制度の授業を開講しています。
養成施設で特例教科目(4科目)8単位を履修すると証明書が貰えるため、それをもって通常の保育士試験に申し込みます。
通常の保育士試験の申込期間に申し込むことも可能ですが、幼稚園教諭免許状保持者の保育士資格取得特例制度を利用する方専用の申込み期間も用意されています。
提出した書類に不備がなければ全科目が免除されるので、試験を受けに行く必要はなく、自動的に合格となります。
最終的には合格証が自宅に届くので、それをもって保育士登録を行なうという流れになります。
資格取得にかかる期間は?
最終的に保育士登録を終え保育士証を得るのに 最短でも1年程度の時間がかかる ことになると思います。
私が利用した「資格の大原」の場合は、養成施設の期間は約4ヶ月間程度でした。そのうち実際に養成施設に通って授業をうけるスクーリングは二日間のみになります。それ以外は、自宅に送られてきたテキストを利用し課題(問題)を自分で解いて提出する形になります。ただ、科目履修の証明は受講期間後に発行されるので、申し込んでから4ヶ月間はかかることになります。
幼稚園教諭免許状所有者の保育士試験の受験申請は4月と10月になるので、その時点までに養成施設での科目履修の証明を得ておく必要があります。保育士試験は年に2回のみなので、少しずれてしまうと次の試験を受けるのが半年後になってしまいます。
そして、幼稚園教諭免許状所有者で科目が免除される場合の合格通知書は約2ヶ月後くらいになるので、6月か12月に合格通知書が届くことになります。
さらに、保育士登録は申請から保育士証が届く届くまで約1~2ヶ月程度かかります。
わかりづらいので、まとめると以下のようになります。
- 養成施設の受講開始後の約4ヶ月後に科目専修証明書が届く (資格の大原の場合)
- 次の保育士試験(4月か10月)に申し込む
- 約二ヶ月後に(6月か12月)に合格通知書が届く
- 合格通知書を持って保育士登録を行なうと約1〜2ヶ月後に保育士証が届く
保育士登録の方法については以下の記事も参考にして下さい。
資格取得にかかる費用は?
私も利用させてもらった「資格の大原」での取得の例だと、養成講座の価格は税込みで6万円になっています。
この費用は特定一般教育訓練給付制度が適用できるので、条件を満たせばハローワークより40%に相当する額が支給されるそうです。特定一般教育訓練給付金については別途ハローワークに確認してください。
これに加えて、二日間のスクーリングの交通費と保育士試験の受験手数料合計(2,479円)、保育士登録の手数料(5,500円)がかかります。
全部で約7万円程度がかかることになりますが、特例を利用せずに資格を取得することを考えるとかなり安い金額にはなると思います。
費用はかかりますが、勤務している認定こども園などから資格手当などが追加で支給されることもあるので、取得がおすすめです。
おすすめの養成施設は?
おすすめの養成施設は私が利用した「資格の大原」になります。
価格も安いことに加えて、実際に養成施設に通って授業を受けるスクーリングは二日間のみになるので働きながらの取得も可能でした。
もちろんスクーリングは土日の授業の選択も可能でした。スクーリングの会場も大原では以下にあるように多くの施設があるので近隣から選ぶことが可能です。
- 北海道 札幌会場
- 関東・甲信越 水道橋会場・池袋会場・新宿会場・町田会場・立川会場・横浜会場・千葉会場・津田沼会場・水戸会場・大宮会場・宇都宮会場・高崎会場・甲府会場
- 北陸 金沢会場・福井会場
- 関西 大阪会場(新大阪)・難波会場・神戸会場・京都会場・和歌山会場・姫路会場
- 九州 福岡会場・小倉会場・熊本会場
【参考】保育士資格保有者の特例もある
保育士としての実務経験がある場合(3年、かつ、勤務時間の合計が4,320時間以上の場合)に大学などで8単位を取得することで、幼稚園教諭の免許の取得が可能です。
こちらは文部科学省の管轄で、幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例として制度が実施されています。
保育士資格しか持っていない方でも、幼稚園教諭免許の資格が可能になっています。
詳細はhttps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htmを参照してください。
【まとめ】働きながら取得可能なのが保育士資格取得特例制度
保育園や認定こども園で働くつもりがなくても、働いている幼稚園が認定こども園に移行するかもしれません。
幼稚園教諭免許状を持つ方が保育士資格を短い期間で取得できる特例制度について、具体的な手順を私の実体験に基づいて解説しました。
- 特例制度の対象:幼稚園教諭免許と3年かつ4,320時間以上の実務経験
- 養成施設での4科目8単位履修による保育士試験全科目免除
- 最短で1年程度での保育士証取得
- 費用目安:合計約7万円程度
認定こども園(幼保連携型)で働く保育教諭等については、令和11年度末までいずれか一方の資格で勤務可能な経過措置が設けられています。
実務経験を積むことが求められるので、現時点で幼稚園に就業している経験がない場合は、認定こども園で働くということでも可能です。
保育士資格取得特例制度自体は令和11年度末までの期間限定の制度になるので、7万円は少々高いと思うかもしれませんが今後のことを考えると取得がおすすめです。
この情報が、特例制度を利用して保育士資格を取得しようと考えているみなさんの参考になることを願っています。
ぜひ、制度を活用して保育教諭としてキャリアの幅を広げてください。
よくある質問(FAQ)
- Q特例制度はいつまで利用できますか?
- A
幼稚園教諭免許状をお持ちの方が保育士資格を取得できるこの特例制度は、こども家庭庁により令和11年度末まで実施期間が延長されています。
特例制度に必要な要件(実務経験と単位取得)を令和12年3月までに満たせば、令和12年実施の保育士試験までこの特例による受験申請が可能です。
制度の期間にご注意ください。
- Q過去の幼稚園等での勤務経験も実務経験として認められますか?
- A
はい、過去に特定の施設(幼稚園、認定こども園、保育所など)で働いていた経験も、特例制度の実務経験として認められます。
複数の施設での勤務期間を合算することも可能です。
ただし、就業期間や勤務時間を証明する実務証明書の発行を勤務していた施設にお願いする必要があります。
- Q特例制度で必要な単位は、どのように取得しますか?通信講座でも可能ですか?
- A
特例制度の適用を受けるために必要な単位は、厚生労働大臣が指定した保育士養成施設で特例用の科目を履修することで取得します。
養成施設によって学習形態は異なり、通信での学習が中心のものや、通学が必要なもの、またはその両方を組み合わせたものがあります。
ご自身の状況に合わせて、学びやすい方法を選ぶことができます。
これが特例制度の単位取得方法になります。
- Q特例制度を利用すると、保育士試験は全て免除になりますか?
- A
はい、特例制度で定められた所定の単位(通常8単位)を養成施設で修得すると、保育士試験の科目が全て免除になります。
試験を受ける必要がなくなり、自動的に合格となりますので、通常の保育士試験とは大きく異なります。
これは保育士試験の科目免除という点で、幼稚園教諭免許をお持ちの方にとって大きなメリットです。
- Q特例制度を利用する場合、どのような手続きが必要ですか?
- A
特例制度を利用した資格取得の流れは、主に「指定の養成施設で必要な単位を取得する」ことと、「保育士試験の受験申請を行う」という二つの大きなステップがあります。
単位取得後、養成施設から発行される単位修得証明書や、勤務先からの実務証明書など、特例制度の申請に必要な書類を準備し、指定された期間内に保育士試験の申請手続きを行います。
これが特例制度の申請方法です。
- Q特例制度を利用する上で、特に注意すべき点はありますか?
- A
特例制度を利用する上では、いくつか注意すべき点があります。
まず、必要な実務経験を証明するための書類を、過去の勤務先にお願いして書いてもらう必要があります。
勤務していた園が廃園しているなど、証明書の取得が難しい場合もありますので、早めに確認することをおすすめします。
また、制度の期間が決まっているため、計画的に単位を取得し、申請手続きを済ませるように注意が必要です。
特例制度の利用で大変な思いをしないよう、計画的に進めましょう。