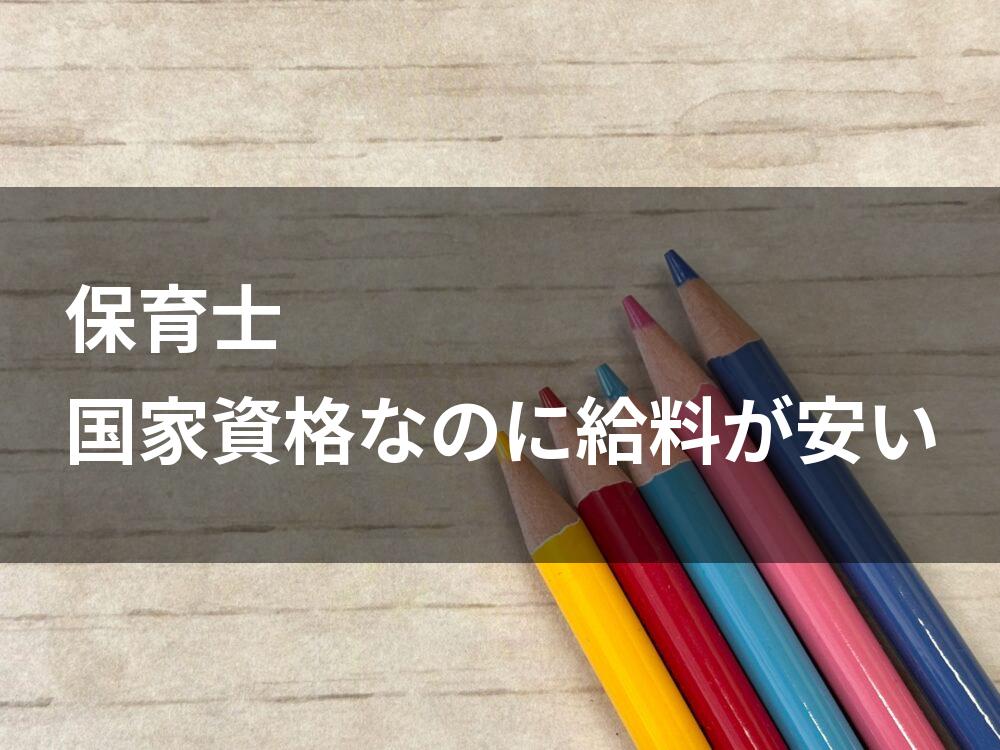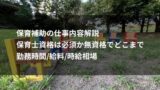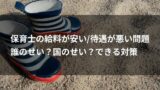| 目次 | 内容 |
|---|---|
| そもそも国家資格ってなに? | ・国が法律で定めた資格制度 ・個人の能力や知識を国が判定し、専門家として認める資格 ・高いハードルがあり、国家試験合格や国認定の養成学校での認定で取得 ・国家資格、公的資格、民間資格の3種類に分けられる |
| 保育士の資格は国家資格 | ・厚生労働省が管轄する国家資格 ・国が認めた養成学校で学ぶか、保育士試験に合格すると取得可能 ・資格がないと「保育士」と名乗って働くことができない「名称独占資格」 |
| 保育士の資格は国家資格の中でも給与は低い? | ・保育士の平均年収は、他の国家資格に比べ低い水準 ・保育園での保育業務は、保育士資格がなくても可能な場合がある ・ただし、認可保育園では、原則として保育士資格が必須 |
| 保育士は国家資格だから給料が高くあるべきは間違い | ・国家資格であるという理由だけで給与が高いとは限らない ・保育士の給与は国が定める公定価格に間接的に左右され、企業が自由に決められない ・保育士不足にもかかわらず給与水準が低い現状がある ・保育士の専門性と高い需要を考慮すると、給与は高くあるべき |
| これから資格取得を目指す人には保育士の資格取得はおすすめできるか? | ・全国で需要があり、職探しに有利な場合がある ・人工知能やロボットに代替されにくく、将来的な安定性が期待できる ・少子高齢化で子どもの数が減る可能性も考慮が必要 ・自身の適性や社会の変化を考えて資格取得を判断すべき |
| 保育士だから給料は高いべき!と言えるようにしたい | ・保育士の給料が低いのは事実 ・「国家資格だから」ではなく、その専門性と高い需要から給与が高くあるべき ・保育士個人も、子どもや保護者へ価値提供に努める姿勢が必要 |
| まとめ:保育士は国家資格なのに給料が安い?国家資格だから給与は高いべき? | ・保育士は国家資格だが、他の国家資格と比べ給料水準が低い現状 ・「国家資格だから」という理由だけで給与の高さは決まらない ・給与は国の公定価格や需要・供給に左右される ・保育士不足解消には給与引き上げが有効な解決策の一つ |
| よくある質問(FAQ) | ・保育士の低い給与水準は、公費依存や専門性の経済的過小評価に由来 ・国家資格でも高給とは限らず、他の国家資格職より低水準 ・低い給与は人材不足の主要因であり、国は処遇改善策に取り組む ・将来性: 全国での需要や人工知能代替の低リスクは利点、キャリアは自身の適性や社会の変化で判断 |
- 保育士は国家資格なのに給料が安い!
- 国家資格だから給与は高いべき?
保育士の仕事は子どもたちの成長を支える非常に重要な役割を担う、大切な仕事です。
この記事では、保育士が国家資格であるにもかかわらず「給料が安いのはなぜだろう」「国家資格だから給与は高いべきではないか」といった疑問に対し、その実態と背景を詳細に紐解いています。

国家資格である保育士の給料は、なぜこんなに低いのでしょうか?

保育士の給与水準には、国家資格であることとは別の、社会的な背景が深く関係しています。
私としては、保育士は国家資格だから給料が高くあるべきではなく、保育士には高いスキルが必要で、需要も高いため、給料は高くあるべきだ!と言えると良いなと思っています。そう言えるように、保育園で働く上で保育士個人としても責任を持って、子どもたちや保護者の方に価値を提供していくことが大切だと思います。
今回は、保育士は国家資格なのに給料が安い?国家資格だから給与は高いべき?なのかということを、そもそも保育士の給料は本当に安いのかという点も踏まえて説明しています。
保育士の資格を保持しています
その経験が参考になればと思います
そもそも国家資格ってなに?
本題に入る前にそもそも国家資格とはどういうものなのでしょうか。
国家資格と公的資格と民間資格
日本の資格を大まかに分けると、 国家資格と公的資格と民間資格の三種類になります。
国家資格には、
- 建築士
- 医師
- 保育士
- 公認会計士
- 弁護士
- 行政書士
などがあり、その名の通り国が付与する資格になります。
公的資格は、一見、国家資格と見分けるのが難しいものになりますが、地方自治体や公益法人、財団法人などによって管理・付与される資格になります。
- 日商簿記検定
- 販売士検定
- 日本語能力試験
- 実用英語技能検定
などがこの一例になります。
民間資格はそれ以外のもので、国や公的機関ではなく民間で管理・付与される資格になります。
例えば、
- TOEIC
- インテリアコーディネーター
- ソムリエ
などたくさんの種類の資格が該当します。
国家資格とは?
国家資格とは、国が法律によって認めた資格で、個人の能力や知識の判定をする資格制度になります。つまり、国が認めた専門家のことをさします。なので、国家資格を取得するには高いハードル(年齢、学歴、実務経験)がある場合が多いです。
国家資格を取得するには、国家試験を合格するか、国が認めた養成学校などで認定条件を満たす必要があります。
保育士の資格は国家資格
保育士の資格は数ある国家資格のなかの一つです。管轄は厚生労働省になります。保育士の管轄が厚生労働省なのは、保育園が厚生労働省の管轄であるためです。
保育園の管轄が厚生労働省なのは、保育園が就労中の保護者の子どもを預かるという性質があるためです。反対に、似ている機関である幼稚園は文部科学省の管轄です。
保育士の資格を取得するには、おおまかに二通りの方法があります。
国が認めた養成学校で単位を取得し認定されるか、保育士試験を受験する必要があります。保育士試験の受験には学歴などの条件も存在します。
保育士の資格の取得方法などについては、以下の記事を参照してください。
【ちなみに】保育士の資格は「名称独占資格」
保育士の資格は名称独占資格と言って、資格を持っていないと保育士と名乗って保育園で働くことが出来ません。
ちなみに、医師や一級建築士というような資格は、業務独占資格と言って、名乗ることをはもちろん、普通の人が禁止されていること、できないことを仕事として行うことができます。
保育園で保育士が就業する際は、保育士証という証明の提出を求められるので、それをもって保育士の資格があることを証明しています。
保育士の資格は国家資格の中でも給与は低い?
保育士という職業が国家資格の必要な仕事の中でも給与が低いということは間違いないと言えます。様々な、資格関連の情報をみていても、保育士の平均年収は300万円程度と記載されていて、他の国家資格と比較しても低い水準になります。
気になる方は、「国家資格 平均年収」などのワードで検索をしてみてください。様々な資格の平均の年収を調べることができます。ただし、国家資格のなかには、必ずしも資格の種類が職種と結びついてないものもあるため、資格と給料が結びつかないものあります。
例えば、見落としがちなところだと、運転免許は国家資格ですが、仕事で運転をする人が全員ドライバーやタクシー運転手というわけではないですよね。なので、国家資格を持っていて、その資格が必要な仕事をしていたとしても、必ずしも資格の種類と職種が結びついているとは限らないということになります。
保育園では保育士の資格が無くても保育業務をすることはできる
付け加えると、保育園で保育業務をするためには必ず「保育士」の資格が必要というわけではありません。保育補助の業務や子育て支援員の研修などもあるため、保育園で働くのに、必ずしも保育士の資格が必要ということではありません。
ただし、もちろん、じゃあ誰でも働けるかというとそういうわけではなく、保育園その種類によって必要な保育士資格者の割合というのが決まっています。
例えば、認可保育園の場合は、基本的に配置基準の100%が保育士である必要があります。一方で、認可外保育施設の場合は、基本的には、配置基準の50%以上が保育士資格保持者であれば良いことになっています。
認可保育園では実質的に保育士の資格は必須
保育園では保育士の資格が無くても保育業務をするができると書きましたが、認可保育園で働くには、例外はありますが、実質的に保育士の資格があることは必須です。
保育士の配置基準が定められており、この基準における100%の人員が保育士資格を持っている必要があります。例外というのは、この保育士の配置基準を上回る場合の人員などをさします。わかりやすく簡単に言うと、保育士が5人が必要な状態で、保育士5人と無資格1人が保育業務に当たるという状態のことを指します。
逆に認可外保育施設や小規模保育事業B型の保育園などであれば、必ずしも100%の人員が保育士資格を持っている必要はなく、保育施設の種類によっても異なりますが、5割以上の保育士等の資格保有者がいれば良いということになっています。
じゃあ、認可保育園では、絶対に保育士の資格が無いと働けないのかというとそういうわけではありません。先ほどの保育士資格の保有者の割合は、あくまでも配置基準に対してです。つまり、配置基準を満たしたうえで、さらに手厚く保育者を配置いしたいというような場合は、無資格者の方が働いても良いということになります。
それを踏まえると、例えば、認可外保育施設である〇〇保育園は保育士資格保有者の配置基準を満たしているから、無資格でも働ける!というように思うかもしれませんが、そうとは限りません。最終的には、無資格者を雇うか雇わないかは保育園次第なので、「うちは資格保有者のみ採用します」という保育園に採用してもらうということは難しいでしょう。
保育士は国家資格だから給料が高くあるべきは間違い
例えば「ITパスポート」という経済産業省が認定している国家資格がありますが、誰でも受験が可能で合格率60%程度の資格があります。この資格はパソコンの入門資格で、大手のIT会社に対して就職時などにアピールしたとしてもほとんど意味をなさないと揶揄されることもあるようです。このように、国家資格というものは、保有していれば職業が保証されるというものとは限らず、当然、給与水準が保証されるものでもないです。
逆に国家資格ではない民間資格においても、資格を持っていることで高い給料などを期待できるものもあります。資格をもっていることが能力の証明になり、需要が高い職や仕事につくことができるためです。例えば、民間資格の有名どころはTOIECや英語検定などは、英語のスキルを持っていることの客観的な証明に使われることがあり、会社によっては、採用可否や給与などにも影響を与える場合もあります。
とりわけ民間企業に雇用される場合の給与は、需要などに応じて企業が決めているものです。やはり「国家資格だから給料が高くあるべき」というのは間違いだと言えると思います。
ただし、保育士に関して言うと、保育士不足と言われる中で、国は保育士の給与水準を上げるということがなかなか進んでいないというのは事実です。仮に私立の民間の保育園であっても、保育士の給料は会社が完全に勝手に決められるというわけではありません。
そもそも、保育園の運営費は国が公定価格として決めていますし、そのなかで、保育園は基準を満たしつつ運営をするので、保育士の給料もある程度の相場内で決まります。つまり、国が間接的に保育士の給与を決めているといっても過言ではありません。
民間企業であっても保育園で働く保育士の給与はほとんど国が定めているので、需要に対して給与待遇が不足しているということは確実に言えるはずです。
むしろ、国はこの状態を乗り切るために、保育士の資格を保有していない無資格者でも保育園で働けるように規制緩和を行っているということもあります。
保育士資格を持っていても保育士として働いていない潜在保育士も多くいる、そして、保育士不足が続いていているので、需要に対して給料が追いついていないという点は間違いないです。
これから資格取得を目指す人には保育士の資格取得はおすすめできるか?
保育士という職業が国家資格の必要な仕事の中でも給与が低いということは間違い無いですが、これから資格取得を目指す人には保育士の資格取得はおすすめできるでしょうか。こればかりは、本人の適性や能力、考え方もあるので、一概にはなんとも言うことができません。
ただし、保育士の資格に他の資格取得に比べてメリットがないという無いわけではなりません。
保育園は日本全国どこにでもあり、資格があれば、どこでも働くことができる可能性があります。また、昨今は特に保育士不足なので、労働者である保育士が有利に職を探すことができると思います。
将来的にロボットやAIに完全に置き換わって職を失ってしまうということも考えにくいので、将来に渡って職に困るという確率を減らすことができます。ただ、一方で日本は少子高齢化であることは間違いなく、子どもがいなくなれば、保育士の必要も少なくなっていくという懸念点もあります。
資格取得においては、自分自身の仕事の適正や、今の状況、もちろん今後の時代の変化なども踏まて考慮すべきことだと思います。国家資格だからとりあえずとってみるとから、比較的簡単そうだからという考えでは、あまり人生において良い影響を与えるのは難しいかもしれません。
また、資格取得の難易度も様々なので、保育士の資格を取りたいからと言って必ず取得できる保証もなければ、保育士以外の資格取得を目指したからといってその資格が取得できるわけでもないので、進路を決めるというのは簡単なことではないでしょう。
保育士だから給料は高いべき!と言えるようにしたい
今回は、保育士は国家資格なのに給料が安い! という件に関しての個人的な見解をまとめました。保育士は国家資格なのに給料が安い?国家資格だから給与は高いべき?なのかということを、そもそも保育士の給料は本当に安いのかという点も踏まえて説明しました。もちろん、国家資格の職業は給料が高くあるべきだという主張もあっても良いと思っています。
保育士の給料が安いのは事実で、他の国家資格と比較しても安い水準であることは間違いないと思います。でもそれには様々な背景や理由があってそうなっていることだと思います。
保育士は国家資格だから給与給料が高くあるべきではなく、保育士には高いスキルが必要で、需要も高いため、給料は高くあるべきだと言えるようになると良いなと私は思っています。あくまでも個人的な考えです。なので、国家資格は給与が高くあるべきという意見もあってしかるべきだと思います。
逆にそういえるように、保育園で働く上で保育士個人としても責任を持って、子どもたちや保護者の方に価値を提供していくことが大切だと思います。
まとめ:保育士は国家資格なのに給料が安い?国家資格だから給与は高いべき?
今回は、保育士は国家資格なのに給料が安い?国家資格だから給与は高いべき?なのかということを、そもそも保育士の給料は本当に安いのかという点もふまえて考えてみました。
保育士は国家資格でありながら、他の国家資格と比較して給料水準が低いという現状に対し、疑問を抱く方も多くいます。
この記事では、保育士の給料が低い背景と、国家資格という側面から給与の妥当性について深く考察しています。
保育士の国家資格における給料水準の妥当性は、多くの議論がなされています。
しかし、現在、保育士として働く人材が不足していることは事実であり、日本社会にとって不可欠な保育士の確保には、給与の引き上げが有効な解決策の一つと考えられます。これは、国家資格であるかどうかの基準にとどまらない問題です。
この記事を通じて、保育士という職業が持つ社会的な価値と、現在の給与体系が抱える課題について深くご理解いただけました。
この情報が、ご自身のキャリアを考える上での参考となり、保育士の待遇改善に向けた社会的な動きにつながることを願っています。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士は国家資格であるにもかかわらず、なぜ給料が安いと言われることが多いのですか?
- A
保育士の給料が低いとされる理由には、複数の要因があります。
まず、保育園の運営は公費に大きく依存しているため、人件費に充てられる費用が制度上限定される傾向があることが挙げられます。
また、歴史的に女性が担う仕事として位置づけられてきた背景から、その専門性や社会的貢献が経済的に過小評価されてきた側面も指摘されています。
さらに、子どもの保育だけでなく保護者支援や事務作業など、多岐にわたる業務で精神的・肉体的な負担が大きい割に、それが給与に十分に反映されていない現状が存在します。
これらが、保育士の給料が安いと感じられる主な原因です。
- Q国家資格である保育士は、他の国家資格と同じように給与が高いべきなのではないでしょうか?
- A
国家資格であるからといって、必ずしも給与水準が高いとは限りません。
給与は、その資格が持つスキルや需要、市場の状況によって大きく変動するものです。
保育士の仕事は高い専門性と重い責任を伴いますが、給料が決定される要因には、運営費が公定価格で定められていることや、国による財源投入の制約も影響します。
そのため、「国家資格だから給与が高いべき」という単純な論理では語れません。
保育士は、その専門性と社会的需要の高さから給与が高くあるべきであると私は考えています。
- Q保育士の平均年収は、看護師や教員といった他の国家資格職と比べて具体的にどのくらい違いますか?
- A
保育士の平均年収は、他の国家資格を持つ専門職である看護師や公立学校教員などと比較すると、一般的に低い水準にあると認識されています。
これは、リサーチでも指摘されている共通の認識です。
保育士は子どもの命を預かる重い責任と、発達支援や健康管理など多岐にわたる専門知識を要します。
それにもかかわらず、他の国家資格職との間で給与水準に差があることが、給料の妥当性について疑問を持たれる一因となっています。
- Q保育士の給料を引き上げるために、国や自治体ではどのような取り組みが進められているのですか?
- A
保育士の給与改善に向けて、国はこれまで「処遇改善等加算」などの施策を行ってきました。
これは、保育士の給料に上乗せされる形で支給される手当のようなものです。
また、一部の自治体でも独自の処遇改善策を講じる動きがあります。
しかし、財源の制約や処遇改善加算の仕組みの複雑さから、現場の保育士がその効果を十分に実感しにくいという課題も指摘されています。
依然として保育士の待遇改善や給与引き上げは、国にとって重要な政策課題の一つです。
- Q保育士の給料が低いことが、保育士の人材不足に繋がっているというのは事実ですか?
- A
はい、給料の低さが保育士不足の一因となっていることは事実だと考えられます。
低い給与水準は、保育士を目指す方が減少する原因となるだけでなく、すでに保育士として働いている方の離職率を高める要因にもなっています。
子どもたちの命を預かる重い責任と多岐にわたる業務内容に対して給料が見合わないと感じる保育士が多く、これが結果として質の高い人材の確保や定着を難しくしているのが現状です。
適切な給与水準は、優秀な人材の確保と保育の質の向上に直結すると確信しています。
- Q現状の給料水準を踏まえて、今後保育士として働き続けることを考える上で、どのような視点を持つと良いでしょうか?
- A
現状の給料水準は考慮すべき重要な点ですが、保育士という仕事は日本全国で需要があり、資格があれば比較的職に困りにくいというメリットがあります。
また、AIやロボットに完全に代替されにくい専門職であるため、将来にわたって安定した職に就く可能性が高いと捉えています。
もちろん、少子高齢化による子どもの減少という懸念点も認識する必要があるでしょう。
ご自身の適性や仕事への価値観、そして今後の社会の変化などを総合的に考慮し、キャリアパスを検討することが大切です。
保育士の給料が改善されるような社会の動きも注視していく必要があります。