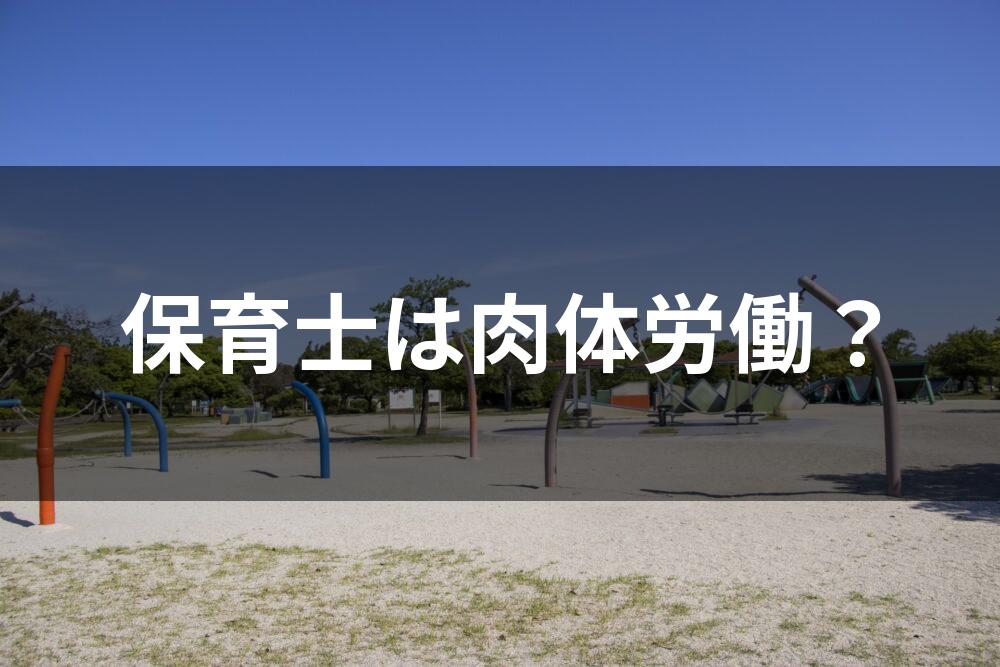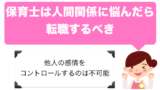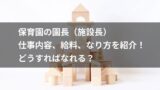| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育士の仕事は肉体労働も多い | ・子どもとの散歩、外遊びなどで身体を動かす ・抱っこ、中腰、立ち膝など腰に負担がかかる姿勢が多い ・体を動かす業務が圧倒的に多く、肉体労働を伴う |
| 精神的な疲労も少なくない | ・チーム体制で、同僚や上司との人間関係に悩むことがある ・休暇時の業務カバーなど、連携が必須となる場面が多い ・保護者からの指摘や苦情対応も精神的疲労の原因 |
| 保育士の仕事に体力はどれくらい必要? | ・一日中動き回れる程度の体力が求められる ・必要な体力は園や担当によって異なる ・仕事への慣れで多くの体力的な負担を軽減できる |
| 肉体労働が多いということは悪いことではない | ・身体を動かす仕事は、座り仕事と異なり健康維持につながる ・がんのリスク低減など、研究結果も健康面での利点を示す ・業務外での運動習慣が不要となり、時間や費用を節約できる |
| 体力がない私は保育士に向いていない? | ・日々の業務で体力は自然とつき、慣れでカバーできる ・運動で体力強化は可能、継続的な筋力トレーニングは必須でない ・体力よりも栄養、睡眠、免疫力など体調管理が重要 ・体力的な負担が少ない「ホワイト保育園」選びが最も大切 |
| 保育士の体力が落ちてきてしまった場合はどうすれば良い? | ・園長に業務内容の変更を相談、代替案を提案する ・接骨院や整体など専門家への相談も有効 ・週休制度や時短勤務、派遣・パートなど雇用形態を変える ・ホワイト保育園への転職も有力な選択肢となる ・キャリアパスとして園長職を目指す道もある |
| 【まとめ】保育士の仕事は肉体労働? | ・保育士の仕事は肉体的・精神的疲労が伴う ・肉体労働は健康維持につながる良い面もある ・体力は慣れで補え、体調管理や免疫力も大切 ・負担の少ない「ホワイト保育園」選びが最も重要 |
| よくある質問(FAQ) | Q保育士の仕事は、具体的にどのような肉体労働を伴うのでしょうか? A乳幼児の抱っこやおんぶ、活発な外遊びや散歩、教材や遊具の持ち運びなどが挙げられる 子どもと同じ目線で中腰やしゃがんだ姿勢を長時間保つため、腰や膝に負担がかかる Q体力に自信がないと、保育士の仕事は続けることが難しいですか? A日々の業務で自然と慣れ、最低限の体力を身につければ順応できる 体調管理や免疫力維持が重要、無理なく働ける「ホワイト保育園」選びも不可欠 Q保育士の仕事における体力的な負担を軽減し、効率的に疲労を回復させる方法はありますか? A職場での業務分担や道具活用、意識的な休憩や水分補給が効果的 適度な運動、十分な睡眠とバランスの取れた食事で疲労回復を促す 不調があれば接骨院など専門家に相談し、適切なアドバイスを得る Q体力が落ちてきたと感じる保育士が、無理なく働き続けるための選択肢にはどのようなものがありますか? A園長への業務内容変更の相談、代替案提示が有効な方法 週休3日や時短勤務、派遣・パートなど雇用形態の変更も選択肢 体力負担が少ないホワイト保育園への転職も検討する Q体力面で不安があっても、快適に長く働ける「ホワイト保育園」の見分け方はありますか? A残業が少なく持ち帰り仕事がない、人間関係が良好な点が重要 勤務体制や福利厚生が充実しているかを確認し、転職サイトで情報収集する Q保育士は年齢を重ねて体力が落ちた場合、何歳くらいまで働き続けることができるのでしょうか?また、どのようなキャリアパスがありますか? A特定の年齢制限はなく、体力が変化しても多様な働き方が可能 キャリアパスとして園長職、乳児クラス担当、療育施設への転職がある 体調やライフスタイルに合わせた勤務形態の調整も有効な選択肢 |
- 保育士の仕事は肉体労働?
- 体力はどれくらい必要?
保育士の仕事は、子どもたちの成長を支えるやりがいのある仕事です。
しかし、日々の業務で体力的な負担を感じる方も少なくありません。
この記事では、保育士の仕事が本当に肉体労働なのか、どの程度の体力が必要なのかを詳しく解説します。
さらに、もし体力が落ちてしまった場合にどのように働き続けるべきか、具体的な解決策と選択肢も紹介します。

保育士の仕事は大好きだけど、最近体力が落ちてきてこのまま続けられるか不安だな…

体力はとても大切ですが、それ以上に「ホワイト保育園」を選ぶことが重要です
その経験が参考になればと思います
保育士の仕事は肉体労働も多い
先に、保育士の仕事は肉体労働なのかという疑問に答えると、保育士の仕事は肉体労働であると言えると思います。
- 散歩
- 外遊び
- うた・手遊び
- ピアノ
これらの仕事内容もそれぞれに、体を動かす動作が付随します。外遊びでは子どもとの鬼ごっこなどで走ることもあります。特に、行動の予測がつきにくい子どもたちを相手にするため、すべての動作を安全に配慮しながら行うことになります。文字で見る表現よりも肉体的に大変な動作が必要になってきます。
保育士の一日の仕事内容については以下の記事でも解説しているので参考にしてください。
よく保育士の仕事を知らない人が「子どもたちと遊んでいるだけ」と表現することもありますが、まったく的を射ていない表現だと思います。
また、子どもたちを相手にするため、中腰や立ち膝での動作も多く腰に負担がかかることも多いです。
- 書類仕事
- パソコンを使った入力業務
などの仕事がないわけではないですが、圧倒的に前者のような体を使う業務が多くなっています。保育園における保育士の仕事は、肉体労働を伴うことが確実だと言えます。
精神的な疲労も少なくない
保育士の仕事は肉体労働の部分も多いですが、精神的な疲労も少なくないです。特に精神的な疲れを感じてしまうのが、人間関係によるものです。これについては、保育園での保育士の仕事に関わらず、世の中のどの仕事についても言えることかもしれません。
ただ、特に保育士の仕事はチーム体制で行う仕事で、黙々と自分の役割をこなしていけば成立するというわけではないのが特徴です。例えば誰かが休暇をとれば、その分を誰かがカバーするという構図になります。
特に乳児など、0〜2歳時の場合は、1クラスを複数人の保育士で担当する複数担任制をしていることも多いです。主担任・副担任があったとしても、必然的に仕事の分担も必要になってきます。そういったなかで、同僚や先輩保育士、主任保育士、園長などとのやりとりが必ず必要になるので、人間関係で悩んでしまうことも少なくないです。
先輩保育士や園長からパワハラを受けているような場合でも、無視をして淡々と自分の仕事を行うということが難しく、どこかで必ず苦手な人とも連携を取る必要が出てしまうのがツライ部分でもあります。
また、保護者とのやりとりも精神的な疲労に繋がることもあります。まっとうな指摘であっても、言いがかりのようなクレームであっても、保育士はそれらを受け止めて対処していく必要があります。
保育士の仕事は、体が強ければなんとかなるというわけではなく、精神的にも強くある必要が求められます。
保育士の仕事に体力はどれくらい必要?
保育士の仕事に体力はどれくらい必要かというのはなかなか回答が難しいです。個人的な見解では、一日中動き回ることができる 体力が必要という感じになります。体力的に「〇〇ができないとつとまらない」というような具体的な動作はあまりないと思います。
もちろん、保育園によっても、雇用形態や立場(担任や副担任、何歳児の担当かなど)によっても必要な体力というのは異なってくると思います。
後述していますが、保育士の仕事に必要な体力面は、慣れでカバーできる部分も少なくない上に、ブラック保育園に就職しないということも重要になってくるので、やる前から自分には無理だと決めつけないほうが懸命かもしれません。
肉体労働が多いということは悪いことではない
世間では肉体労働の仕事はあまりおすすめできないと捉える人も一定数いるかとは思います。たしかに、体力を消耗する仕事より、消耗しない仕事のほうが良いように思ってしまうのも理解できます。
もちろん、残業や持ち帰りの仕事で日々の睡眠時間すら削られてしまっているという場合は別ですが、仕事の中で体を動かすことができているということは悪いことではないと個人的には思っています。
それは、座り仕事は病気になりやすいという考え方もあるためです。
座り仕事は病気になりやすい??
日本でも、仕事中に長時間座っていると発がんが増えるという研究結果が出ています。国立がん研究センターの研究グループは、50~74歳の約3万3000人を追跡調査した結果、座ったまま仕事をすることが多い男性では膵臓(すいぞう)がんが、女性では肺がんが有意に増加することを確認しました。
※「座りすぎはがんを招く」https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20201016-OYTET50000/より
このような研究結果もあるので、適度に体を動かすことを仕事にできるということは、逆にメリットが多いと考えることができると思います。
座り仕事で、業務外で健康体を維持するためにジムやプールに通う人もいるので、その必要が少ないことはメリットの一つだと思います。
気持ちとしては「肉体労働 = 大変」と思わずに、体を動かすことが仕事で、ある程度の健康を維持しつつ、お金を貰うことができてラッキーと思うと良いかもしれません。
体力がない私は保育士に向いていない?
これから保育士を目指している人や保育士として働き始めたばかりで自分の体力のなさに気が付き「体力がない私は保育士に向いていない」と思っている人もいると思います。
慣れでカバーできる部分も少なくない
まだ、保育士の仕事を始めたばかりという方は、日々の体力的なしんどさに驚いている人もいるかもしれません。しかし、毎日仕事を続けていると慣れてくる部分も少なくないです。
よく使う部分の筋肉などは必然的に鍛えられますし、しっかりと気を張る部分と、少し手を抜く場面も理解できてくると思います。もっとも、これはどのような仕事でも言えることもかもしれません。
体力はつけることができる
どうしても体力がないという方は、これからでも体力をつけることは可能です。
- ジムに通う
- プールに通う
- ランニングをする
- 通勤時に歩いてみる
などです。ボディビルダーのようにムキムキになる必要はありません。
ちなみに、保育士は仕事外で常に体力づくりを続けなければいけないわけではありません。先程も言ったように、保育士の肉体労働の大変な部分は慣れでカバーすることができる点も多いと思います。最低限の体力をつければ、あとは仕事をしながら慣れていくことができると思います。
体力よりも体調管理も重要
体力が少ない部分は、しっかりと栄養のある食事を取り、きちんと睡眠を取ることも大切です。そうすることが体力の回復に繋がるためです。保育士は、よく寝てよく食べるということが一番大切だったりするのかもしれません。
また、保育士の仕事では、子どもも含めて多くの人と日々、近い距離で接するため、様々な菌やウイルスとも接する機会が多いです。そのため、体力というより、免疫力なども非常に重要になってきます。風邪を引きにくいような体作り、風邪を引いたとしてもすぐに回復できるような免疫力などがより必要になります。
ブラック保育園に就職しないことも大切
そもそもの話にはなりますが、「保育士」という仕事を一括りに考えてしまうということも間違っているかもしれません。例えば、世の中には「営業」と呼ばれる仕事がありますが、会社によっても部署によってもその役割や必要な能力、体力を異なると思います。
保育士も同様で、働く保育園によって体力的な負荷は大きく変わってきます。
毎日残業時間が多かったり、持ち帰っても仕事をしなければいけない日々が続いてしまうと、体力の回復が間に合わなくなってしまいます。夜に時間がなければ栄養が少ないお弁当を食べてしまったり、睡眠もきちんと取れなくなってしまい、それが負の連鎖になってしまい、体調不良になってしまうかもしれません。
体力自体はあることに越したことはないですが、それ以上にきちんとしたホワイト保育園に就職するということが大切です。
保育士の体力が落ちてきてしまった場合はどうすれば良い?
保育士として働いていて、体力が落ちてきてしまったなと言う場合の対処法などを紹介しています。
業務の変更などを園長に申し出る
保育士が自分の体力落ちてきてしまって業務の負担に耐えられないと思った場合にまずできる対処法の一つが園長などに相談するということです。自分の仕事内容の調整をしてもらうためです。
業務の変更などを園長に申し出る際のコツは、保育園や他の同僚にもメリットが出るような提案をすることです。
単に、負担になってしまっている業務をなくしてほしいという要望だけをするよりも、その代わりに自分ができることを多くやるという交渉も大切です。例えば、散歩に行けない代わりに、その時間に行事の準備の作業などを多くするというような形です。
適材適所で保育士の人員を配置する責務は保育園の園長にもあると思うので、自分の状況などを踏まえた要望などは積極的にしていくべきだと思います。
専門家に頼る
体力が落ちてしまったと感じる原因になっている体の痛みなどは専門家などに聞いてみたり、施術によって改善する可能性もあります。
- 接骨院
- 整骨院
- 整体
症状によって上記のような専門家のいる施設で相談をしてみるのが良いと思います。
立ち方、座り方、歩き方、靴の変更などで症状などが劇的に改善する場合もあります。体力が落ちてしまったと諦めるのではなく、一見の価値はあると思います。
### 雇用形態を変更する
雇用形態を変更することで、体力的な負担が軽減される可能性があります。単純に労働時間が短くなったり、担任の有無や責任の内容や範囲が変わる場合があるためです。
- 週休3日勤務制度
- 時短勤務制度
- 派遣・パートでの勤務に変更
などのように雇用形態や勤務形態を変えるということも選択肢のひとつです。
現在働いている保育園で雇用形態を変えるパターンと、転職という形で雇用形態を変えるというパターンがあります。
転職を視野に入れる
現在就業中の保育園での負担軽減などが難しければ、転職などの際に負担を軽減できるようにするのも良いです。
日々の保育士としての業務の負担軽減には転職もとても有効です。転職の際は労働条件の交渉がしやすいというのもメリットの一つです。今は保育士不足なので、入職時の交渉は進みやすいです。しかも、その前提条件があって入職しているので、自分の気持ちや周りの目線を考えても良いです。
特に保育士向けの転職サイトを利用すると条件交渉がしやすいです。例えば「腰が悪いので腰に負担がかかる業務は外してほしい」というような個人ではなかなかしにくい細かい要望を担当のアドバイザーが代わりに行ってくれます。
- マイナビ保育士
 |全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです! - ジョブメドレー保育士
 | 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)

※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。
保育園の園長などの管理者を目指す
ベテラン保育士の方で、体力の低下を気にしている方は、園長職を目指すというのも良いかもしれません。保育園の園長であれば、責任は増しますが、肉体的な負担は現場の保育士と比較して軽減できる可能性もあります。もちろん、園によってはより体力的な負担が増えるという場合もあります。
誰でも簡単になれるわけではないですが、保育士のキャリアという面でも目指すことは悪くないことだと思います。
保育園の園長の特徴やなり方などは以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
【まとめ】保育士の仕事は肉体労働?
保育士の仕事は、肉体労働と精神的疲労が伴いますが、体力よりも職場環境の選択が長期的な働き方において最も重要です。
保育士という仕事は肉体的な負担、かつ、精神的な負担も少なくない仕事です。日常的に体力を使う動作が多いうえに、人間関係の悩みも多い仕事だからです。
私自身は、仕事で肉体的な負担が多いということはメリットだと考えています。普通のデスクワークの人が仕事外でジムやプールに通っていることがありますが、その必要があまりないためです。仕事をすることである程度健康な体を維持することができます。
肉体的にも精神的にも強いということは保育士という仕事をする上ではとても良いことです。もちろん、保育士という仕事に限らず、世の中で生きていくこと全般に言えることだと思います。
本当に保育士という仕事につきたいというのであれば、安易に肉体労働だからやめておこうと思うのはもったいないことかもしれません。体力的な部分は、慣れでカバーできる部分も少なくないです。
そして、体力以上に大事なことは、ブラックな保育園で働かないということです。同じ保育士の仕事でも、ブラック保育園とそうでない保育園では肉体的にも精神的にも疲労度は大きく変わります。
体力自体はあることに越したことはないですが、それ以上にきちんとしたホワイト保育園に就職するということが大切です。
体力に不安を感じても諦めず、この記事で紹介した具体的な対策や、体力的な負担を軽減できるホワイト保育園選びを進めていきましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士の仕事は、具体的にどのような肉体労働を伴うのでしょうか?
- A
保育士の仕事は、子どもの安全確保と成長を支えるために多くの肉体的な動作を伴います。
例えば、乳幼児の抱っこやおんぶ、子どもたちと一緒の活発な外遊びや散歩、教材や遊具の持ち運びなどが挙げられます。
また、子どもと同じ目線で関わるために、中腰やしゃがんだ姿勢を長時間維持することも多く、腰や膝に負担がかかる場合があります。
これらは日々の業務において頻繁に発生し、保育士の肉体労働は多岐にわたるのが実情です。
- Q体力に自信がないと、保育士の仕事は続けることが難しいですか?
- A
体力に自信がないと感じていても、保育士の仕事を続けることは十分に可能です。
保育士として働く上で必要な体力は、日々の業務を通じて自然と慣れていく部分が多く、最低限の体力を身につければ、あとは仕事をしながら順応できます。
体力をつけるための運動を取り入れることも効果的です。
また、体力そのもの以上に、日頃からの体調管理や免疫力維持が非常に重要です。
最も大切なのは、無理なく働ける「ホワイト保育園」を選ぶことであると考えています。
- Q保育士の仕事における体力的な負担を軽減し、効率的に疲労を回復させる方法はありますか?
- A
体力的な負担を軽減し、疲労回復を促すには、いくつかの方法が考えられます。
職場では、園内で体力が必要な業務を他の職員と分担したり、台車などの道具を積極的に活用したり、意識的に休憩や水分補給を行うことが大切です。
個人的な対策としては、適度な運動を継続し、疲労回復のために十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけることが挙げられます。
体の痛みや不調がある場合は、早めに接骨院や整体などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも負担軽減につながります。
- Q体力が落ちてきたと感じる保育士が、無理なく働き続けるための選択肢にはどのようなものがありますか?
- A
体力が落ちてきたと感じる場合は、まず園長に相談し、業務内容の変更を申し出るのが一つの方法です。
園や他の同僚にもメリットが出るような提案をすることで、体力を使う業務を調整してもらえる可能性があります。
また、雇用形態を変更することも有効な選択肢です。
週休3日勤務や時短勤務、派遣・パートでの勤務に変更することで、労働時間が短くなったり、責任の範囲が変わるため、体力的な負担を軽減しながら長く働き続けられます。
現在の園での調整が難しい場合は、体力的な負担の少ないホワイト保育園への転職を視野に入れることもできます。
- Q体力面で不安があっても、快適に長く働ける「ホワイト保育園」の見分け方はありますか?
- A
体力的な不安を抱えながらも長く快適に働くためには、「ホワイト保育園」を選ぶことが極めて重要です。
ホワイト保育園は、残業が少なく持ち帰り仕事がほとんどないなど、労働環境が整備されています。
職員間の人間関係が良好で、困った時に助け合えるチームワークが整っている園も、精神的な負担を軽減するポイントです。
また、保育士の健康やワークライフバランスを重視し、勤務体制や福利厚生が充実しているかも重要な見分け方です。
転職を考える際には、保育士専門の転職サイトなどを利用し、アドバイザーを通じて園の雰囲気や実態について詳しく情報収集することをおすすめします。
- Q保育士は年齢を重ねて体力が落ちた場合、何歳くらいまで働き続けることができるのでしょうか?また、どのようなキャリアパスがありますか?
- A
保育士として働く上で、特定の年齢制限は定められていません。
体力が年齢とともに変化しても、様々な働き方が可能です。
体力が落ちてきたと感じる場合、キャリアパスとして管理職である園長を目指す道があります。
園長は、現場での肉体的な負担は軽減される可能性があります。
他にも、乳児クラスなど比較的運動量の少ない年齢層の担当に異動したり、児童発達支援センターや放課後等デイサービスといった、より個別の支援が中心となる施設への転職も選択肢の一つです。
自分の体調やライフスタイルに合わせて勤務形態を調整することも、長く働き続けるために有効な方法です。