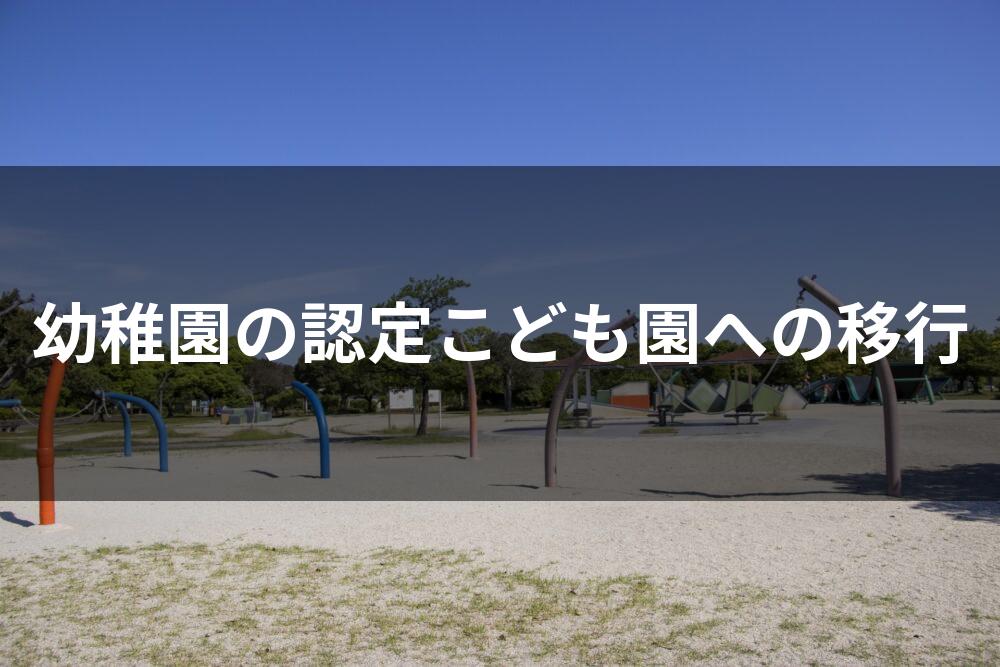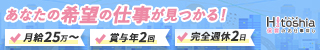| 目次 | 内容 |
|---|---|
| そもそも認定こども園ってなに? | ・幼稚園と保育園、両方の機能を合わせ持つ施設 ・「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4種類が存在 |
| 幼稚園から認定こども園への移行が急増中 | ・内閣府の報告で382カ所の幼稚園が移行 ・認定こども園全体の数は1048園増加 ・園児数も増え、移行は増加傾向にある状況 |
| なぜ幼稚園は認定こども園へ移行する? | ・共働き世帯増加で保育園の利用希望者が増える ・幼稚園は定員割れを起こす現状があるため ・保護者・国や自治体・幼稚園それぞれにメリットがある移行 |
| 既存の利用者(保護者や児童)はなにが変わる? | ・基本的には利用している保護者や子どもへの大きな変化はない ・預かり時間の増減もない ・0〜2歳児が入園する ・先生の人数が増えるなどの周囲の変化がある |
| 働いている幼稚園教諭にとってはなにが変わる? | ・幼保連携型や幼稚園型への移行が多い ・0〜2歳児担当や保育士資格の取得が求められる可能性 ・先生の人数が増え、給料が増える場合がある ・保育士宿舎借り上げ制度などの利用が可能になる ・就業時間、シフト、休暇など働き方が大きく変化する可能性 |
| 保育士は幼稚園から移行した認定こども園で働ける? | ・現時点では保育士資格のみで働ける場合が多い ・将来的には幼稚園教諭と保育士、両方の資格が必要になる見込み ・特例制度を活用し、幼稚園教諭免許の取得を検討 |
| 【まとめ】幼稚園の認定こども園への移行が増えているのはなぜ?働き方はどう変わる? | ・幼稚園の需要減と保育ニーズ増加が主な理由 ・保護者、国・自治体、幼稚園にとってメリットがある ・幼稚園教諭は0〜2歳児担当や働き方など変化が大きい ・宿舎借り上げ制度の利用などメリットも期待される |
| よくある質問(FAQ) | ・少子化や共働き世帯の増加が背景 ・国や自治体が待機児童解消を目指す要因 ・幼稚園側も財政安定化や質の高い教育を目指す選択 |
| 幼稚園教諭の働き方の変化、メリット・デメリット | ・メリット: 就職先の多様化、安定雇用、キャリアアップの機会 ・デメリット: 業務負担増、異年齢保育対応、保育士資格取得の学習負担 ・ライフワークバランスの維持が課題となる場合がある |
| 0歳児担当の場合の準備 | ・乳児の発達に応じた保育知識の習得 ・病気・安全管理の専門知識、保護者との連携強化 ・研修や学習での専門性向上 |
| 給料・福利厚生の変化 | ・国からの補助金増で給料増の可能性 ・「保育士宿舎借り上げ制度」や「処遇改善手当」対象の可能性 ・福利厚生の充実が期待される |
| 幼保特例制度 | ・幼稚園教諭免許保有者が保育士資格を取得しやすくする期間限定の制度 ・通常の少ない単位取得で資格が得られる特例措置 ・保育教諭資格取得をスムーズにするもの ・利用条件や期限は都道府県・年度で異なるため確認が必要 |
| 今後のキャリア形成で意識すべき点 | ・自身の興味や専門性を明確化する ・必要な資格(保育士資格など)の取得 ・多様な年齢の子どもへの対応スキルを磨く研修への参加 ・「やりがい」を見つけるきっかけにもなる |
- 幼稚園の認定こども園への移行が増えているのはなぜ?
- 勤務している職員の働き方はどう変わる?
幼稚園教諭の皆様、お勤めの園が認定こども園への移行を検討していることで、自身の働き方に漠然とした不安を感じていませんか。
この記事では、なぜ幼稚園の認定こども園への移行が増えているのか、そしてそれに伴い幼稚園教諭の働き方がどう変わるのかを具体的にわかりやすく解説します。

今後、私の働き方はどう変わるのでしょうか?

不安を解消し、具体的な働き方の変化を把握できます。
幼稚園で働いている方に幼稚園教諭の方にとっては、他人事ではないことだと思います。
その経験が参考になればと思います
そもそも認定こども園ってなに?
認定こども園は、教育と保育の両方を行う施設で、幼稚園と保育園の両方の機能を兼ね備えた施設になります。
一般的に認定こども園と言っても、複数の種類があります。
幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
幼稚園型
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
保育所型
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
※子ども家庭庁「認定こども園概要」https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kodomoen/gaiyouより
認定こども園の特徴などの詳細は以下の記事でも紹介しているので参考にしてみてください。
幼稚園から認定こども園への移行が急増中
幼稚園382カ所が認定こども園に移行したと、内閣府が報告しています。
幼稚園382カ所、保育所716カ所、その他の保育施設17カ所がこども園に移行したほか、新規開園も62カ所あった。なお、複数の施設が合併して1つのこども園になったケースなども含まれるため、移行数と増加数は一致しない。
在籍園児数は▽幼保連携型 68万7817人(同9万732人増)▽幼稚園型 15万1474人(同1万6616人増)▽保育所型 8万7671人(同1万6979人増)▽地方裁量型 4323人(同337人増)
※「認定こども園、1048園増加 幼稚園や保育所の移行進む」https://www.kyobun.co.jp/news/20190927_02/#:~:text=%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%83%BB%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6,%E3%81%AE%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%8C%E9%80%B2%E3%82%93%E3%81%A0%E3%80%82より
このように、認定こども園の数は増加傾向にあり、幼稚園からの移行も増えています。
なぜ幼稚園は認定こども園へ移行する?
昨今の日本では、保育園の利用希望者が増えている一方で、幼稚園の利用希望者は減少傾向にあります。
これは、共働きの増加などにより、より長時間にわたって子どもの保育を行う保育園の利用希望者が多いためです。少子化自体は進んでいますが、それ以上に保育園の利用希望者が増加している状況です。
幼稚園に子どもを預けた場合だと、基本的には両親ともにフルタイム(8時間勤務)の仕事をするのは難しいという現状がありますよね。なので、保育園は不足していて、逆に幼稚園は定員割れを起こしているところもあります。
そんななかで、
- 保護者にとっては、保育園と同様の条件で子どもを預けることができる施設が増える
- 国や自治体にとっては保育の待機児童を減らすことができる
- 既存の幼稚園施設にとっては、定員を満たすことができる、また、運営にかかる補助金等も増加する場合がある
というそれぞれのメリットがあるため、幼稚園から認定こども園への移行が進んできています。
既存の利用者(保護者や児童)はなにが変わる?
すでに幼稚園に子どもを入園させている利用者にとっては、認定こども園に移行した場合に、何か違いが発生するのでしょうか。
結論から言うと、既存の利用者にとっては、もちろん施設ごとの方針などによりますが、特に大きな変化はないことが多いです。
逆に言うと、利用している幼稚園が認定こども園になったからといって、そのこと自体で預かり時間が増える・減るということもありません。あくまでも既存の幼稚園に保育所の機能が加わるだけなので、既存の利用者には大きな変更がない場合が多いです。
ただし、通園している園児にとっての環境の変化としては、
- 0−2歳児が入園する
- 先生(保育士・幼稚園教諭)が増える
認定こども園になることで、新たに先生(保育士・幼稚園教諭)を雇う場合があるので、それに伴い担任やクラス編成などが今までとは変わってくるということもあると思います。
このような周囲の変化が起きることはあると思います。子どもにとっては、大きな変化になるかもしれません。
働いている幼稚園教諭にとってはなにが変わる?
既存の利用者(保護者や児童)にとっては大きな変化はないと書きましたが、働いている幼稚園教諭にとっては大きな変化があります。
先ほど紹介した、認定こども園の種類ですが、以下の種類に分かれています。
- 幼保連携型
- 幼稚園型
- 保育所型
- 地方裁量型
まず、既存の幼稚園が保育所型に移行するケースはないので、そこは省略します。また、地方裁量型に関しても、幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設からの認定こども園への移行になるので、こちらのケースも幼稚園からの移行は基本的に存在しないはずです。
なので、幼稚園は幼保連携型か幼稚園型の認定こども園に移行するケースが多いです。
0〜2歳児が加わる(場合による)
場合によっては、3歳児以上しか受け入れないということもありますが、認定こども園になると0〜2歳児が園児として加わることになります。
幼保連携型、幼稚園型のどちらの場合でもあっても、今働いている幼稚園教諭の方が保育士の資格も有している場合、園の方針などによって、認定こども園に移行した後は0ー2歳児の担任などになる可能性も想定されます。
保育士の資格を持っていない場合は、資格取得を園から推奨されることになると思います。特に幼保連携型の認定こども園に関しては、両方の資格の保有が求められる「保育教諭」という新しい職種で働くことになります。ちなみに資格取得に関しては、幼稚園教諭免許保持者の保育士資格の取得の特例制度があるのでそちらが利用できます。ただし、特例なので期限が定められている点に注意が必要です。
幼稚園教諭としては、今まで担当したことがない年齢の子どもを担任することになると思うので、新たな知識が必要になります。
先生(保育士・幼稚園教諭)が増える
認定こども園になると定員構成などに変更がかかり、新たに先生を雇用する場合が多いです。特に保育士(と幼稚園教諭の両方の資格)を保持している人を雇用し、保育所部分の担当にする場合が多いです。
0〜2歳児を受け入れる場合は、3歳児以降と比較して多くの人員が必要になるので、先生の数も多く増えることになると思います。
給料は増えるかも??
給料に関しては、園ごとによると思うのでなんとも言えませんが、認定こども園になることで補助金制度なども変更があると思うので、増える可能性はあると言えます。
また、保育園で働く保育士が利用できる保育士宿舎借り上げ制度の利用や参加が可能になる場合もあります。研修参加などで、保育士向けの処遇改善を受け取ることができるようになります。この点は大きなメリットと言えるかもしれません。
就業時間・シフト・休暇など働き方が変わる
また、保育所部分の預かり時間が増加するので、幼稚園教諭の働き方も大きく変わることになると思います。いままでは少数の預かり保育がメインだったところが保育所機能を備えることになるので、より長時間の開所時間になります。
幼稚園は4時間の保育時間が基本ですが、保育所部分では、最大11時間の保育時間になります。
幼稚園の頃は、場合によっては、今までは子どもが帰った後は、書類仕事などの時間をとることができていた場合もあると思いますが、それが難しくなるかもしれません。保育園で働く保育士のような働き方に近づくということになると思います。
また、休暇に関しても大きく変わってきます。保育所部分に関しては、基本的に日曜日、祝日、年末年始以外は開所の必要があるので、土曜日も毎週では無いですがシフトによって出勤の必要が出てくるかもしれません。
今まで夏季・冬季・春季などにあった休み期間も、保育所部分は開所していることになるので、その期間中も出勤する必要が出てくる可能性もあります。
このように、就業時間・シフト・休暇などの点で、幼稚園教諭の働き方も大きく変わってくることになると思います。
保育士は幼稚園から移行した認定こども園で働ける?
認定こども園へ移行する幼稚園の求人を狙っている保育士の方も多いと思います。現時点(2020年)では、保育士の資格のみがあれば、認定こども園へ移行する幼稚園でも働くことが可能な場合が多いです。
現時点では、各認定こども園の種類別に必要な資格が以下のように定められています。
<幼保連携型>
保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有。 ただし、施行から10年間は、一定の経過措置あり。<その他の認定こども園>
満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましい。
満3歳未満:保育士資格が必要
将来的には両方の資格の所有が求められることになると思います。保育士の資格を持っていて実務経験がある場合は、幼稚園教諭の免許状を特例で取得できる制度も期間限定であるので、そちらの利用を検討したほうが良いです。
【まとめ】幼稚園の認定こども園への移行が増えているのはなぜ?働き方はどう変わる?
幼稚園の認定こども園への移行が増えているのは、幼稚園の需要減と、保育需要の増加のためです。
認定こども園に移行するのは、幼稚園、国や自治体、保護者にとってもメリットがそれぞれあります。
- 保護者にとっては、保育園と同様の条件で子どもを預けることができる施設が増える
- 国や自治体にとっては保育の待機児童を減らすことができる
- 既存の幼稚園施設にとっては、定員を満たすことができる、また、運営にかかる補助金等も増加する場合がある
幼稚園から認定こども園への移行は、働いている幼稚園教諭にとっては大きな変更になります。
- 0〜2歳児が加わる(場合による)
- 先生(保育士・幼稚園教諭)が増える
- 保育士資格の取得が求められる場合があること
- 給料は増えるかも??
- 就業時間・シフト・休暇など働き方が変わる
- 宿舎借り上げ制度の利用など、メリットが期待できること
幼稚園教諭にとっては良いことばかりとは限りませんが、今後の働き方や就業先選びの参考にしてもらえると幸いです。
よくある質問(FAQ)
- Q認定こども園への移行が加速しているのは、どのような社会的な背景があるからでしょうか?
- A
少子化に伴う幼稚園の定員割れや、共働き世帯の増加による保育ニーズの多様化が大きな理由です。
保護者にとっては長時間保育や休日保育のニーズに応え、国や自治体にとっては待機児童の解消に繋がります。
幼稚園側も財政基盤の安定化や質の高い教育・保育の一体提供を目指すために、認定こども園化を選択します。
特に「子ども・子育て支援新制度」がこの流れを後押ししています。
- Q幼稚園から認定こども園へ移行する際、幼稚園教諭の働き方に具体的にどのような変化があるのか、メリットとデメリットを教えてください。
- A
認定こども園への転換は、幼稚園教諭の働き方に多様な変化をもたらします。
メリットとしては、就職先の多様化や安定した雇用、キャリアアップの機会が挙げられます。
また、乳幼児期からの発達を包括的に支援できる認定こども園教諭の役割にやりがいを感じる方も多いでしょう。
一方、デメリットとしては、認定こども園教諭業務負担の増加や異年齢保育への対応、保育士資格取得幼稚園教諭としての学習負担があります。
従来の勤務体系と異なるシフト制の導入などにより、幼稚園教諭ライフワークバランスの維持が課題となる場合もあります。
- Q認定こども園に移行した後、幼稚園教諭として0歳児からの乳児保育を担当する場合、どのような準備が必要になりますか?
- A
認定こども園では0歳児からの保育も担うため、幼稚園教諭の方は新たな知識やスキルを習得する準備が必要です。
乳児の発達段階に応じた保育方法や、病気・安全管理に関する専門的な知識を学ぶことが大切です。
また、保護者との密なコミュニケーションや連携を深めるスキルも求められます。
研修会への参加や関連書籍での学習を通じて、幼稚園教諭仕事内容変化に対応し、専門性を高める努力をすることが有効です。
- Q認定こども園への移行後、幼稚園教諭の給料や福利厚生はどのように変わる可能性がありますか?
- A
認定こども園へ移行することで、国からの補助金が増えるなど園の財政基盤が安定し、その結果として幼稚園教諭給料認定こども園としての収入が増える可能性があります。
また、保育士が利用できる「保育士宿舎借り上げ制度」や「処遇改善手当」の対象となることで、福利厚生が充実するケースも期待できます。
これらの制度は、幼稚園経営認定こども園移行における大きなメリットの一つとなります。
- Q幼稚園教諭が保育士資格を取得するための「幼保特例制度」について、具体的な内容や利用条件を教えてください。
- A
幼保特例制度は、幼稚園教諭免許を持っている方が保育士資格を取得しやすくするための期間限定の制度です。
通常よりも少ない単位取得で資格が得られる特例措置であり、現職の幼稚園教諭にとっては、幼保連携型認定こども園で働く上で必要な「保育教諭」の資格取得をスムーズにする重要な制度となります。
詳細な利用条件や申請期限は、都道府県や年度によって異なりますので、最新情報を確認することが不可欠です。
- Q認定こども園への移行が進む中で、幼稚園教諭として今後のキャリアを築く上で意識すべき点は何ですか?
- A
認定こども園への転換は、幼稚園教諭のキャリアアップ認定こども園としての機会を広げます。
今後のキャリアを考える上で、まずは自身の興味や専門性を明確にすることが重要です。
乳児保育に力を入れたいのか、リーダーとしての役割を担いたいのかなど、具体的な目標を設定しましょう。
そして、必要な資格(保育士資格など)の取得や、多様な年齢の子どもへの対応スキルを磨く研修への参加を積極的に検討してください。
認定こども園就職先幼稚園教諭としての可能性を広げ、ご自身の「やりがい」を見つけるきっかけにもなります。