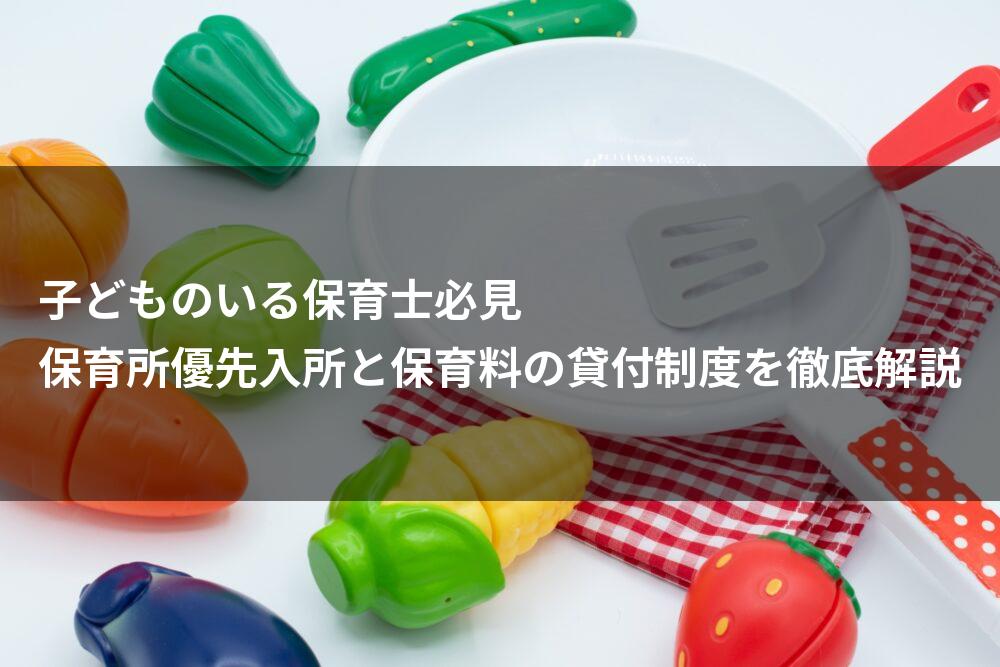| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 | ・未就学児を持つ保育士への保育料の一部を貸付する制度 ・都道府県や政令市が主体で実施、社会福祉協議会が多い ・月額上限27,000円、1年間貸付、週20時間以上の勤務が条件 ・2年間勤務で返済免除 |
| 未就学児をもつ保育士の子供の預かり支援資金 | ・未就学児を持つ保育士へのファミリーサポートセンター等の利用料を貸付する制度 ・東京都の制度では利用料の半額(年123,000円以内)を支援 ・最長2年間、2年間保育士として就労で返還免除 ・保育所の優先入所と合わせて利用可能 |
| 保育士のこどもの保育所への優先入所 | ・政府の「子育て安心プラン」で推進されている制度 ・保育士の社会復帰を促し、待機児童を減らす目的 ・自治体により条件が異なり、加点方式が多い ・勤務地と居住地が異なる場合も加点対象になる可能性 |
| 制度は自分で見つけて自分で申請しないと損! | ・保育士向けの支援制度は多数存在する ・制度は自ら情報収集し、申請する必要がある ・予算に限りがあるため、早めの申請が重要 ・利用できる制度は積極的に活用すべき |
| ブランクがある潜在保育士の方の復帰方法はこちら | ・ブランクのある保育士への支援制度も国や自治体が行っている ・詳細な情報は別途記事を参照 |
| 出産後の求職・転職活動は保育士の転職サイトがおすすめ | ・子育て中の転職活動は負担が大きい ・転職サイトの利用で、スケジュール調整や書類審査の代行が可能 ・子育て中でも転職しやすい環境を提供 |
| まとめ | ・子どものいる保育士向けの制度として、保育料貸付、預かり支援、優先入所を紹介 ・経済的負担を軽減し、安心して働くことを支援 ・情報収集と制度活用で、仕事と育児の両立を促進 ・保育士不足解消に貢献 |
| よくある質問(FAQ) | ・子どもの預かり支援は保育所に入れない場合に利用可能 ・保育料貸付はパートや派遣でも利用できる可能性あり ・優先入所は市区町村への確認が重要 ・貸付制度は2年勤務で返済免除が一般的、要確認 ・優先入所の条件は市区町村ごとに異なる ・制度利用は早めの情報収集と申請が大切 |
- 子どもがいるけど保育士の復帰するか悩む
- なにか支援制度はないのか?
子どものいる保育士さん必見!保育所への優先入所や保育料の貸付制度を活用して、経済的な負担を軽減し、安心して働きませんか?この記事では、子育て中の保育士を支援する制度について詳しく解説します。

保育料の負担が大きくて悩んでいるんだけど、何か良い制度はないのかな?

お子さんのいる保育士さん向けの支援制度が充実しています!ぜひ活用してください。
- 保育所等の保育料の一部貸付
- ベビーサッターなど預かり支援金の貸付
- お子さんの保育所への優先入所
このような支援の目的は、保育士不足のなかでお子さんのいる保育士を適切に援助して、引き続き保育士として就業をしてもらいたいという国の狙いがあります。保育士は働き方の問題点などから、子どもが生まれたのを機に仕事を辞めてしまう方も多いです。
この記事でわかること
- 保育料の一部貸付制度の利用条件と申請方法
- 子どもの預かり支援資金の活用方法
- 保育所への優先入所を実現するためのポイント
未就学児をもつ保育士に対する支援制度については、国、都道府県、市区町村などの自治体の情報を参考にしています
その経験が参考になればと思います
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業は、未就学児(小学校入学前の児童)のいる、すでに保育士として働いている方やこれから保育士として働く方に対して保育料の一部を貸付してくれる制度です。
実施の主体は都道府県、もしくは、政令市であることがほとんどです。そのため例えば神奈川県では横浜市、川崎市、神奈川県でそれぞれ異なる実施主体で制度を実施しています。
基本的には社会福祉法人の「〇〇県社会福祉協議会」という機関が実施している場合が多いですが、自治体によって異なるので注意してください。
また、すべての都道府県で実施されているわけではないようです。加えて、年度ごとに予算も決まっているので予算に達した段階で申し込みを締め切るようです。申込先や実施有無を調べるにはまずは都道府県に確認してみると良いと思います。
貸付の条件はどの機関でもほとんど同様で、基本的には
- 月額上限27,000円
- 貸付期間は1年間
- 保育所での週20時間以上の勤務が条件
- 2年間の勤務で返済免除
というのが一般的なようです。保育所での週20時間以上の勤務なので、正職員はもちろん、パートや派遣などでも対象になると思います。
保育所というのは、認可保育園(小規模保育事業なども含む)が基本になると思いますが、実施の自治体によっては認可外保育施設なども対象になる可能性があるので、確認してみると良いと思います。
ただし、自治体によっては、保育士の就業施設などの条件が微妙に異なる場合があるようです。利用したい方は必ず住まいの実施期間に詳細を確認をしてください。
2年間勤務すると返済が免除になるので、お子さんのいる保育士の方にとってはかなり良い制度だと思います。
未就学児をもつ保育士の子供の預かり支援資金
未就学児をもつ保育士の子供の預かり支援資金は、未就学児のいる、すでに保育士として働いている方やこれから保育士として働く方に対してファミリーサポートセンター事業・ベビーシッター派遣事業等を利用する際の利用料の一部を貸付してくれる制度です。
東京都の制度では以下のような条件になっています。
- 子供の預かり支援事業利用料の半額 (年123,000円以内)
- ファミリーサポートセンター事業・ベビーシッター派遣事業等
- 保育士が勤務する継続した期間(最長2年)
- 2年間保育士として引き続き就労すると、貸付金が返還免除
こちらも、すべての都道府県で実施されているわけではないようです。実施の有無は住んでいる都道府県ごとに確認してください。
加えて、年度ごとに予算も決まっているので予算に達した段階で申し込みを締め切るようです。
なんらかの事情で子どもが保育所に入ることができずに、ファミリーサポートセンター事業・ベビーシッターを利用する場合は補助を受けることができます。
後述していますが、保育士のこどもの優先入所を行なっている自治体もあるので、それを利用できれば保育所への入所の可能性を上げることも可能です。
保育士のこどもの保育所への優先入所
政府の「子育て安心プラン」で「保育士の子どもの預かり支援の推進」として保育士のこどもの保育所への優先入所が推進されています。2018年度から自治体に対して国が保育士等のこどもを優先入所させるように求めています。
保育士等の子どもの保育園等への入園の可能性が大きく高まるような点数付けを行い、可能な限り速やかに入園を確定させることは、
・当該保育士等の勤務する保育園等が早期に当該保育士等の子どもの入園決定を把握して当該保育士の職場への復帰を確定させ、利用定員を増やすことを可能にし、保育の受け入れ枠の増加に大きく寄与するとともに、
・保育士等が妊娠・出産後、円滑に職場復帰できる環境を整えることにより、高い使命感と希望をもって保育の道を選んだ方々が、仕事と家庭の両立を実現しながら、将来にわたって活躍することが可能となり、保育士の処遇の改善にも大きな効果が見込まれることから、待機児童の解消等のために保育人材の確保が必要な市町村においては、このような取組を行うよう努めること。
※ 「保育士等の子どもの優先入所等に係る取扱いについて」より https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/27f4a5b4-53c9-446d-ab3d-7c7055949a26/bd6122e6/20230929_policies_kokoseido_law_tsuuchi_tsuuchi-h24-h29_371.pdf
これは待機児童を減らすための試みで、保育士が社会復帰して働くと、その分を保育所を利用できるこどもが増えることになります。
保育士にはこどもの人数に対して厳格に配置基準が定められているため、保育士一人が働くと待機児童は0歳児なら3人、1~2歳児なら6人、3歳児なら20人、4~5歳児なら30人減ることになります。
待機児童が多いのは1-2歳です。1-2歳の場合、6人 – 保育士の子ども1人で実質的に5人待機児童が減ることになります。保育士だけずるいと考える人もいるかもしれませんが、理にかなった制度です。
認可保育園の入所基準同様、制度実施の主体は市区町村になるので、保育士のこどもが保育所へ優先入所できるかどうかは市区町村次第になります。制度を利用したい未就学児がいる保育士の方は市区町村に詳細を問い合わせて見て下さい。
以下は東京都世田谷区の例です。
区内の保育施設等に月20日以上かつ1日6時間以上勤務している保育士・保育教諭が、申込児の入園が決まらないことにより、産休または育休から復帰できず、区内の保育施設等の運営に深刻な影響がある場合(4月1日入園の二次選考のみ適用)
上記の場合に 調整指数で+2点 の加点となっています。
ちなみに、優先入所の詳細な条件は市区町村ごとに異なります。単に、同一指数の場合に優先的に入所できるということもあれば、ほぼ確実に入所できるくらいの大幅な加点が行われる場合もあります。
さらに、国は「市町村の圏域を超えた利用調整が行われるよう、積極的に各市町村間で協定を結ぶ等の連携・調整を行うこと。」を自治体に求めています。
なので、住んでいる市区町村と保育士として働いている市区町村が異なる場合でも加点を行ってくれる場合もあります。
こちらの制度に関しても、実施しているかどうかは自治体次第になるので、いずれにしても詳細は市区町村に確認してください。
制度は自分で見つけて自分で申請しないと損!
未就学児のいる保育士に限らず、都道府県や自治体で様々な保育士の支援制度が行われています。このような制度は黙っていて利用できるものではありません。これ以外にも、未就学児のいる保育士に対してなにか支援を行なっている自治体などもあるかもしれません。
制度があるかどうかもしっかりと自分自身で情報を入手しないとわからないことが多いです。利用すればお得な制度ほど、実はやり方や申込方法がよくわからないということは多いです。
しっかりと自分で申請に必要な情報や条件を調べて、実施機関に申し込む必要があります。制度によっては年度ごとに予算が決められているものもあるので、早く申請しないと締め切ってしまうということもあります。
せっかく保育士のためにある制度なので、利用できる方は利用しないと損してしまいます。制度は積極的に自分で見つけて自分で申請しましょう。
ブランクがある潜在保育士の方の復帰方法はこちら
ブランクのある潜在保育士に対しても国や自治体が様々な支援を行っています。それについては以下の記事でも別途解説しているので参照してください。
出産後の求職・転職活動は保育士の転職サイトがおすすめ
お子さんがいる保育士の方の転職活動はなかなか難しいです。お子さんのことも考えながら面接にいかないと行けないからです。面接だけではなく、保育園側とのやり取りなども気を使いながら行う必要があります。
保育士の転職サイトを活用すれば、転職にかかる負担をかなり軽減することができます。例えば、保育園との面接のスケジュール調整もコンサルタントが代行してくれます。
場合によっては、書類審査もコンサルタント側が行ってくれるので面接に行くだけで良いという場合もあります。子育て中でもしっかり就職・転職活動をしたいという方におすすめです。
- マイナビ保育士
 |全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです! - ジョブメドレー保育士
 | 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)

※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。
まとめ
この記事では、子どものいる保育士が利用できる保育所への優先入所や保育料の貸付制度について解説しました。
これらの制度を活用することで、経済的な負担を軽減し、安心して働くことができるようになります。
これらの制度は、保育士不足を解消するために国や自治体が提供しているものです。
積極的に情報を集め、自分に合った制度を活用して、仕事と育児の両立を実現しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q子どもの預かり支援資金は、具体的にどのような場合に利用できますか?
- A
お子さんが保育所に入れないなどの事情でファミリーサポートセンターやベビーシッターを利用する際に、その利用料の一部を貸付という形で支援を受けられます。
- Q保育料の貸付制度は、正社員の保育士しか利用できないのでしょうか?
- A
いいえ。保育料の貸付制度は基本的に週20時間以上の勤務が条件のため、パートや派遣などの雇用形態でも利用できる可能性があります。
- Q保育士の子供が保育所へ優先入所できる制度は、どのように申請すれば良いですか?
- A
お住まいの市区町村に詳細を確認することが重要です。申請方法や必要な書類など、手続きについて詳しく教えてもらえます。
- Q貸付制度を利用した場合、2年間勤務すれば必ず返済が免除されるのでしょうか?
- A
はい、2年間保育士として継続して勤務すれば、貸付金の返済が免除されるのが一般的です。ただし、自治体によって条件が異なる場合があるので、必ず確認が必要です。
- Q優先入所の条件は、どの市区町村でも同じですか?
- A
いいえ、優先入所の条件は市区町村によって異なります。加点の幅や対象となる条件などが異なるため、必ずお住まいの地域の情報を確認してください。
- Q制度を利用する際に注意すべき点はありますか?
- A
制度は年度ごとに予算が決められている場合があり、予算に達すると受付が終了することがあります。早めに情報を集め、申請することが大切です。