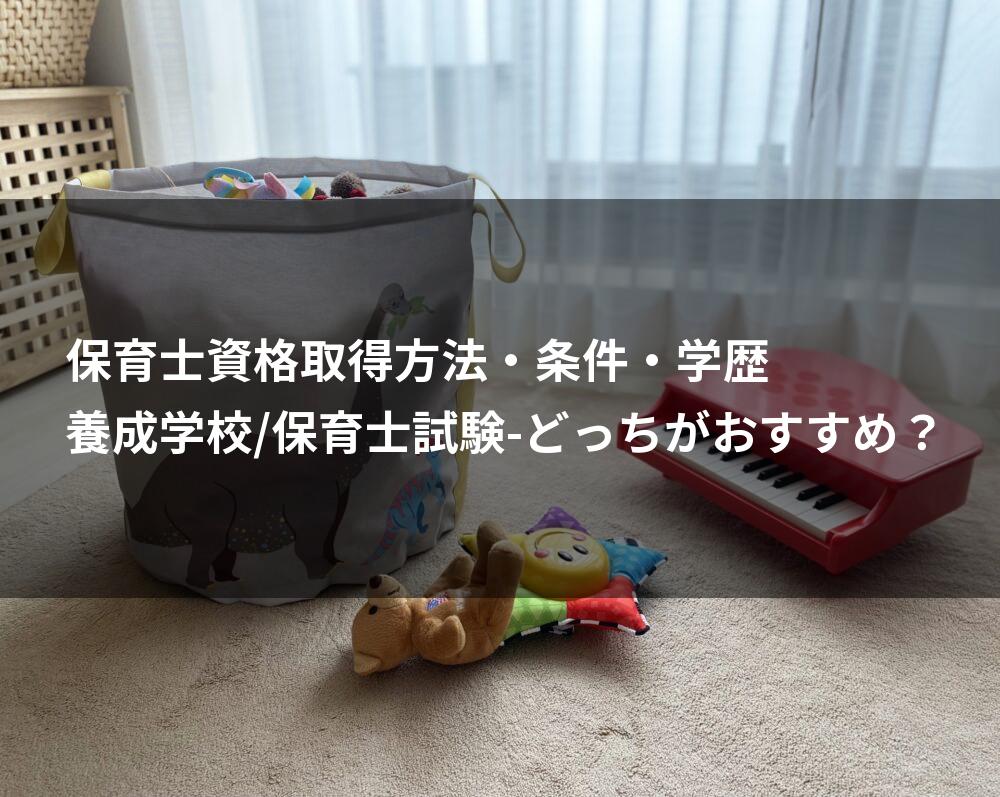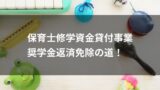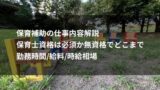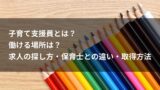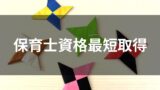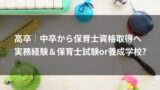| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育士資格の取得方法一覧 | ・保育士資格取得には養成学校への通学と保育士試験の受験の2つの方法がある ・それぞれの方法について紹介 |
| 保育士資格の取得方法① 養成学校に通う | ・厚生労働省指定の養成学校で指定科目を履修すると卒業時に資格取得可能 ・公立保育園の保育士を目指す課程や幼稚園教諭の資格も取得できるコースもある ・夜間コースを開講している学校もあり、社会人も通学可能 |
| 保育士資格の取得方法② 保育士試験を受ける | ・保育士試験は厚生労働省管轄の資格試験で、合格すれば資格取得可能 ・基本的に年2回実施され、費用は受験料のみで済む場合がある ・受験には要件があり、学歴や実務経験が求められる |
| 養成学校と保育士試験での取得どちらがおすすめか | ・社会人には保育士試験、高校卒業後の進路に迷っている場合は大学進学も選択肢 ・絶対に保育士として働きたい場合は養成所がおすすめ ・自身の状況を考慮して最適な方法を選択することが重要 |
| そもそもなぜ保育士の資格が必要? | ・正しい知識を持った人が保育することで、事故防止や保育の質の確保につながるため ・保育士は子どもの命を預かる責任があり、安全な保育を行う必要がある ・認可保育園や認可外保育園で保育者として働くには、基本的に資格が必要 |
| 無資格からでも実務経験を積むというのも選択肢の一つ | ・保育士の配置基準を上回る人員については無資格者でも保育業務に従事可能 ・保育補助として経験を積みながら、保育士試験の実務要件を満たすことも可能 ・保育園での業務経験は試験対策にも役立つ |
| まずは子育て支援員の資格を取得してみるというのも選択肢の一つ | ・子育て支援員は保育関連業務に就業する人のためにできた資格 ・各自治体実施の研修を受講することで資格取得可能 ・無資格の場合よりも就業できる保育施設の選択肢が広がる |
| 【まとめ】保育士資格の取得方法を解説。養成学校と保育士試験での取得どちらがおすすめか? | ・保育士資格の取得方法は養成学校への通学と保育士試験の受験の2種類がある ・養成学校は費用がかかるが着実に資格取得を目指せる ・保育士試験は受験要件があり試験対策が必要 |
| よくある質問(FAQ) | ・保育士資格は学歴がなくても、実務経験があれば取得可能 ・働きながら資格取得も可能で、夜間コースを開講している養成学校もある ・資格取得費用は取得方法で異なり、養成学校は高額だが貸付制度も有り |
- 保育士資格はどうやって取れる?
- 養成学校と保育士試験での取得どちらがおすすめ?
保育士資格の取得を考えているけど、どうすればいいかわからない方へ。
養成学校に通うか、保育士試験を受けるか迷いますよね。
この記事では、それぞれの取得方法について詳しく解説します。
ご自身の状況に合った方法を見つけて、保育士への第一歩を踏み出してみませんか。

自分にはどんな取得方法があっているんだろう?

養成学校と保育士試験、それぞれのメリット・デメリットを知って、自分に合った方法を見つけましょう!
この記事でわかることはこちらです。
私は保育園、幼稚園、認定こども園で勤務した経験があります
その経験が参考になればと思います
保育士資格の取得方法一覧
保育士の資格を取得するのには大きく以下の2つの方法があります。
- 保育士資格の取得方法① 養成学校に通う
- 保育士資格の取得方法② 保育士試験を受ける
このそれぞれの方法について紹介します。
保育士資格の取得方法① 養成学校に通う
厚生労働省が指定する養成学校(大学・短大・専門学校)で2~4年間、指定の科目を履修することで、卒業時に保育士資格を得ることができます。
保育士の資格を取得しつつ、公務員である公立の保育園の保育士への就業を目指す課程などがある専門学校などもあります。また、保育士の資格と合わせて幼稚園教諭の資格なども取得できるようなコースを設定している学校もあります。
公立保育園の保育士は公務員試験の受験も必要なため、別途試験勉強が必要になりますが、資格取得の勉強と並行して行うことができます。
また、夜間主コースを開講し、社会人が仕事をしながら通える養成学校もあります。
基本的に必要な単位を取得して卒業すれば保育士資格を取得することができます。
養成学校の費用目安は?
保育士の専門学校などであれば費用は2年間で200万円程度が目安となります。大学などに通う場合は、4年間で400万円程度の費用がかかります。
これ以外にも、教材費や交通費などの費用がかかります。養成学校に通うために一人暮らしなどが必要な場合はさらに費用が必要になります。
| 養成学校種類 | 費用 |
|---|---|
| 専門学校(2年制) | 200万円 |
| 大学(4年制) | 400万円 |
専門学校は、後述する保育士試験と比べて費用は高くなりますが、しっかりと単位を取得することで、より確実に保育士資格を取得できます。
保育士の修学費用の貸付制度有り
養成学校の費用面がどうしても難しいという方向けに、費用面の負担を減らすことができる方法もあります。
保育士資格を取得するために指定の養成学校に通う学生向けに各都道府県では保育士修学資金貸付事業を行っています。
修学に必要な費用の貸付を受けることができます。卒業後保育士として保育施設に就業して勤務を続けると返済免除などの規定もあります。
卒業後の保育施設への継続勤務(3〜5年程度)が条件となっている場合が多く、保育士として勤務しない場合は、通常の奨学金と同様に返済する必要があります。
詳細条件などや定員などは実施している団体によって異なるので注意が必要です。保育士向けの修学費用の貸付制度に関しては以下の記事でも紹介しています。
保育士資格の取得方法② 保育士試験を受ける
2つ目の保育士の資格の取得方法は「保育士試験」を受けることです。保育士試験は、厚生労働省が管轄している保育士資格を取得するための試験になります。
養成所に通う場合と違って、試験に合格すれば保育士の資格を取得することができます。試験は基本的に年2回実施されています。
そのため、最短で次回の試験に合格すれば保育士資格を取得できます。費用は受験料のみで済むため、養成学校に通うよりも安価になる場合があります。受験料は約1万2千円です。
ただし、不合格の場合は毎回受験料がかかるため、費用がかさむ点に注意が必要です。
保育士試験の概要に関しての詳細は以下の記事でも解説しています。
保育士試験には受験要件がある
注意が必要なのは、保育士試験は誰でも受けることができる試験ではなく、受験には受験要件というものがあります。
受験要件は以下のようになっています。
- 大学、短期大学、専門学校を卒業している
- 高校卒業で、2年以上かつ2880時間以上の保育関連の実務経験
- 中学卒業で、5年以上かつ7200時間以上の保育関連の実務経験
- ほか、いくつかの条件あり
受験要件の詳細は、以下の記事をご参照ください。
受験要件を満たしていない方の場合は、まずは要件を満たす必要があり、保育関連の実務経験が必要になってくるので、少しハードルは高くなってしまいます。
特定の条件で保育士試験の科目の免除も可能
以下の条件に該当する方の場合は、保育士試験の科目の免除も可能になっています。
- 幼稚園教諭の資格を持っている
- 幼稚園教諭の資格を持っていて、幼稚園や保育関連施設での実務経験(3年以上かつ4320時間以上)がある
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格を持っている
幼稚園教諭の資格を持っている方の場合、「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」の科目がそれぞれ免除されます。
幼稚園教諭の資格を持っていて、幼稚園での実務経験(3年以上かつ4320時間以上)もある方の場合は、保育士資格試験の筆記試験の「保育の心理学」「教育原理」「保育実習理論」と「実技試験」が免除されます。
さらに、大学・短大・専門学校等で特例教科目(4科目・8単位)「福祉と養護」「子ども家庭支援論」「保健と食と栄養」「乳児保育」を取得すれば、残りの科目についても免除されます。
該当者向けに特例教科目のみを履修可能な養成施設もあるので、これを利用すると保育士試験の全科目が免除されます。
保育士試験の科目の免除については「幼稚園教諭の資格を持っている」「幼稚園教諭の資格を持っていて、幼稚園での実務経験もある」方は以下の記事を参照してみてください。
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格を持っている方は、免除申請により「社会的養護」・「児童家庭福祉」・「社会福祉」の科目が免除になります。
養成学校と保育士試験での取得どちらがおすすめか
これから保育士の資格の取得を考えている方にどちらの方法での取得がおすすめかという点を解説します。
結論から言うと、それぞれの状況によって、おすすめする方法は変わってくると思います。一概にこれがおすすめと言えるものはありません。
すでに社会人の方で、就業しながら保育士の資格の取得を考えている方には、保育士試験での取得がおすすめです。専門学校などの養成所は夜間での通学になると、選択肢も限られますし、費用も高額になってしまうためです。
高校卒業後の進路に迷っている場合、専門学校などの養成所への進学は他の職種への就業の選択肢を狭める可能性があります。大学に進学し、卒業後に保育士試験を受けて資格を取得することも可能です。
逆に、絶対に保育士として働きたいという方は、養成所に行くことで、確実に資格を取得できて、保育士の仲間もたくさんできると思います。
自分自身の状況を考慮して、どうするべきかがベストな選択になるのかをしっかりと考えることが大切だと思います。
そもそもなぜ保育士の資格が必要?
保育士の資格が必要な理由は、保育に関して正しい知識を持った人が保育園で働くことで、保育園での事故防止や保育の質の確保につながるためです。
保育士は子どもの命を預かる責任があるため、安全に保育を行うために様々な観点から日々勤務しています。
そして、認可保育園や認可外保育園で保育者として働くためには、基本的には保育士の資格が必要になります。国は、保育児童の人数に対しての必要な保育士の人数を基準を定めています。
認可保育園も、保育士資格をもっている人を保育者として雇用することでこの基準をクリアしています。
昨今、保育の需要が増加しており、保育士資格保持者の需要も高まっています。
無資格からでも実務経験を積むというのも選択肢の一つ
前述の通り、認可保育園で保育者として働くには基本的に保育士資格が必要ですが、資格がなくても保育園で働くことが可能です。
保育園には保育士の配置基準があり、それを上回る人員については無資格者でも保育業務に従事できます。
例えば、0歳児3人に対して1人以上の保育士が配置されている場合、追加で無資格者を補助として配置できます。
このような立場で働く人を保育補助と呼び、無資格でも働ける保育園は少なくありません。
保育補助として経験を積みながら、保育士試験の実務要件を満たしたり、働きながら保育士試験の合格を目指すことも可能です。
保育園での業務を経験しながら試験に臨むことで、保育士資格取得後すぐに働き始めるよりもリスクを抑えることができます。
まずは子育て支援員の資格を取得してみるというのも選択肢の一つ
子育て支援員は、平成27年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」の中で、保育関連の業務に就業する人のために出来た新しい資格になります。
各自治体が実施する研修を受講することで「子育て支援員研修修了証明書」の交付を受けることができます
国家資格ではありませんが、研修を修了することで、無資格の場合よりも就業できる保育施設の選択肢が広がります。
子育て支援員に関しての詳細は以下の記事を参照してください。
【まとめ】保育士資格の取得方法を解説。養成学校と保育士試験での取得どちらがおすすめか?
この記事では、保育士資格の取得方法として、養成学校に通う方法と保育士試験を受ける方法の2つを紹介しました。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合わせて選択することが大切です。

結局、自分にはどの方法があっているのかな?

ご自身の状況を整理して、どちらの方法が最適かじっくり検討してみましょう。
まずは、ご自身の学歴やライフスタイルを考慮し、それぞれの方法について詳しく調べてみることをおすすめします。
保育士資格の取得方法は以下の大きく2つの方法があります。
- 保育士資格の取得方法① 養成学校に通う
- 保育士資格の取得方法② 保育士試験を受ける
養成所は最低2年間通う必要があり費用もかかってきますが、しっかりと履修をすれば保育士の資格を取得できます。
保育士試験での資格取得は年2回のチャンスで、きちんとして試験対策として勉強が必要です。
幼稚園教諭の免許保持者や社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格保持者には保育士試験の科目免除もあります。
養成学校と保育士試験での取得どちらがおすすめかというのに一概に答えはないので、自分自身の状況を考慮して、どうするべきかがベストな選択になるのかをしっかりと考えることが大切だと思います。
保育士試験については、以下の記事も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士資格は、学歴がなくても取得できますか?
- A
はい、保育士試験には学歴以外にも受験資格があります。
高校卒業後、2年以上かつ2880時間以上の保育関連の実務経験があれば、受験資格を満たします。
中学卒業の場合は、5年以上かつ7200時間以上の実務経験が必要です。
- Q働きながら保育士資格を取得できますか?
- A
はい、働きながら保育士資格の取得を目指すことは可能です。
保育士試験は年2回実施されているため、仕事と両立しながら試験勉強を進めることができます。
また、夜間主コースを開講している養成学校もあります。
- Q保育士の資格取得には、どのくらいの費用がかかりますか?
- A
保育士の資格取得にかかる費用は、取得方法によって大きく異なります。
養成学校に通う場合は、専門学校で2年間で200万円程度、大学で4年間で400万円程度が目安となります。
保育士試験の場合は、受験料のみで約1万2千円です。
ただし、不合格の場合は毎回受験料がかかります。
- Q養成学校に通う場合、費用を抑える方法はありますか?
- A
はい、養成学校の費用を抑える方法として、各都道府県で実施されている保育士修学資金貸付事業を利用する方法があります。
修学に必要な費用の貸付を受けることができ、卒業後、保育士として一定期間勤務すると返済が免除される場合があります。
- Q幼稚園教諭免許を持っていますが、保育士資格を取得できますか?
- A
はい、幼稚園教諭の免許をお持ちの場合、保育士試験の一部科目が免除される制度があります。
「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」の科目が免除されます。
さらに、幼稚園での実務経験があれば、筆記試験の「保育の心理学」「教育原理」「保育実習理論」も免除されます。
- Q保育士試験の難易度や合格率はどれくらいですか?
- A
保育士試験の難易度や合格率は年度によって変動しますが、一般的には合格率が20%前後の難関試験と言われています。
筆記試験と実技試験があり、それぞれ対策が必要です。
過去問や対策講座などを活用して、効率的に学習を進めましょう。