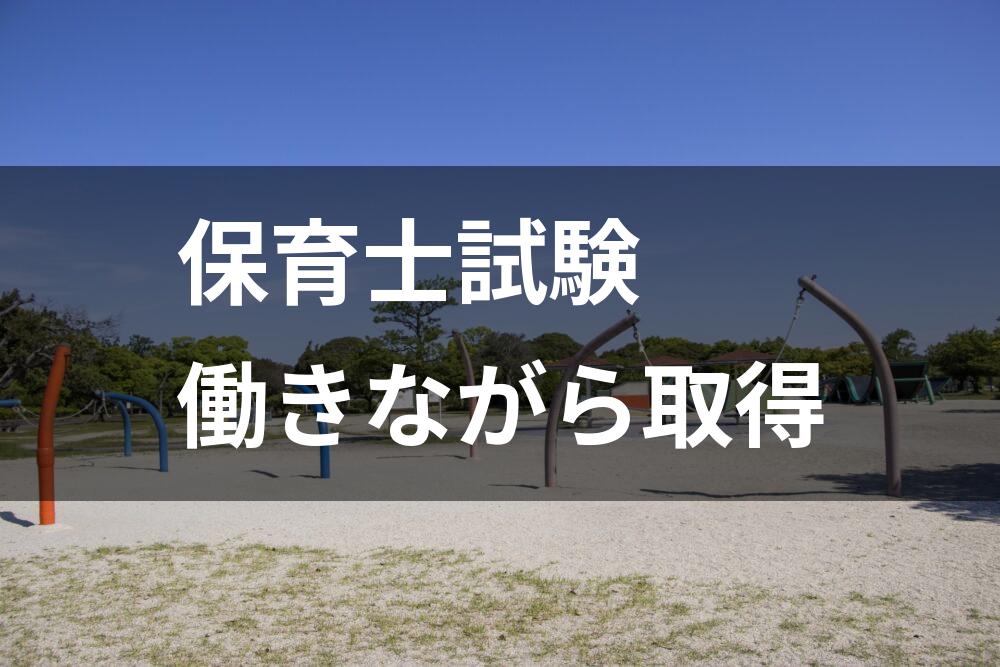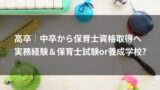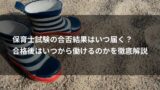| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育士試験とは? | ・保育士になるための国家資格。詳細は専門記事を参照 |
| 保育士試験の合格率は? | ・毎年20%台後半の合格率で推移 ・実技試験まで含めた最終的な数字 ・難易度は低くない国家資格 |
| 保育士試験の筆記試験の概要 | ・全9科目のマークシート方式で実施 ・各科目5択問題、教育原理・社会的養護以外は20問 ・全科目で6割以上の得点が必要 ・土日の2日間で行う |
| 保育士試験の筆記試験のポイント | ・正誤組み合わせ問題が多く、まんべんない知識が必要 ・科目別の合格判定のため、得意科目でのカバーは不可 ・一度合格した科目は3年間有効 |
| 保育士試験の実技試験の概要 | ・3分野(音楽、造形、言語)から2分野を選択 ・音楽は弾き歌い、造形は絵画、言語はお話 |
| 保育士試験の実技試験のポイント | ・音楽選択ではピアノ以外にギターやアコーディオンも選択可能 ・楽譜の持ち込みも許可されている |
| 保育士試験の実技試験の対策方法 | ・合格率が高いため、筆記試験後からの対策でも十分 ・ピアノが苦手なら他の分野を選択 ・プロ級の技術より、保育士として子どもを意識した表現が評価の鍵 |
| 主な保育士試験の対策勉強方法 | ・独学は費用を抑え、自分のペースで学習可能 ・通信講座は体系的なカリキュラムやサポート、最新情報を提供 |
| 合格までの目安の期間 | ・半年から3年程度と個人差が大きい ・年2回の受験機会があり、予備知識や学習時間により期間は変動 ・本気で取り組めば半年での合格も可能 |
| 保育士試験の注意点 | ・受験チャンスは年2回(地域限定試験含め年3回) ・受験料は毎回12,950円と高額 ・教育原理と社会的養護は同時に合格が必須な「ニコイチ科目」 ・一度合格した科目も3年以内に全科目合格が必須 ・地域限定試験では実技の代わりに研修の場合もある |
| 働きながらも保育士試験の対策は可能? | ・合格率は低いものの、働きながら最短半年で合格する人もいる ・予備知識がなくても合格は可能 ・個人の努力や生活スタイル次第で十分に合格を目指せる |
| 保育士試験、資格取得関連の記事 | ・関連情報を提供するウェブ記事のリスト |
| まとめ | ・国家資格である保育士試験は難易度が高いが、計画的な勉強と対策で働きながらの合格が可能 ・筆記9科目・実技2分野の満遍ない知識が重要 ・独学や通信講座など勉強方法が選択可能 ・年複数回の受験チャンスがあり、科目合格は3年間有効 |
| よくある質問(FAQ) | ・働きながらの学習時間管理 通勤・昼休みなどのスキマ時間を活用し、週末や夜にまとまった学習時間を確保。無理なく継続可能なスケジュール作成が重要 ・独学と通信講座の比較(働きながら) 独学は低コストでマイペースに学習。通信講座は体系的なサポートや最新情報を提供。自己管理能力や予算に合わせて選択、計画が苦手なら通信講座が有効 ・短期間合格の勉強計画 綿密な計画と過去問分析が不可欠。試験日から逆算し各科目の時間を割り当て、頻出分野に注力。全科目6割以上の得点が必要なため、バランス良い学習が重要 ・筆記試験で特に難易度が高い科目 全9科目6割以上が必要。特に「教育原理」「社会的養護」は同時に合格が必須な「ニコイチ」科目。全般的に暗記量と範囲が広く、過去問活用で満遍ない対策が重要 ・働きながらのモチベーション維持 小さな目標設定で達成感を積み重ね、モチベーションを維持。同じ目標を持つ人々との情報交換も有効。合格後の自身の姿を具体的にイメージすることも重要 ・保育士試験の費用と費用を抑える方法 受験料は毎回12,950円かかる。費用を抑えるには、少ない回数での合格を目指し、独学で市販教材を活用。自身の学習スタイルに合った効率的な方法を選ぶ |
- 保育士試験の勉強・対策方法を知りたい
- 働きながらの取得は可能?
「保育士資格を取得したいけれど、働きながらの資格取得は本当に可能なのだろうか」と、多くの方が不安を感じているかもしれません。
この記事では、保育士試験の具体的な勉強方法や対策はもちろん、働きながらでも合格を目指せる道筋を詳しく解説します。

仕事と勉強を両立して、本当に保育士試験に合格できるのでしょうか?

努力と計画次第で、働きながらでも保育士資格の取得は十分に可能です。
その経験が参考になればと思います
保育士試験とは?
そもそも保育士試験ってなに?って方はまずは以下の記事を御覧ください
保育士試験の合格率は?
保育士試験の合格率は毎年20%台後半程度となっています。この合格率というのは実技試験までの数字になります。
つまり、保育士試験を受けて最終的に保育士資格を得ることができるのが毎回全体の 20%程度 ということになります。
同様に国家資格である公認会計士の2019年の試験の合格率が11.1%であることを考えると、なかなか難易度が高いと想像ができます。
もちろん受験が可能な前提条件や受験をする対象者が全く違うので一概に比較することは出来ませんが、それだけ難易度は低くないということがわかります。
保育士試験の筆記試験の概要
保育士試験の筆記試験は五択問題です。出題範囲は以下になります。
- 保育原理
- 教育原理
- 社会的養護
- 児童家庭福祉
- 社会福祉
- 保育の心理学
- 子どもの保健
- 子どもの食と栄養
- 保育実習理論
それぞれ20問(教育原理、社会的養護は10問)のマークシート方式の試験になります。
実技試験に進むには全科目に合格する必要があります。 合格基準はそれぞれの科目で6割以上の得点になります。
全体で6割の得点ではなく、それぞれの科目で6割以上の得点で合格する必要があります。つまり20問の科目では12問に正解すれば良いです。10問の科目は6問です。
基本的には土曜日と日曜日の二日間に渡って試験が実施されます。
| 筆記試験 | 詳細 |
|---|---|
| 試験内容 | マークシート方式 |
| 選択肢 | 5択 |
| 科目数 | 9科目 |
| 設問数 | 20問(教育原理、社会的養護は10問) |
| 合格点 | 6割 |
| 試験時間 | 各1時間(教育原理、社会的養護は30分) |
| 試験日程 | 2日間 |
過去の問題と回答例に関しては、こちらの記事をご確認ください。
保育士試験の筆記試験のポイント
保育士試験の筆記試験は5択のマークシート方式ではありますが、勘で当てられるような問題になっていないことが多いです。
空欄に当てはまる適切な語句を選ぶというようなものではなく、5つの文章が並べられて、そのそれぞれの正誤の組み合わせを選ぶという問題が多いです。
問1 次の文は、保育所における保育に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 保育所は、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。
B 保育における養護とは、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために主として看護師が行う治療や処置である。
C 保育における養護とは、そのための一定の時間を設けて、そこで行う援助や関わりである。
D 保育における養護とは、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために保護者に対する指導を行うことである。
E 保育所では、保育全体を通じて、養護に関するねらいや内容を踏まえた保育が展開されなければならない。(組み合わせ)
A B C D E
1 ○ ○ ○ × ○
2 ○ ○ × ○ ×
3 ○ × × × ○
4 × ○ × × ×
5 × × ○ ○ ○
例として上記のような問題になります。このような問題だと、少なくとも5個のうち3つ以上を正しい知識を知っておかないと正解を選択することが難しいです。
そのため、まんべんなく科目全体の知識を得ておく必要があります。
しかも、科目ごとの合格不合格になるので、得意な特定の分野で他の苦手な分野をカバーするということもできません。
そのため、まんべんなくすべての分野に関しての知識を得ておく必要があります。
ただ、後述していますが、科目毎の合格は3年間有効なので、もし「もう既に試験に申し込んだけど特定の分野の勉強が間に合わない」という場合は、あえて一部の科目を捨てて次回以降に合格を目指すという戦法も有りかと思います。
受験料はかかってしまいますが、中途半端に不合格になってしまうと次回の試験でもすべての科目を勉強し直さないといけなくなってしまいます。
保育士試験の実技試験の概要
実技試験は、3分野のうち2分野を選択します。
- 音楽(弾き歌い)・・・幼児に歌って聴かせることを想定して、課題曲の両方を弾き歌いする。
- 造形(絵画)・・・保育の一場面を絵画で表現する。
- 言語(口演・素話)・・・子どもが集中して聴けるようなお話を行う。
過去の試験内容に関しては全国保育士要請協議会の過去問のページに記載されています。
保育士試験の実技試験のポイント
保育士試験の実技試験のポイントです。
音楽はピアノでなくても良い
ピアノ、ギター、アコーディオンのいずれかで演奏すればよいとなっているので、それらのうちのどれかを選択することになります。
ピアノ以外の楽器はご自身での持ち込みになります。楽譜の持ち込みも可能となっています。
保育士試験の実技試験の対策方法
保育士試験の実技試験の合格率は80%台後半から90%台前半と高くなっているので、対策は合格後からでも問題ないです。
ただ、ピアノに関しては未経験の状態からすぐに弾けるようにするのは難しいと思うので、その場合は事前に練習をしておくか、もしくは、ピアノ以外の分野を選択するのがおすすめです。
保育士試験の受験申請の手引に求められる力というのが分野ごとに記載されています。
音楽(弾き歌い)
求められる力:保育士として必要な歌、伴奏の技術、リズムなど、総合的に豊かな表現ができること。
造形(絵画)
求められる力:保育の状況をイメージした造形表現(情景・人物の描写や色使いなど)ができること。
言語(口演・素話)
求められる力:保育士として必要な基本的な声の出し方、表現上の技術、幼児に対する話し方ができること。
採点基準はこれらの部分になります。あくまでも上記の保育士として任せられる人材であるかどうかが基準になるので、プロ並みの技術は全く求められません。
むしろ、どんなに高い技術があってもその点ができていないと合格にはならない場合があります。
大切なことは子どもたちをしっかりと想定して実技が出来ているかという点です。
主な保育士試験の対策勉強方法
独学
書籍やアプリなどを利用した独学での勉強方法です。保育士試験は独学でも十分合格が可能です。
受験範囲が広いためそれなりに時間はかかります。
通信講座
通信講座を利用しての勉強方法は、独学に不安がある方におすすめです。法改正などの最新情報もキャッチすることができます。
費用は少しかかってしまいますが、確実に試験対策を進めることができます。
合格までの目安の期間
最短で半年で合格する人もいれば3年間で少しずつ合格科目を増やしていって合格する方もいます。保育士の受験機会は基本的に年2回なので、受験チャンスは割と多いです。
こればかりは、予備知識や毎日どれくらいの勉強時間をかけられるかによって大きく合格までの期間が変わってきます。
ただ一つ言えることはやる気を出して本気を出せば半年での合格も不可能ではないです。
保育士試験の注意点
最後に保育士試験の注意点について紹介します。
チャンスは年2回、もしくは3回
保育士試験は基本的には年に2回行われることが通例になっています。なので、受験のチャンスは年2回です。もちろん、受験回数分受験料がかかってくるのでむやみに受験すれば良いというわけではありません。
また、神奈川県のように国家戦略特区地域限定保育士試験が行われている場合は、受験のチャンスを一回増やすことが可能です。
ただし、国家戦略特区地域限定保育士試験に合格した場合は、最初の3年間はその地域でしか保育士として働くことができません。
受験料はなかなか高額
受験のチャンスは年2回あると書きましたが、受験料はなかなか高額です。
保育士試験の受験料は 12,950円 です。内訳は受験手数料12,700円+受験申請の手引き郵送料250円となります。
他の国家資格と比較しても特別に高くというわけでは有りませんが、結構な負担となる金額だと言えます。
受験料がもう少し安ければとりあえず受けてみて感覚を掴むなんてこともできますが、それなりの金額がかかるので、しっかりと対策を講じて合格見込みがある程度できてから挑む必要があります。
教育原理および社会的養護はニコイチの科目
教育原理および社会的養護はニコイチの科目です。2つで一つということです。
「教育原理」と「社会的養護」はそれぞれで試験が行われますが、合格は2つの科目同時にする必要があります。
つまり、それぞれ10問中6問以上正解する必要があります。例えば、前期の試験で「教育原理」に合格して、後期の試験で「社会的養護」に合格するという、合格の仕方は出来ません。
同じ試験で両方に合格しないと合格という扱いになりません。
3年以内に全科目合格する必要がある
保育士試験自体は何回でも受けることができますが、一度合格した科目は3年間有効になります。
つまり、3年間で全科目に合格しない場合、3年前に合格した科目は再受験が必要になります。
逆に言えば3年間はキープしておくことができますが、受験料(12,950円)は毎回かかるので、注意が必要な点になります。
地域限定試験では実技試験の代わりに研修の場合も
これはそれぞれの特区によって異なりますが、神奈川県の場合は、実技試験ではなく、研修が行われています。
研修の場合は、規定の研修を受講すると合格という形になります。例えば、神奈川県の2019年の保育実技講習会は、合計27時間に及ぶ研修で約5日に渡ります。
保育実技研修を行うことで、より実務的な保育の知識を得ることが可能になるというメリットもあります。また、実技試験が苦手という方にとっては、講習会を受講すれば必ず合格できるというメリットもあります。
国家戦略特区地域限定保育士試験に関しては以下の記事を参照してください。
働きながらも保育士試験の対策は可能?
冒頭に書いたとおり合格率は20%程度なので、決して簡単な試験というわけではありません。
ただ、保育士試験の合格者の話を聞いていると、最短で次回の試験(2ヶ月から半年後の試験)に合格しているケースもあります。なかにはもちろん働きながら受験している人もいます。
保育士試験の内容は今までの生活や仕事、経験で得られる予備知識はあまり多くない(例えば子育て経験があったとしても得られるという予備知識は多くはない)です。
なので、最短で合格できた = もともと知識があった というわけでもなく、最短でも合格できる人もいるということがわかります。
あくまでも試験なので、対策には得意不得意があるので、一概に誰でも働きながら合格できるとは言えませんが、その人の生活スタイルや努力によっては十分働きながらでも合格が可能な試験だと思います。
保育士試験、資格取得関連の記事
まとめ
この記事では、保育士試験の具体的な勉強方法や対策、そして働きながらでも合格を目指せる道筋についてお伝えしました。
保育士試験の合格は決して簡単な道のりではありませんが、適切な勉強方法と計画によって、働きながらでも夢を叶えることは十分可能です。
ぜひこの記事で得た知識を活かし、あなたのペースで資格取得に挑戦してみてください。
よくある質問(FAQ)
- Q働きながら保育士試験の勉強をする際、具体的にどのように時間管理をすれば効率的ですか?
- A
働きながらの勉強で最も大切なのは、毎日のスキマ時間を有効に活用することです。
通勤電車の中や昼休み、家事の合間など、15分から30分程度の細切れの時間を過去問活用や暗記学習に充てましょう。
加えて、週末や平日の夜には、まとめて1時間から3時間の勉強計画を立て、集中的に机に向かう時間を確保することが効率的な学習には欠かせません。
無理なく両立できるよう、事前に学習スケジュールを立てて、継続可能なペースを維持することが重要です。
- Q独学と通信講座、働きながら保育士試験の取得を目指すならどちらがおすすめですか?
- A
働きながら保育士試験の取得を目指す場合、独学と通信講座にはそれぞれメリットがあります。
独学は費用を抑え、自分のペースで学習を進められる利点があります。
一方、通信講座(ユーキャン、キャリカレ、たのまななど)は、体系的なカリキュラムや疑問点のサポート体制が充実しており、法改正などの最新情報も提供されます。
ご自身の自己管理能力や予算、学習スタイルに合わせて選ぶことが大切です。
特に、計画を立てるのが苦手な方や、質問できる環境が欲しい方には通信講座が効率的でおすすめです。
- Q短期間で保育士試験の合格を目指すには、どのような勉強計画を立てるのが効果的ですか?
- A
短期合格を目指すには、まず勉強計画を綿密に立てることが重要です。
試験日から逆算し、各科目にかけられる時間を具体的に割り出します。
過去問活用を軸に、出題傾向を把握し、頻出分野に重点を置いて学習を進めるのが良いでしょう。
特に筆記試験の9科目すべてで6割以上の正答が必要なので、得意科目で苦手科目をカバーできないことを理解し、科目別対策をバランス良く行うことが一発合格への近道です。
また、疲労を避けるため適度な休憩を学習スケジュールに組み込みましょう。
- Q保育士試験の筆記試験で、特に難易度が高い科目や対策が難しい科目はありますか?
- A
保育士試験の筆記試験は全9科目あり、すべて6割以上の得点が必要です。
特に「教育原理」と「社会的養護」は、それぞれ10問中6問以上の正答が必要なうえ、この2科目は同じ試験で同時に合格しなければならない「ニコイチ」科目であるため、集中した対策方法が求められます。
しかし、全体的に難易度が高いと感じられるのは、暗記量が多いことや、出題範囲の広さにあるからです。
特定の科目に偏らず、過去問活用を通じて全科目の出題傾向を把握し、まんべんなく効率的な学習を進めることが重要です。
- Q働きながら勉強する中で、モチベーション維持の具体的な方法はありますか?
- A
働きながらの勉強方法は、モチベーション維持が重要になります。
小さな目標を設定し、それを達成するたびに自分を褒めることで、達成感を積み重ねましょう。
例えば、「今日はこの章を終わらせる」「過去問を10問解く」といった具体的な目標が良いです。
また、同じ目標を持つ社会人や主婦の方々と情報交換ができるオンラインコミュニティやSNSを活用するのも有効な対策方法です。
合格後の保育士としての自分の姿を具体的にイメージし、目標を明確に持つこともモチベーション維持に繋がります。
- Q保育士試験の費用はどのくらいかかりますか?また、費用を抑える方法はありますか?
- A
保育士試験の受験料は、通常12,950円(受験手数料12,700円+受験申請の手引き郵送料250円)です。
これは毎回かかる費用ですので、合格までの回数が増えるほど総額は高くなります。
費用を抑えるには、できるだけ少ない回数での合格を目指すことが一番です。
具体的には、独学で市販のテキストや過去問活用を主軸にすることで、通信講座と比較して教材費を抑えることが可能です。
ただし、サポート面での費用対効果を考えると、自分の学習スタイルや必要なサポートレベルに合わせて、最適な勉強方法を選ぶことが結果的に効率的となり、総費用の抑制にも繋がるでしょう。