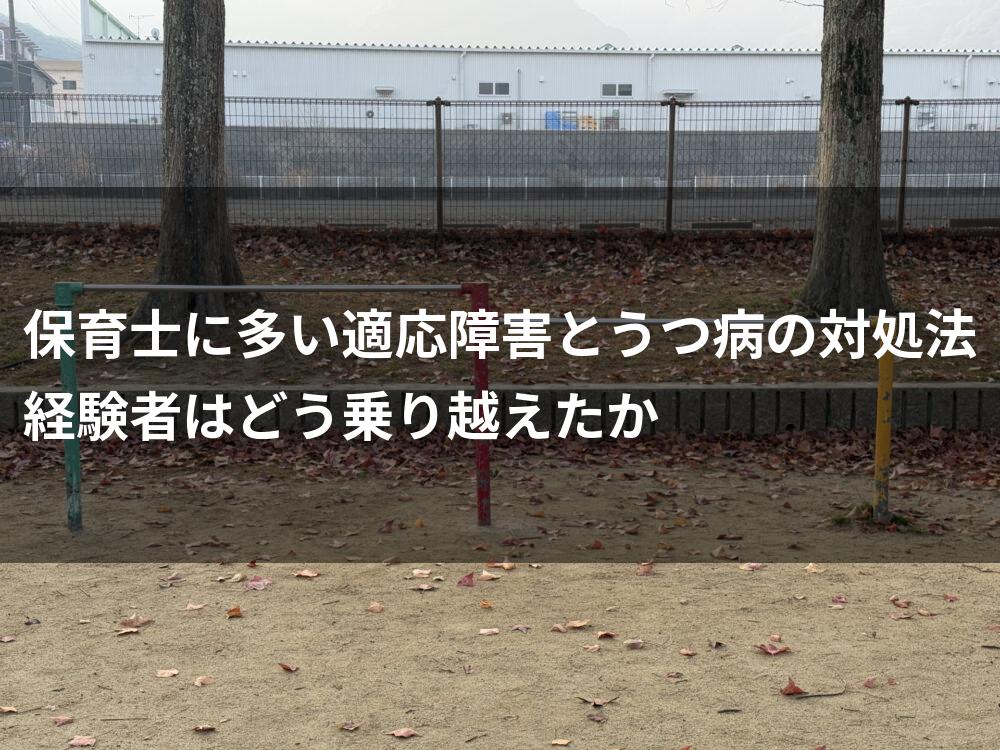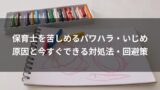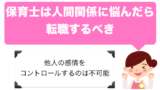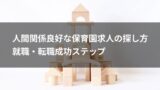| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 適応障害とは? | ・ストレスが原因で心身のバランスが崩れる状態 ・原因が明確で社会生活に支障が出る ・ゆううつや不安、不眠などの症状 ・保育士は人間関係が原因になる場合も |
| うつ病とは? | ・一日中気分が落ち込み、何をしても楽しめない状態 ・不眠や食欲不振などの身体症状もある ・脳の働きが悪くなり、ものの見方が否定的になる ・専門家への相談と休養が必要 |
| 保育士はなぜ適応障害やうつ病になる? | ・主な原因は人間関係のストレス(パワハラなど) ・仕事量の多さもストレスの要因 ・残業や持ち帰り仕事でリフレッシュできない ・複数の要因が重なって発症することも |
| 適応障害を経験した保育士へのインタビュー | ・パワハラなどが原因で発症、不眠や欠勤につながる ・病院を受診し、診断書で休職を選択 ・休職中は傷病手当金を受給し通院 ・人間関係の問題から転職、症状が改善 |
| うつ病、適応障害から保育士復帰するための方法 | ・問題のある職場は退職する ・パートや派遣、単発などで徐々に復帰 ・ベビーシッターや小規模園も選択肢 ・転職サイト活用で慎重な職場選び |
| まとめ:【経験談】保育士に多い適応障害やうつ病の対処法を経験者から学ぶ。 | ・保育士の適応障害・うつ病は人間関係や業務量多さが原因 ・経験談から早期受診や休職・転職が重要 ・回復後は無理なく安心できる環境で働く ・悩みを一人で抱えず専門家などに相談 |
| よくある質問(FAQ) | ・症状に気づいたら早めに専門病院などを受診 ・休職は医師の診断書を園に提出して申し出 ・休職中は心身を十分に休めることが大切 ・復帰・転職時は情報収集や相談で慎重な職場選び |
- 保育園に出勤したくない
- 毎日、気分が落ち込んでいる
- 仕事のストレスを溜め込んでしまっている
保育士の仕事は子どもたちの成長を支える素敵な仕事である一方、心身に大きな負担がかかることも少なくありません。
特に、強いストレスから適応障害やうつ病につながる場合があります。
この記事では、実際に適応障害を乗り越えた保育士さんの体験談を交えながら、原因や症状、そして回復への道のりや具体的な対処法について詳しくご紹介します。

ストレスで体が辛い。これって適応障害?うつ病?

同じように悩んでいるあなたへ、回復とより良い働き方を見つけるヒントをお伝えします。
- 保育士に多い適応障害やうつ病の原因と症状
- 適応障害を経験した保育士の実際の対処法と経験談
- 心身の回復を第一にした具体的な保育士復帰方法
- 安心して働き続けるためにブラックな保育園を避けることの重要性
適応障害とは?
日常生活の中で、何かのストレスが原因となって心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じたもの。原因が明確でそれに対して過剰な反応が起こった状態をいう。
症状はゆううつな気分、不安感、頭痛、不眠など、人によって様々ですが、仕事や学業などを続けたり、対人関係や社会生活を続けることに問題のある状態となります。これらは一般的には正常な人にも現れる症状ですが、適応障害の場合はそれを超えた過敏な状態となります。
※ 引用元:e-ヘルスネット https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-041.html
保育園で働く保育士の場合は、特に他の保育士との人間関係や園長との人間関係、子どもとの関わりの中で耐え難いことがありと適応障害になってしまう人もいます。
例えば、先輩保育士からのいじめやパワハラが一つの例です。特に保育園は狭い世界なので、退職する以外に逃げ場が無く適応障害になってしまう人もいます。
※ 詳細は医療機関などに確認してください。
うつ病とは?
一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなっている状態です。また、うつ病になると、ものの見方や考え方が否定的になります。うつ病かなと思ったら、自己判断をせずに、総合病院の精神科や心療内科、精神科のクリニックなどに相談しましょう。内科などのかかりつけの医師に相談したり、保健所や精神保健福祉センターの相談窓口を利用することもできます。うつ病を克服するためには、早めに専門家に相談し、しっかりと休養をとることが大切です。
※ 引用元:こころの情報サイト うつ病 https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=9D2BdBaF8nGgVLbL
保育園で働く保育士の場合は、適応障害になった結果としてうつ病の症状が出てしまうことが多いようです。
※ 詳細は医療機関などに確認してください。
保育士はなぜ適応障害やうつ病になる?
適応障害やうつ病の原因はストレスです。ストレスの原因は人によって様々です。
保育士の方の場合は、人間関係のストレスが一番多いと思います。園長や先輩保育士のパワハラなど自分にとって許容できないものがあるとそれが原因で適応障害になってしまう保育士もいます。
他にも、保育士のストレスの原因として多いのは仕事量の多さです。毎日保育園で残業して、持ち帰りの仕事もして、休日も出勤をする、こんな状況で休日にリフレッシュもできずにストレスが重なってしまうという方も多いです。
また、これらの複数の要素が重なってストレスを溜め込んでしまう保育士も多いのが実情になっています。
適応障害を経験した保育士へのインタビュー
適応障害を経験した保育士の友人から話を聞くことができたのでその内容を共有させていただきます。
適応障害を経験した保育士の状況

適応障害を経験した時の状況などを教えてもらえますか?
- パワハラ
- 眠れない
- 起きれない
- 仕事も手につかなくなってくる
- 欠勤が続いてしまった
一年目の保育士で先輩からパワハラなどを受けることがあり徐々に適応障害のような状況に陥っていったそうです。
最終的には夜も眠れなくなり、朝も起きれなくなり欠勤する形になってしまったようです。
適応障害を経験した保育士とった対処法

保育園を欠勤してしまった後の対処法を教えて下さい。
※ 病気の対処法などは人それぞれ異なると思うので、同じことをすればうまくいくというわけではないので、参考までに捉えてください。
病院に行く
このような症状になってから私がまずはじめにしたことは病院に行くということです。身近な人に相談してみて一度病院に行ったほうが良いと言われたので、病院に行くことを検討しました。
近くの病院やクリニックで精神科や心療内科があるところを探し、直近で予約がとれたのは心療内科のクリニックだったのでそちらに行くことにしました。精神科や心療内科は事前に予約が必要なことが多いので、電話をして予約をとってから行きました。
電話で軽く症状などを聞かれるので、とりあえず仕事にいけなくなってしまったということを伝えました。
病院に行くと、普通の病院と同様に受付を済ませ呼ばれるまで待機していました。受付の人に呼ばれると個室に案内されて、まずは女性のカウンセラーの方と一対一でカウンセリングを受けました。
ここでいま自分がどのような状況になっているかの経緯などを詳しく話しました。カウンセリング後は医師に呼ばれるまで再び待機となりました。
医師に呼ばれると再びカウンセリングの内容を再確認され、体に起きている症状(眠れない)などの症状を詳しく聞かれました。
休職する
私がすでに欠勤をしてしまっているということもあり、医師からはその場で休職したほうが良いという助言があり休職の診断書を発行してもらいました。病名としては「適応障害」と診断されました。
医師と相談の結果、とりあえず1ヶ月の休職をすることにしました。医療機関によるかもしれませんが、いきなり診断書を発行してくれないケースもあるようなので注意が必要かもしれません。
その診断を受けて、保育園に電話をし休職を申し出ました。すでに欠勤している日が出ていることもあり、その場ではとくに何か言われるということはなかったです。とりあえず体調を良くしてくださいということで電話は終了しました。
保育園には行きたくなかったので、診断書などは後日郵送で送付しました。
通院する
休職中は一週間に一度くらいのペースで心療内科に通院しました。薬は、眠れなかったので睡眠に関するものと、うつの症状もあったのでその薬もいくつか処方されていました。
とりあえず、一ヶ月間は仕事のことや今後のことなどは考えずに、なにをするわけでもなくとにかく休んでいました。
休職中は健康保険の傷病手当金が支給された
休職中は、健康保険の「傷病手当金」というものも支給を受けることができました。医師の診断書と保育園が発行する休職をしていることを証明する書類が必要です。
金額としては、貰っていた給料の7割程度でしたが、生活は継続できる状態だったので助かりました。
転職する
休職をして一ヶ月くらいが立って体の症状的には良くなってきました。ただ、パワハラなど人間関係の問題もあったので、おそらく再発するだけだろうという思いがあったので復職するという選択肢はほとんど消えていました。
そこからは転職をして別の保育園で働くことや、まったく別の業界で働くことも考えました。
結果的に、私の場合は保育の仕事自体は嫌いではなく、どちらかというと職場の人間関係の問題が多かったので再び保育園で働くという選択をすることにしました。
そのまま休職中に転職活動をはじめて転職先が決まったら、退職届を出して退職をしました。この間のやりとりは電話やメール、郵送などで行っているので、休職後は園長と顔を合わせるということはなかったです。
転職が決まってからはびっくりするくらい症状も改善してきたのでやはり人間関係の問題は転職するしかないのかもしれません。
適応障害を経験した保育士からのアドバイス

反省点やもっとこうしておけばよかったということはありますか?
ひとつは頑張りすぎずに早く転職しておけばよかったということです。自分のなかで年度末までは続けないとという思いもあってそれでずるずると辞められずにいました。
そうしているうちにパワハラをしてくる先輩とさらに関係が悪化してどんどん追い込まれてしまいました。早い段階で転職を決めていればこんなにつらい思いをしないで済んだかもしれないです。
もうひとつは、病院は早め早めに行くべきということです。精神科や心療内科と聞くとどこか仰々しいイメージもあったり、自分は病気じゃないという思いもあってなかなか行けていませんでした。
実際に病院に行ってみると心療内科などは普通のサラリーマンの人とかも多く来ていて、想像ほど仰々しいものではなかったです。極端な話、風邪を引いて薬をもらうというくらいの感覚で行っても良いと思います。
適応障害を経験してみてわかったことは、体は結構正直だなということです。出勤しなくてはと思っても、体が拒否をしているというようなイメージです。おそらく出勤したら嫌なことが起きるということからの防御反応です。
そういう意味では正しい防御反応なので、早めに病院に行って相談し、転職をしてしまったほうが良いと思います。保育士が特定の保育園に固執する必要は無いと思っています。
うつ病、適応障害から保育士復帰するための方法
- 退職する
- パート保育士として復帰する
- 派遣保育士として復帰する
- 単発、短期間の保育士として復帰する
- ベビーシッターとして復帰する
- 小規模保育園で復帰する
- 保育士転職サイトに登録して復帰する
- 無理して急いで復帰する必要はない
ここからは、うつ病、適応障害から保育士復帰するためのおすすめの方法について紹介します。
退職する
まだ、保育園を退職していないという方の場合で、職場の労働環境や人間関係に問題があるという場合は、その保育園を退職するというのが復帰の第一歩になります。職場の労働環境や人間関係に問題がある場合は、どうしてもその部分が復帰妨げになってしまうことがあります。今の職場で無理して復帰しようとしないということが一つの選択肢になります。
パート保育士として復帰する
パートなどの短時間での勤務であれば、負担が少なく、徐々に心と体を仕事へと慣らしていくことが出来ます。いきなりのフルタイムでの復帰は難しいという方は、まずはパートから復帰するのがおすすめです。
派遣保育士として復帰する
派遣保育士として就業することの良い点は、登録した派遣会社が それなりに色々やってくれる ということです。求人探しは、もちろん、就業後のフォローなどもです。例えば、ブラック保育園の労働違反などにトラウマがあるという方もいらっしゃるかもしれません。派遣保育士の場合は、派遣会社に相談をすることができ、派遣会社が保育園に対して、改善などを求めてくれます。
また、派遣の場合は、保育園との面接はないので、気負うことなく就業開始ができます。そして、派遣保育士の場合は、期間が決められた雇用になるので、終わりが見えていると心理的な安心感もあると思います。
単発、短期間の保育士として復帰する
フリーランスの保育士であったり、単発の派遣の仕事などで、復帰するというのもおすすめです。単発や短期間であれば、人間関係にあまり気を使う必要がないため、人間関係の構築に自信がないという方にもおすすめです。
ベビーシッターとして復帰する
キッズラインなどのベビーシッターの仕事は、基本的に、子どもと一対一でのシッティングの仕事がメインなので、人間関係に気を使う必要がありません。また、ノルマなどはないため、完全に自分自身が働きたい時間に働くということが出来ます。
小規模保育園で復帰する
小規模な保育園で復帰するというのも良い選択肢の一つです。小規模な保育園は、園児の人数も、職員の人数も、仕事の負担なども全体的に大規模保育園と比較して少ない傾向があります。そのため、いきなり、フルで働くというのが難しいという方におすすめになります。
保育士転職サイトに登録して復帰する
保育園や職場での人間関係が原因で、うつ病、適応障害の原因となってしまったという場合は、同じことをまた経験したくはないですよね。そのためには、慎重に新たな職場を選ぶ必要があると思います。保育士転職サイトを活用すれば、担当者と相談しながら、求人を選ぶことができます。
保育士転職サイトの担当者は、保育園の人間関係や内部事情なども知っている場合があるので、保育園の詳し情報を聞きながら、就職する保育園を選んでいくことができます。
- マイナビ保育士
 |全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです! - ジョブメドレー保育士
 | 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)

- ヒトシア保育| ※全国の正社員・派遣・パート保育士の求人に対応しています。登録しないと得ることができない非公開の求人もたくさんあります。 求人数も多いのでとにかくたくさんの情報を得たいという人にもおすすめです。
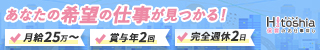
※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。
無理して急いで復帰する必要はない
ここまでうつ病、適応障害から保育士復帰するためのおすすめの方法について紹介しましたが、無理して急いで復帰する必要はないということも理解しておく必要があります。保育士に限ったことではないですが、人間は心と体が一番大切です。無理して復帰してしまうと、余計に状況が悪化してしまう可能性があります。
特に、保育士の場合は、保育士不足の状態なので、多少のブランク期間があったとしても復帰しやすい環境にあります。そんななかで、復帰を焦ってしまうと、ブラックな保育園に就業してしまうリスクも増えてしまいます。
ブラックな保育園に復帰しないことも大切
うつ病、適応障害から復帰するための、まず一番大切なことは、ブラックな保育園に就職しないことです。ブラックな園は労働環境も人間関係も良くないことが多いため、余計に状況が悪化してしまう可能性もあります。
まとめ:【経験談】保育士に多い適応障害やうつ病の対処法を経験者から学ぶ。
保育士の仕事で強いストレスを感じることは珍しくありません。
そのストレスから適応障害やうつ病を発症する方もいらっしゃいます。
この記事では、実際に適応障害を経験した保育士さんの体験談を交えながら、その原因や症状、そして回復のための具体的な対処法や復帰への道筋についてご紹介しました。
心身の健康を守るためにも、まずはブラックな保育園に就職しないことが最も重要です。
- 保育士の適応障害やうつ病の原因は人間関係や業務量の多さ
- 適応障害を経験した方は、早期に病院を受診し、休職や転職を選択している
- 心身が回復したら、無理のない働き方や安心して働ける環境を探すことが大切
- 問題のある職場に戻らず、自分に合った方法でキャリアを継続する
もし現在、心身の不調を感じていたり、職場の環境に悩んでいたりするならば、一人で抱え込まず、専門家や信頼できる人に相談してください。
この記事でご紹介した対処法や復帰方法を参考に、あなたに合った方法を見つけて、心身ともに健康に働き続けられる環境を探していきましょう。
再三にはなりますが、病気の対処法などは人それぞれ異なると思うので、同じことをすればうまくいくというわけではないので、参考までに捉えてください。
私自身も保育園に出勤したくないなと思っていたことはありました。おそらくこのような気持ちが適応障害のはじまりだと思います。
特に人間関係の問題であれば、極端な話その人がいなくならない限りは改善されないことになります。
保護者とのトラブルであれば、その子どもが卒園するまで我慢すればなんとかなるかもしれませんが、園長や先輩保育士との問題であれば、いつその人達がいなくなるかわかりません。もしかしたらずっとそのままの関係かもしれません。
保育園に出勤したくないなと思う原因が自分で取り除けるものであれば良いですが、取り除けないものであればやはり転職を考えるしかないのかもしれません。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士として働く中で、適応障害やうつ病の症状が出ているかもしれないと感じたら、まずどうすれば良いですか?
- A
体のだるさや気分の落ち込み、眠れない、といった「もしかして」という症状に気づいたら、早めに病院を受診してください。
精神科や心療内科といった専門家に相談する方法や、まずはかかりつけの内科医に話を聞いてもらう選択肢もあります。
自分は大丈夫だと思わず、早めに相談することが大切です。
- Q適応障害やうつ病と診断された場合、休職するためにはどのような対処法をとるのですか?
- A
適応障害やうつ病と診断されたら、医師に休職の必要性について相談しましょう。
医師から診断書を発行してもらえます。
その診断書を園に提出し、休職の申し出をします。
園への連絡は電話や郵送といった方法で行えます。
詳細は、園の就業規則を確認するか、人事に問い合わせてください。
- Q休職中に心身を効果的に休めるための具体的なメンタルケアの方法はありますか?
- A
休職中は、焦らずゆっくり休むことが最も重要です。
十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけましょう。
散歩やストレッチなど、無理のない範囲での軽い運動は心身のリフレッシュにつながります。
好きな音楽を聴いたり、穏やかな趣味に時間を使ったりするのも良いでしょう。
心と体が安らぐ時間を多く持つように意識することが大切です。
- Q復帰や転職を検討する際に、ブラックな保育園を避けるための具体的なポイントは何ですか?
- A
ブラックな保育園を避けるためには、事前に情報収集をしっかり行う必要があります。
労働条件通知書に記載されている残業時間や休日規定を詳しく確認しましょう。
面接では、実際に園で働く職員の様子や園全体の職場環境を注意深く観察してください。
保育士転職サイトを利用する場合、担当者から職場の人間関係や実際の働き方について詳しい情報を得ることも有効です。
- Q保育士の仕事に関する悩みやストレスについて、どこに相談できるのですか?
- A
保育士の仕事で抱える悩みやストレスは、一人で抱え込まないことが重要です。
園の同僚や信頼できる先輩、家族や友人に話を聞いてもらうことも有効です。
園によっては、産業医やカウンセラーといった専門家に相談できる窓口を設けている場合があります。
公的な機関としては、保健所の精神保健福祉相談や各自治体の相談窓口を利用できます。
- Q一度適応障害やうつ病を経験した後、復帰して再発を防ぐためにはどのような対策が必要ですか?
- A
適応障害やうつ病から復帰した後、再発を防ぐには対策を講じることが大切です。
まずは、自分自身のストレスサインにいち早く気づくことが重要です。
疲れや不調を感じたら、無理せず休息をとりましょう。
人間関係など、ストレスの原因が特定の事柄にある場合は、園と相談して業務内容や配置の調整を試みることも必要です。
一人で抱え込まず、定期的に専門家と話す機会を持つことも再発予防につながります。
柔軟な働き方を選択することも有効な対策になります。