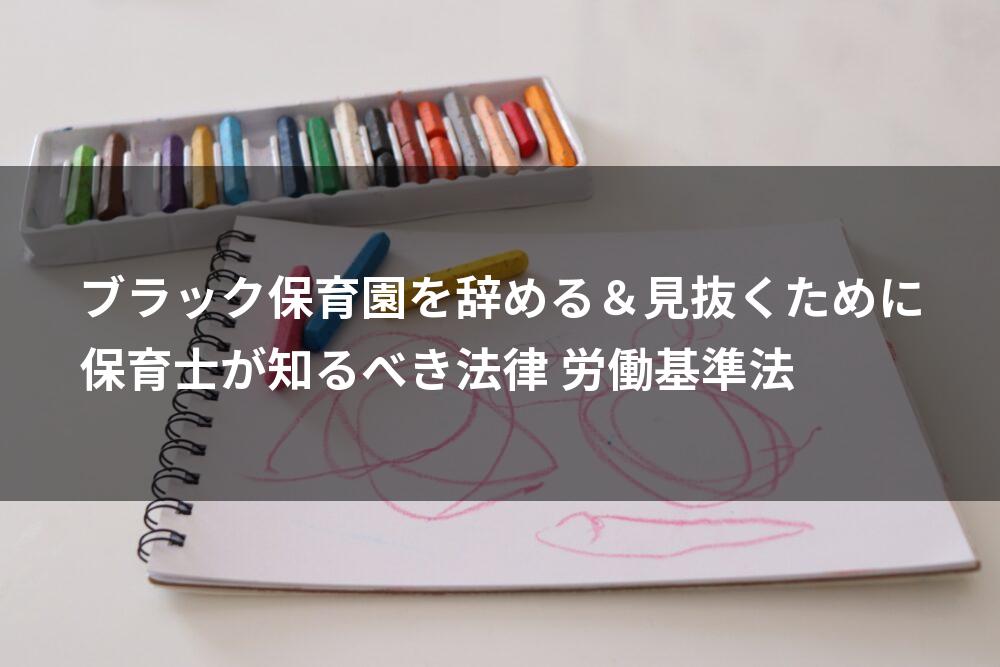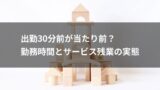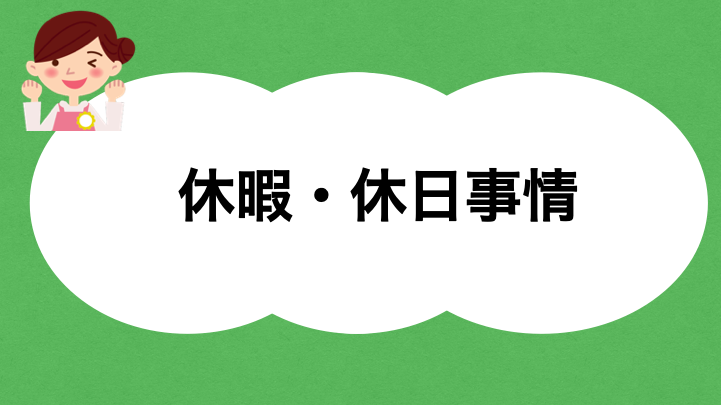| 目次 | 内容 |
|---|---|
| ブラック保育園から抜け出すのになぜ法律を知る必要があるか | ・ブラックかの判断基準の一つに法律遵守の有無 ・サービス残業や持ち帰り残業は法律違反 ・法律知識があれば園の指示の正当性を判断し、不当要求に対抗可能 ・知識がないと経営者の言いなりになり不利な状況に陥るリスク |
| 保育士が最低限知っておくべき法律「労働基準法」 | ・労働者の権利を守る基本法 ・労働時間(法定・変形)、残業(36協定・割増賃金)、休憩(必要時間・業務離脱)、休日(最低日数)の規定 ・有給休暇(付与条件・日数・取得義務)、解雇(制限・予告)、出産・育児休業(権利)、退職(意思表示期間)のルール ・就業規則(作成・記載事項・周知義務、法律を下回る規定は無効)の重要性 |
| 法律違反に関しては客観的な記録を残しておくべき | ・サービス残業など法律違反の客観的な証拠(出退勤時間のメモ等)を残すことの推奨 ・記録は後々の残業代請求などで有効な証拠となる可能性 |
| 法律を理解してブラック保育園を退職しよう! | ・労働関連法の知識が、現職場の状況判断や転職時の見極めに役立つこと ・法律を学び、自身の働き方を見直すことの推奨 |
| まとめ | ・ブラック保育園に悩む保育士にとって労働基準法の知識が重要であることの再確認 ・主な内容(法律知識の必要性、主要項目、見極め方、記録の重要性)の概要 ・公的機関への相談やホワイトな園への転職も選択肢 ・権利を守り、安心して働ける環境を見つけるための行動喚起 |
| よくある質問(FAQ) | ・サービス残業/持ち帰り仕事は違法であり断る権利があること、相談先の提示 ・法律上は2週間前通知で退職可能であること、退職代行などの手段 ・有給休暇は原則全て消化可能であること ・求人票や面接でのブラック保育園の見分け方のヒント、パワハラや相談への不安に対するアドバイス |
- ブラック保育園に悩んでいる?
- 勤務している保育園のこれって法律的にOKなの?
ブラック保育園での過酷な労働環境に悩み、「もう限界かも…」と感じている保育士さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、そのような状況から抜け出し、自身の権利を守るために不可欠な「労働基準法」の知識について、ブラック保育園での勤務経験がある私が解説します。
法律を知ることで、現在のブラック保育園の特徴や問題点を正確に把握し、不利なく退職交渉を進めたり、次の転職で失敗しないための見分け方を身につけたりすることができます。

今の働き方、もしかして法律違反?どうやって辞めたらいいんだろう… 辞めた後の転職も不安だな…

労働基準法を知れば、自分の身を守り、より良い労働環境を選ぶ力がつきますよ
- ブラック保育園の問題と法律知識の重要性
- 保育士が押さえるべき労働基準法のポイント(労働時間、残業、休憩、休日、有給、退職など)
- 転職時にブラック保育園を見抜くための視点
- 法律違反の証拠を残すことの大切さ
ブラックに悩んでいる場合はまずは、法律を知るべきだと私は思っています。
ブラック保育園に対抗するには法律を知ることも重要だと思う。何も知らなかった昔の私は、園が言うんだからそういうもんだろうと勝手に思ってた。法律を知ることでしっかりおかしいことにも気づける。
— 保育士さえこ@ブラック脱出済 (@hoikushisaeko) August 31, 2019
法律を知ることで正当にブラックに対抗することができ、転職の際もブラック保育園かどうかを見極める力にも関わってくると思っています。このことに関して解説していきます。私は法律に詳しいわけではないので、法律に関する詳細はしっかりと専門家や機関に確認することを推奨します。
ブラック園で働いていたことがあります
複数回の転職経験があります
その経験が参考になればと思います
ブラック保育園から抜け出すのになぜ法律を知る必要があるか
ブラックかどうかの基準のひとつに労働関係の法律が守られているかどうかという基準があると思います。ブラックの定番であるサービス残業・持ち帰り残業は法律違反そのものです。
日本では、労働者を守るために様々な法律が定められています。保育士は法律を知ることで、今働いている保育園で法律が守られているかどうかがわかるようになります。
また、法律を知らないとブラック保育園の経営者に言われたことに従うしかなくなってしまいます。
例えば、「残ってる仕事は家に持ち帰ってやって」と言われたときに、それが正しいことなのかどうかわからないです。法律を知ることでそれが法律違反 = 正しくないと理解することができます。
法律違反だと知ることでなにか問題が起きたときも正当に対処することができます。
逆に法律を知らなければ、何が良いか悪いかということの判断基準が曖昧になり、ブラック保育園の経営者に足元をすくわれるということも起きてしまいます。
保育士が最低限知っておくべき法律「労働基準法」
労働者と雇用者が守るべき基準を定めている法律が「労働基準法」です。ブラックで悩んでいる保育士が最低限知っておくべき法律です。
法律は、基本的には「最低条件」が明示されているので、事業者が労働者にとってこの条件を上回る条件を定めることは可能です。
一部「労働基準法」以外の法律も関わってくる部分があると思いますが、保育士が特に知っておくべき内容について以下に示しています。
法定労働時間について
法定労働時間については以下のようになっています。
- 週間40時間、1日8時間が限度
また、労使協定や就業規則などで定めた場合は1週間単位、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制を導入することができます。
- 1週間単位の変形労働制
- 1ヶ月単位の変形労働制
- 1年単位の変形労働制
変形労働制の場合は1週間単位、1ヶ月単位、1年単位で労働時間を設定することができます。
保育士の求人でもたまに変形労働制を採用しているものがあります。
これは、その該当期間、一週間であれば一週間の労働時間が定められているということになります。例えば、週40時間の変形労働制であれば、一週間に働く時間の合計が40時間ということになります。
ある一日に多くの時間働いたとしても、ある一日の労働が短いなどで週に働く時間が調整されます。支払われる残業代にも影響してきます。
残業について
労働基準法では、法定労働時間以上の労働をする場合、36協定というものを結ぶ必要があります。
法定時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、これを超えることができますが、その場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、複数月平均80時間以内とする必要があります。
法定時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、これを超えることができますが、その場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、複数月平均80時間以内とする必要があります。
ただし、この残業時間には例外があります。特別条項付き36協定を締結していると、さらに上限を超えて残業をすることが可能です。
特別条項付き36協定 には以下の条件があります。
- 延長できる時間は、労使であらかじめ決めておかなければならない
- 残業の上限が延長できるのは「特別な事情」がある場合のみ
- 残業の上限が延長できるのは1年の半分まで
残業時間に関して以下の割増賃金を支払う必要があります。
- 1週間の労働合計時間が40時間以上、または1日の労働時間が8時間以上の場合は1.25倍分支払い
- 週一回の休日出勤に関しては1.35倍分支払い
- 22時から翌5時までの深夜労働は1.25倍分支払い
- 1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた部分については、1.5倍分支払い
いずれの場合でも残業したぶんの時間の賃金は必ず支払われる必要があります。
休憩について
休憩については以下のように定められています。
- 6時間以上の労働を続けたら45分の休憩
- 8時間ちょうどの場合は45分の休憩
- 8時間を超えた場合は1時間の休憩
例えば、所定の労働時間が8時間で休憩が45分と規定されている保育園の場合、残業を1分でもした場合は追加で15分の休憩を取る必要があります。
休憩は業務から完全に離れている必要があります。保育士で給食の介助、午睡の見守りや書類仕事をしている場合は法律上正しい休憩時間とは言えません。
休日について
休日については以下のように定められています。
- 最低限週1回は休日、もしくは4週間ごとに4日以上の休日が必要
保育園は週休二日が多いですが、実は最低限週に一回休日があれば良いんですね。
有給休暇について
有給休暇に関しては以下の付与条件になっています。
- 6ヶ月間継続して勤務、そのうち8割以上出勤で10日間の有給休暇付与
付与日数は以下のようになっています。
- 半年継続勤務で10日
- 1年半継続勤務で11日
- 2年半継続勤務で12日
- 3年半継続勤務で14日
- 4年半継続勤務で16日
- 5年半継続勤務で18日
- 6年半継続勤務で20日
有給休暇の権利は発生日から2年間有効であり、繰り越しが可能です。前年度からの繰越分と合わせて、保有できる有給休暇日数の上限は最大40日となり、それを超える分は消滅します。
2019年4月からは、年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させる必要があります。正社員として雇用されている場合は、基本的に5日間は有給休暇を取得できることになります。
- 年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させる義務
有給を消化させる義務は会社側にあり、違反すると罰金などの定めがあります。
そして、有給の買い取りについては基本的に違法となります。前述の消失分を企業が独自の取り決めで買い取る場合は合法となります。
有給休暇の取得理由は必要なく、有給休暇については労働者から請求があった場合は、会社は正常な運営を妨げる場合において、時季変更を依頼することが可能です。
すなわち、違う日付に有給休暇を与えるということです。保育所においては、正常な運営を妨げる場合というのは必要な保育士の人数が確保されない場合になると思います。
かなり前もって休暇を伝えていたにも関わらず、時期の変更の依頼があるということは、保育所側が必要な保育士を確保する義務を果たしていないということになります。
解雇について
労働基準法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
すなわち、園長や経営者の気分で、客観的に合理的な理由がなく解雇はできません。
そして、解雇は前もって伝える必要があります。
- 解雇の30日前に予告するのが原則
- 即時の場合、30日分の平均賃金を即時に支払う
解雇を行う場合、原則として少なくとも30日前に予告する必要があります。30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。これは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる解雇の場合でも同様です。
出産休業について
出産休業については以下の条件があります。
- 6週間以内(双子以上の場合は14週間)以内に出産の予定のある場合に請求があれば出産休業
- 産後8週間は必ず出産休業の義務があり、医師から支障がないと診断された場合のみ6週間後から就業が可能
育児休業について
育児休業については以下の条件があります。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されていないことが明らかでない
退職について
退職については、2週間前までに退職の意思表示を被雇用者側からする必要があります。
- 2週間前までに退職の意思表示をする必要がある
そのため、園独自のルールで「3ヶ月前に伝える」というルールを定めていても、法律上は2週間前に退職の意思表示をすれば退職は可能となります。
あくまでもそれは、園が決めた勝手なルールなので保育士が守る義務はありません。
口頭でも退職の意思表示をすれば退職することが可能です。退職届を出して、受取拒否などをしても口頭で伝えておけば問題ないです。
就業規則について
「常時10人以上労働者を使用する使用者」は就業規則を作成することを義務付けています。保育園は通常、常時10人以上労働者を雇用している場合が多いので用意されているはずです。
就業規則には以下の内容が定められています。
- 始業及び終業の時刻
- 休憩時間
- 休日(週のなかでどこを休めるのか)
- 休暇(有給休暇、育児休暇など)
- 交代勤務がある場合はその交代勤務について
- 賃金
- 賃金の計算、支払い方法、いつ払うかなど
- 退職について
- 退職手当について
- 臨時の賃金や最低賃金の設定について
- 労働者が負担する金額について(食費や作業用品など)
- 安全や衛生について
- 職業訓練について
- 災害補償について
- 業務外の疾病の扶助について
- 表彰
- 制裁
- 他に全労働者が関わることについて
労働者にとって法律の条件を上回る規則を定めることは可能ですが、下回る規則(不利な規則)を定めていても無効となります。
就業規則の内容は労働者に周知されている必要があるので、見たことがない、見させてももらえないという場合は違法の状態になります。
法律違反に関しては客観的な記録を残しておくべき
ブラック保育園の法律違反に関しては、しっかりと客観的な記録を残しておくべきです。
例えばサービス残業を強いられているという場合は、毎日何時に出社して何時に退勤したという情報をメモに残しておくと良いです。
あとあと、残業代を請求するということになった場合にも有効な証拠になります。
法律を理解してブラック保育園を退職しよう!
今勤務している保育園が、なんとなくブラック保育園だとはわかるけど労働関係の法律はあまり詳しくないという方は、一度労働関係の法律に関しては目を通しておくとよいと思います。
次に転職する際にもブラックを見極めるのに役にたつような知識を得ることができるかもしれません。
まとめ
この記事では、ブラック保育園での過酷な労働環境に悩む保育士さんに向けて、労働基準法の知識がいかに重要かを解説しました。
法律を知ることは、自分を守り、より良い働き方を選ぶための第一歩になります。
- ブラック保育園の問題と労働基準法知識の必要性
- 保育士が知るべき労働基準法の主要項目(労働時間、休憩、有給など)
- 転職活動でブラック保育園を見抜く方法
- 違法な働かせ方の客観的な記録の重要性
まずは労働基準法の内容を確認し、今のブラック保育園を辞めるべきか、ご自身の働き方を見つめ直してみましょう。
必要であれば労働基準監督署などの相談窓口への相談や、ホワイト保育園への転職も検討してください。
保育士としての権利を守り、安心して働ける環境を見つけるために、一歩踏み出すことが大切です。
よくある質問(FAQ)
- Qサービス残業や持ち帰り仕事が「当たり前」になっていますが、断っても大丈夫でしょうか?
- A
たとえ「みんなやっている」という雰囲気でも、労働時間外の労働、つまりサービス残業や持ち帰り仕事を強制することは労働基準法に反します。
勇気を出して断ることは、自分の心と体を守るために大切なことです。
もし断りにくい場合は、記録を残し、労働基準監督署などの相談窓口に相談することも考えてみてください。
- Qブラック保育園を辞めたいのですが、引き止めが怖くて言い出せません。
- A
引き止めへの不安、よくわかります。
法律上は退職の意思を伝えてから2週間で退職できます。
もし直接伝えるのが難しい場合は、内容証明郵便で退職届を送る方法や、退職代行サービスの利用も選択肢の一つになります。
ご自身の安全と精神的な負担を最優先に行動しましょう。
- Q退職時に残っている有給休暇は、すべて消化できますか?
- A
はい、労働基準法で定められた有給休暇は労働者の権利であり、原則として退職時にすべて消化することが可能です。
園側が一方的に有給消化を拒否することはできません。
もし拒否された場合は、理由を確認し、必要であれば労働基準監督署へ相談することも可能です。
- Q転職活動中です。求人票だけでは良い保育園か判断できません。
- A
求人票 チェックポイントとして、給与や福利厚生だけでなく、具体的な労働時間の記載(固定残業代の有無など)や休日数を確認しましょう。
面接では、職場の雰囲気や残業の実態、保育士の離職率などについて逆質問をしてみるのがブラック保育園の見分け方の一つです。
園長の人柄や他の職員の様子も注意深く観察してください。
転職エージェントに相談し、口コミ情報を得るのも有効です。
- Q園長や先輩からの言動がパワハラではないかと感じています。
- A
もしパワハラかもしれないと感じたら、一人で抱え込まないでください。
まずは、いつ、どこで、誰に、何をされた(言われた)のか、具体的な状況を記録に残すことが重要です。
その上で、信頼できる同僚や家族に相談したり、園内の相談窓口、労働組合、または外部の労働基準監督署や弁護士などの相談窓口にパワハラ相談を検討しましょう。
ハラスメント 防止は園側の義務でもあります。
- Q労働基準監督署に相談したいのですが、少し不安です。
- A
労働基準監督署への相談は、保育士が労働環境 改善のために利用できる公的な窓口です。
匿名での相談も可能ですし、相談内容に応じて適切なアドバイスや、場合によっては園への指導を行ってくれます。
違法残業や休憩時間が取れないなど、労働基準法に関わる問題であれば、まずは電話などで気軽に問い合わせてみることをお勧めします。
相談は無料です。