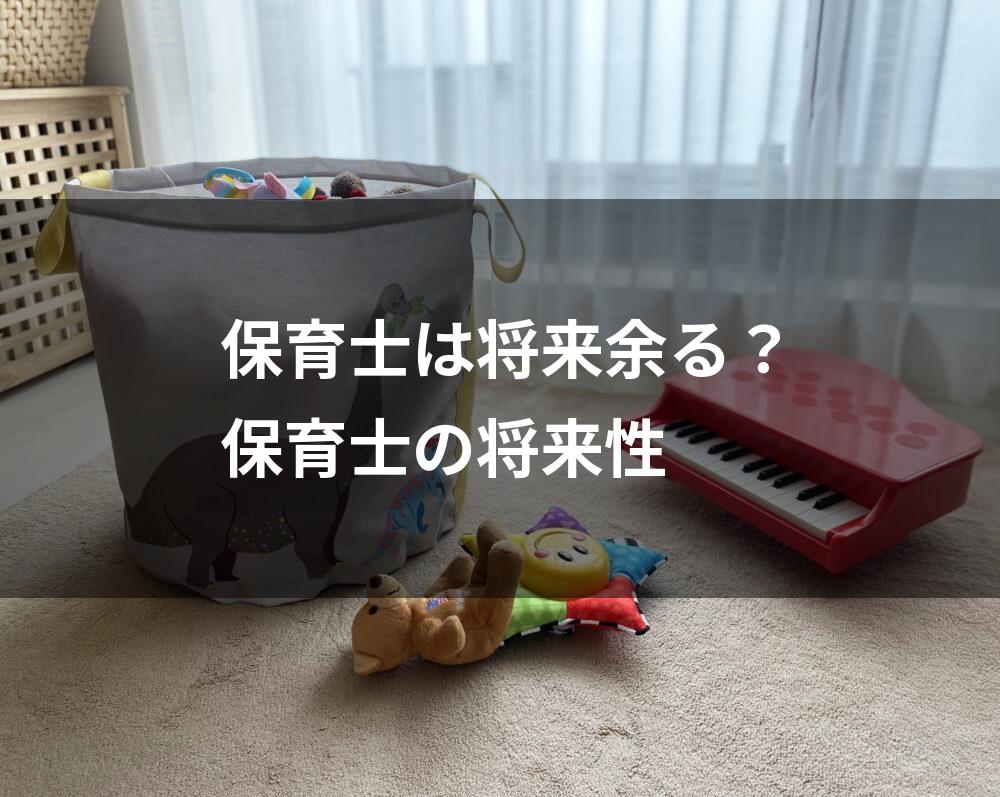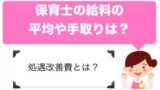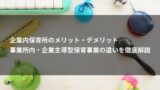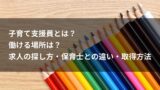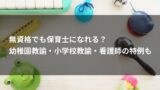| 目次 | 内容 |
|---|---|
| 保育士の給料は将来的にどうなる? | ・国主導の処遇改善で、全産業の女性労働者の賃金水準まで向上する可能性。 ・景気に左右されにくいが、保育需要により給与水準が変動する可能性。 ・給料や待遇改善を求めて転職が加速する傾向が予想される。 |
| 保育士の需要は将来的にどうなる? | ・共働き世帯の増加により、保育需要は中期的に増加傾向。 ・少子化により、長期的には保育需要が低下する可能性。 ・規制緩和が進むと、保育士資格の有無に関わらず人材が活用され、保育士が余る可能性。 |
| 保育士の資格は将来無意味なものになる? | ・保育士資格が完全に無意味になる可能性は低い。 ・規制緩和により資格が形骸化する可能性は否定できない。 ・国は待機児童解消のため、無資格者の活用を進める可能性がある。 |
| AI(人工知能)などの技術革新の影響は? | ・AI技術により、一部業務(見回りなど)が代替される可能性。 ・事務作業などの雑務はIT化により効率化が進むと予想される。 ・最低限のITスキルは保育士も身につける必要性が高まる。 |
| 外国人人材や移民などの影響は? | ・外国人が保育士資格を取得し、保育園で働くことは可能。 ・規制緩和により、外国人人材が安価な労働力として保育現場で増加する可能性。 ・保育の質を維持するため、保育士は規制緩和に反対する必要がある。 |
| ベビーシッターによる保育園機能の代替の影響は? | ・待機児童がベビーシッターを利用する流れがある。 ・ベビーシッターを外国人でカバーする可能性も考えられる。 ・保育士は日本人にしかできない質の高い保育を提供する必要がある。 |
| 保育士個人はどうしたら良いか | ・保育士や他業種へ転職できるスキルを身につけることが重要。 ・保育の質が低い保育園との関わりは避けるべき。 ・質の低いスキルが身につき、トラブルに巻き込まれるリスクがある。 |
| 【まとめ】保育士の将来性と保育士が生き残るには | ・給与水準は改善傾向にあるものの、少子化により長期的には需要が低下する可能性。 ・IT化が進んだ保育園を選び、ITスキルを身につけることが重要。 ・保育士同士で団結し、国を動かす必要性がある。 |
| よくある質問(FAQ) | ・保育士は他分野でも活躍できるスキルを身につけておくことが重要。 ・共働き世帯の増加は中期的に保育士の需要を増加させる。 ・AI技術は一部業務を代替する可能性、保育士としての専門性を高めるだけでなく、他分野のスキルも身につけることが大切。 |
- 保育士の仕事は将来どうなる?
- 保育士の仕事に将来性はある?
- 将来は保育士が余る?
保育士の将来性について、現役保育士の視点から徹底的に考察した記事です。保育士として、保育士という職業の将来性について真剣に考えてみました。
この記事を読むことで、保育士の給与や需要が今後どうなっていくのか、AI技術や外国人材が保育現場にどのような影響を与えるのかがわかります。

保育士の仕事って、将来どうなるんだろう?

保育士として長く活躍するために、今からできることを知りましょう!
この記事でわかること
- 保育士の給与は一定水準まで上昇する見込み
- 共働き世帯の増加により、中期的には保育士の需要は増加
- 少子化の影響で長期的には保育士の需要は低下
結論として、保育士として生き残るためには、単なる保育スキルだけではなくプラスアルファの付加価値が必要になると考えています。今でこそ保育士不足で待機児童が発生していますが、日本は少子高齢化なので、この流れはいずれ落ち着いていきます。そうなると、保育士余りの時代に突入します。
その経験が参考になればと思います
保育士の給料は将来的にどうなる?
まずは、保育士の給料は将来的にどうなるのかという考察になります。
処遇改善は一定水準までは進む
現在は、国主導の保育士の待遇改善が進んでいて、最終的には「保育士の処遇について、全産業の女性労働者との賃金差がなくなるよう追加的な処遇改善を行う」とされています。
全産業の一般労働者の女性の賃金平均が約24.6万円なので、その水準までは給料が上がっていくという計画があります。
なぜ「女性」の労働者との賃金差なのかがわかりませんが、少なくとも直近では平均月給の約24.6万円というのが目標のようです。
それ以降は、その時の保育需要によって決まってくるのではないかと思っています。その基準まで給与が上がったとしてその時に待機児童がゼロであればそのままの待遇が維持され、それでも保育士が足りなければさらに処遇改善が進んでいくのではないでしょうか。
保育士の給料は景気に左右されにくい?
保育士の給料は景気に左右されづらいというのが特徴です。保育園は国の補助金で成り立っているので景気が悪いからと言って補助金が減るということが無いためです。
むしろ景気が悪化すると、夫婦の給与が悪化して今まで専業主婦・主夫だった人が働きに出る必要が出てきます。その際に、こどもを保育園に預けるという流れが加速するため、保育の需要はやや高まる傾向にあります。
現段階では、日本は人口減などにより中長期的には不景気になるということが確実視されているので、保育士はその点では安定感のある職業と言えると思います。
給料・待遇改善を求めての転職は加速する
保育士の転職のハードルは、年々低くなってきていると感じています。保育士不足で転職に抵抗がない保育士が増えてきているため、給与・待遇改善を求めて保育士の転職は加速していくと考えられます。
保育士の需要は将来的にどうなる?
保育士の将来を考える上で、保育需要が今後どうなっていくのかという点は切っても切れない問題になります。
共働きで引き続き需要が増加
先にも示した通り、夫婦共働きというのが今の政府の推進でもあり、世の中の流れになっています。その中で保育需要というのはさらに高まっています。
夫婦共働きは、国にとってもメリットがあります。働く人が増えると、税収が増えるためです。収入がない人は所得税や住民税を支払わなくて良いですが、収入がある人は所得税や住民税の支払いが必要になるためです。会社も従業員を雇用し売上と利益を伸ばすことができれば、法人税として国にお金が回ってきます。
共働き世帯は確実に年々増加していて、保育需要も高まってきています。少なくとも共働きの割合は一定水準まで上がっていくのでその期間は保育需要は増加していくと思います。
人口と少子化の影響は?
日本の人口は確実に減少していて、もちろん、就学前人口も減っていっているので、将来的には保育需要は低下していくことは間違いないです。
現在は就学前人口は減っていても、共働きの増加による保育需要増加ペースの方が上回っているので保育需要は増加していますが、どこかの時期を境に保育需要は確実に減っていきます。
東京に関して言えば、2025年以降人口が減少していく予定なので、そこが一つのターニングポイントになると考えられます。逆に言えば、それまでは保育需要は高まる要素しかありません。
保育士はさらに先の将来は余る?
将来的には保育士があまってしまう、保育士として働きたいけど働けない人が増える可能性は高いと思っています。
地方は東京よりも早い段階で、保育需要が低下していくと思います。
今は保育士不足ですが、10年後20年後は逆に保育士が余っているという未来も想像できます。そうなってくると保育士の待遇にも影響が出てくると思います。
今は保育士不足が深刻なため、例えば、パワハラなどをする園長がいる保育園に対して「一斉退職」するという手段で対抗する保育士もいます。
保育士が余っている状態だと、一斉退職後に働く先がなくなってしまう可能性があります。結果的に一斉退職は起きにくくなり、我慢して働くことになるでしょう。
パワハラやサービス残業などの悪化した労働環境が改善されるきっかけがなくなってしまいます。
将来保育士が余る原因となり得るもの
ここからは、将来保育士が余る原因となり得るものを紹介します。
保育需要がなくなる
少子高齢化が進んでいて、人口が増える見込みがありません。そのため、保育が必要な子どもの人数も将来的には現状していく見込みになります。一方で、就業者に関しては定年が引き上げられたり、共働きも進んでいるため、保育士として働くことができる状況の人は減るとは限りません。そのため、
保育園が閉園する
保育需要がなくなるということと等しいですが、入園を希望する人が少なくなれば、最終的にはその保育園は統合されたり、閉園されることになります。結果的に、働いている保育士も就業を続けられなくなる可能性が出てきます。
規制緩和が行われる
保育士に関係がある規制緩和とは、例えば、
- 保育士資格を持っていなくても保育士として働けるようにする
- 外国人の人材を保育士として登用する
- 保育士ひとりあたりの園児の人数を基準を引き下げる
- ロボットなどを保育士の代用とすることができる
などが挙げられます。
規制緩和が行われると、例えば、先程の例のより安価に雇用できる無資格者や外国人の人材の保育従事者増やすということが考えられます。また、園内に必要な保育士の人数を減らすということもあるでしょう。
結果的に、保育士資格を持っている保育士が余ってしまうことが起こり得ます。
規制緩和は徐々に行われていく
自分が働いている園は地方裁量型認可化移行施設ではないので関係ないと感じている方もいると思います。
たしかにその通りですが、注意が必要なのは規制緩和は知らない間に徐々に行われているという点です。
最近でも以下のような保育士配置の規制緩和となるような制度ができています。
- 企業主導型保育事業
- 保育士の割合50%、認可保育園なみの保育園補助金
- 朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例
- 保育士最低2人配置要件について、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。
- 幼稚園・小学校教諭の保育士代替
- 保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保育士に代えて活用可能とする。
私自身も知らないまま、地方裁量型認可化移行施設が出来ていましたし、今後もこのような気づかない間に徐々に規制緩和が行われていく可能性があります。
気づいたら自分が働いている保育園になんらかの影響が出ているということが起きます。
保育士があまると既存の保育士はどうなる?
保育士が余ってしまうと、既存の働いている保育士はどうなるのでしょうか。予想してみます。
転職がしにくくなる
転職をしようと思っても、募集をしている園が少なくなります。また募集をしていても応募者の人数が多くなるため、合格する確率も低くなります。結果的に、保育人材の流動性が下がってしまってい、全体的に転職がしにくくなります。
ブラック保育園が増える
昨今では、保育士不足の影響で、保育士を確保するため(保育園の売上を確保するため)、各保育園は様々な待遇改善を行っています。待遇改善は、金銭面だけでなく、休暇や労働時間など保育士の働きやすさを改善するものも含まれます。
また、保育園の人間関係などにおいても、「辞められると困る」ために、優しくする・きちんと育成するという考えが園長などにも生まれやすいです。
一方で、保育士が余ってしまうと、「辞めたら誰か別の人を採用すれば良い」という考え方が生まれやすくなります。待遇を改善する必要がなくなり、人間関係も努力して良くする必要がなくなります。いわば、保育園の方が立場が強くなるということです。
給与待遇が悪化する
保育士があまった場合におこることの一つが、保育士の給与待遇が悪化です。ボーナスがカットされたり、残業代が支払われていたものがサービス残業になってしまったりです。また、新規に採用される保育士は、下限の月給に近い形で雇用されるケースも増えます。
特に、期間を定められて実施されている保育士の待遇改善は、徐々に打ち切りになっていくということが想定されます。「保育士宿舎借り上げ制度」などがそれに当たります。保育士宿舎借り上げ制度は、保育士が居住する賃貸に関する補助になりますが、この制度は、そもそも期間が定められて実施されているので、保育士があまるような情勢になると、打ち切りになる可能性が高いです。
保育士を辞める人が増える
前項までに挙げた保育士があまった場合の既存の保育士への影響は、マイナスな面が多く、保育士として働くよりも別の仕事をしたほうが良いという考え方をする人が増えていくでしょう。そのため、保育士を辞めて別の仕事を始める人も増えることが想定されます。また、それに伴い、新しく保育士を目指す人も減ることになるでしょう。今では、国や自治体などが保育士資格の取得の金銭的な支援なども行っています。奨学金の支給や返済の補助、資格取得の補助金などです。ですが、それらは現状で保育士が不足しているために行われている施策になるので、当然保育士が充足すれば、終了や打ち切りになっていくでしょう。
経営者は当然、簡単で安い人材を雇用する
保育園の経営者は、人件費を削減できるため、コストを抑えられる安価な人材を雇用する傾向があります。
国の見解では、保育の質は「地方裁量型認可化移行施設への定期的な指導・監査の実施や運営状況の見える化」「都道府県の協議会による人材確保策の実施・公表」によって確保されるとされています。
もし、無資格者を雇用しても保育の質が担保されるのであれば、経営者は賃金が安く雇用しやすい無資格者を登用する可能性があります。
特に待機児童が多く、定員がすぐに埋まってしまう状況では、保育園の評判やサービスの向上に力を入れる必要性が薄れるかもしれません。
保育士の資格は将来無意味なものになる?
個人的な見解としては、保育士の資格が全く無意味になるということはないと思います。
ただし、規制緩和が続いて形骸化していくということは十分考えられます。少なくとも、保育士余りの時代になるまでは、国はできる限り保育士ではない人を保育園で働かせて乗り切ろうという意思を持っているように感じられます。
国としては、とりあえず待機児童を減らしたいけどなるべくお金はかけたくないので、無資格の保育人材を活用しつつ乗り切ろうという形です。今後、保育需要が落ち着いてきて待機児童がいなくなったら、今度は保育士が余り出すと思います。
保育士の待遇を上げずに乗り切ったので、待遇は低いままで保育士の雇用が失われるという未来が起きるかもしれません。
AI(人工知能)などの技術革新の影響は?
保育の仕事は、AI(人工知能)に置き換わりにくい産業だと言われています。
そうは言っても一部の業務はAIに置き換わる可能性もあります。例えば、見回りロボットのようなものができると、午睡の際などのSIDS(乳幼児突然死症候群)対策の昼寝番などが可能になります。
「見回りロボットを一台は保育士一人分としてカウントできる」というような規制緩和が将来的には起きる可能性は高いでしょう。
この点で保育士は、AIに置き換わりづらいからといって驕り高ぶるのではなく、質の高い保育を提供し続ける必要があると思います。
雑務はITなどに置き換わり効率化が進む
逆に直接の保育と関係のない事務作業などの雑務はITにどんどん置き換わって効率化されていくと思います。現時点で保育園のIT化は他の業種と比べても遅れているので、今後も改善があるという意味では伸びしろがある部分だと思います。
現状は、IT化などによる業務効率化は進んできていますが、それ以上に保護者などの要求レベルも上がっているので、保育士の業務範囲は拡大しています。
ITによる効率化は、保育園の経営で他の保育園と差別化することができる数少ない部分になります。業務効率の良い保育園は保育士の負担が少ないということになるので、ここに力を入れている保育園が保育士にも選ばれて今後も生き残っていく流れになると思います。
保育日誌なども効率化されて作業負担が減っていくと思います。ピアノの演奏などももしかしたらそこまで必要はなくなるかもしれませんね。逆に言うと、最低限のITスキルは保育士も身に着けた方が良いです。
外国人人材や移民などの影響は?
保育園で仕事を行うには基本的に「保育士」の資格が必要です。実は言うと保育士の資格は日本国籍の無い外国人であっても取得することは可能です。ただし、日本人が受ける保育士試験の受験基準を満たし、同様の試験を受ける必要があるのでただちに保育園が移民の外国人保育士だらけになるということは考えづらいです。
もちろん、政府が規制緩和を行い保育園に必要な保育士の人数を少なくしようとする動きがあった場合は、影響が出る場合があります。すなわち保育士が安価な外国人人材に置き換わり職を奪われるということも有りえます。
例えば、外国人が祖国での「保育士」のような資格を持っているれば、日本では保育士として働けるような規制緩和が考えられます。
祖国の保育士のような資格が、日本の保育士資格のようにしっかりとした試験が行われないものであった場合は、一気に安価な外国人人材に置き換わるという可能性もあります。
実際に現在も大阪府が以下のような提案を国に対して行っています。
国家戦略特区において、大阪府から、所定の研修を修了した「保育支援員」 を保育士とみなして、配置基準上、保育士に置き換えて配置できるようにすべき
(例)人員配置基準上、12人の保育士の配置が求められる保育園の場合、保育士のうち3分の1(4人)を保育支援員(1.5人で保育士1人に換算)に代え、保育士8人・保育支援員6人で保育業務を行う。
※ 大阪府・大阪市の提案について 平成30年4月27日 厚生労働省子ども家庭局保育課 (https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/h30/shouchou/20180427_shiryou_s_2_1.pdf) より
ただし、厚生労働省は以下の理由からこの提案の受け入れは困難としています。
- 「保育の質(≒保育士の配置)の確保・向上」を進める政府方針や現場の実態に逆行している
- 保育は、単なる「見守り」ではなく、教育の性格を含むもの。「保育支援員」について保育士みなしを可能にするためには、保育士と同等の養成課程が確保されている必要
これは外国人に限った話ではないですが、保育士という資格が軽く見られているのでこういう動きが起きています。
このような規制緩和に関して保育士としては、保育の質の低下も考えられるので子育て世代と団結して断固として反対していかなければいけないです。
ベビーシッターによる保育園機能の代替の影響は?
現在も保育園に入ることができなかった待機児童がベビーシッターを利用するという流れがあります。東京都では、待機児童になったお子さんは1時間あたり250円でベビーシッターを利用することができる補助があります。
保育士が足らない部分をベビーシッターでカバー
↓
ベビーシッターは外国人でカバー
ということが起こりえます。現在でもベビーシッターは保育士資格が無資格でも就業するこが可能なので、仮に保育園の保育士の規制緩和を死守できたとしてもベビーシッターへの置き換えは防ぐことができません。
先進国の例でいうと、例えば、香港ではヘルパー制度があり、子育てを含めた家事などをヘルパーに任せる文化があります。ヘルパーのほとんどはフィリピン人で外国人ヘルパーの最低賃金は、月に6万5千円となっています。
日本でもこのような形で安価な外国人をシッターとして利用する流れが進むと保育士の地位が危ぶまれてしまいます。
この点に関しては、いきなり外国人にベビーシッターを任せるということは抵抗があると思うので、日本人にしかできない質の高い保育の提供をすることで、対抗することが可能だと思います。
保育士個人はどうしたら良いか
保育士個人は今後どうしていけばよいかという点を紹介します。
保育士・他業種問わずに転職する・転職できるスキルを身につける
対策としてできることは保育士や他業種に問わず転職できるスキルを身につけることです。今でこそ保育士不足ですが、将来的には保育士が充足する可能性もあります。つまり余ってしまうということです。
保育士が不足した未来では、今のように気に入らないことがあれば違う保育園に転職すれば良いというような考えは通じなくなってきます。保育園も募集をすればすぐに保育士が集まるような状況だと、待遇を改善しようとか働き方を良くしようとは思わないかもしれません。
辞めたいけど新しい保育園に採用してもらえない、他業種に転職するにもなんのスキルももっていない、というような状態だと今よりもさらにブラック保育園に搾取される形となってしまいます。
保育士としてのスキルはもちろん、他業種に転職できるようなスキルを持っていたほうが安全と言えると思います。
保育の質が低い保育園とは関わらない
施設の種類を問わず保育の質が低い保育園とは関わらないほうが無難です。質の低いスキルが身につきますし、保育士はなにかトラブルが起きた場合の責任も重いです。
例えば、福岡県の認可保育園で子どもに対して複数の保育士が暴言を浴びせたというニュースが話題になっていました。
この保育園では、特定の誰かというわけではなく、実に8人の保育士が暴言を浴びせていたようです。このように、特に若手の保育士であれば、その保育園で長く勤めることで、このような正しくない行為が当たり前になってしまい、適切ではない保育スキルが身についてしまうことがあります。周りがやっているからと言う理由で自分も同調してしまうことはないとは言えないと思います。
保育園の保育の質が低いなと思ったら、別の保育園に転職するなどして、なるべく関わらないようにするのが良いです。
【まとめ】保育士の将来性と保育士が生き残るには
この記事では、現役保育士の視点から保育士の将来性について考察しました。真剣に保育士の将来性について考えた結果のまとめになります。
給与水準は改善傾向にあるものの、少子化により長期的には需要が低下する可能性があることを解説しています。
- 保育士の給与は一定水準まではあがる
- 共働きの増加で中期的には保育士の需要は増加する
- 少子化の影響で長期的には保育士の需要は低下する
- ITによる効率化の進んだ保育園を選んで働くべき
- 最低限のITスキルは身につけるべき
- 保育士同士で団結して国を動かす必要がある
- 日本人にしかできない質の高い保育を提供する
- ITやAIに置き換えできない保育スキルを高める
私は保育士という職業は向こう5年~10年は安泰だと思っています。ただしそれ以降は、保育士不足から保育士が余るという未来が考えられます。例えば「英語が得意な保育士」「ITスキルが有る保育士」「体操が教えられる保育士」「プログラミングが教えられる保育士」などは保育士として生き残ることができると思います。保育以外の仕事を副業にするということでも良いと思います。
保育士にも単なる保育スキルだけでなくプラスアルファの付加価値が必要になると考えています。
これらの情報を参考に、将来を見据えたキャリアプランを立ててみましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q保育士の将来性について、現役保育士が特に意識しておくべきことは何ですか?
- A
少子高齢化が進む日本において、将来的には保育士が余る可能性も考慮し、保育士としての専門スキルに加えて、他分野でも活躍できるスキルを身につけておくことが重要です。
- Q保育士の給料は今後どのように変化すると考えられますか?
- A
国主導の待遇改善により、一定水準までは給料が上昇する見込みです。ただし、待機児童が解消された場合は、その後の給与水準は保育需要によって左右される可能性があります。
- Q共働き世帯の増加は、保育士の需要にどのような影響を与えますか?
- A
共働き世帯の増加は、保育ニーズを高めるため、中期的には保育士の需要を増加させると考えられます。しかし、長期的には少子化の影響で、保育士の需要は低下する可能性があります。
- Q保育士の資格は、将来的に無意味になる可能性はありますか?
- A
保育士資格が完全に無意味になることはないと考えられますが、規制緩和が進み、資格の形骸化が進む可能性はあります。特に、保育士不足を解消するために、資格を持たない人材の活用が進む可能性があります。
- QAI技術の進化は、保育士の仕事にどのような影響を与えますか?
- A
AI技術は、午睡の見回りなど、一部の業務を代替する可能性があります。しかし、保育士の創造性や人間性が求められる業務は、AIに代替されにくいと考えられます。
- Q保育士として長く活躍するために、今からできることはありますか?
- A
保育士としての専門性を高めるだけでなく、ITスキルや外国語スキルなど、他分野のスキルも身につけることが重要です。また、常に質の高い保育を提供し、保護者や地域社会からの信頼を得ることも大切です。